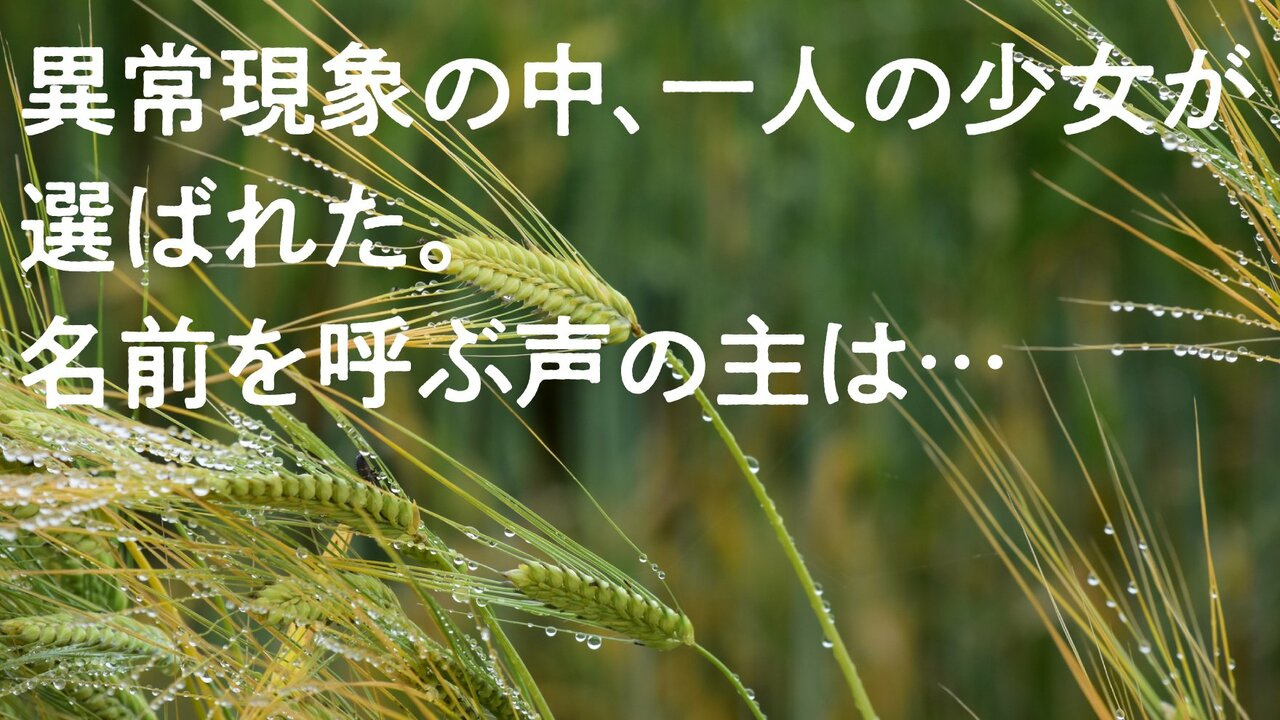異常現象が続いていた。やがて一人の少女が選ばれた。
ある時の春、天地を転がす地震が起きた。その年は、いつもの年とは違い、確かに異常現象が続いていた。涸れるはずのない泉が涸れてしまったのだ。見る見るうちに干上がる湖。このままではこの湖を糧としている村の人々、そして、この鎮守の森の多くの生き物の命が危ぶまれる事態となる。連日、多くの村人が祠に集まり祈りをささげることになった。
連日の猛暑により干上がる湖。そこに現れたのは、湖の最深部にある石の祠だった。平安時代、龍神湖がまだ十分の一ほどの大きさだった頃に湖畔の脇に龍神様を祀って石の祠を作ったのだ。湖底が露わになり、土と石の世界が広がった。土色の臭いの風が巻く。湖底は砂漠のように熱い。
連日連夜雨乞いの儀式がとりおこなわれるが、一向に湧水は涸れきったままだ。業を煮やした村人が神職に願い出た。龍神様に人柱をささげることを。村の長(おさ)に一任され、やがて一人の少女が選ばれた。少女の名は「生(いく)」。龍神様への儀式は翌日の夜と決められた。生は雪より二歳年下であり、雪を姉のように慕っていた。雪もまた、生を妹のようにかわいがっていた。二人は背格好も同じ、声まで似ていた。村人の誰が見ても双子の姉妹のように見えた。
儀式の前夜、雪は巫女装束の身支度を整えると、眠っている父母に深々と一礼をした。物音を立てぬよう静かに家を出た。そしてもう一度深々と一礼をすると、小走りに走り始めた。その背中には強い思いがみてとれる。いつの間にかその脇を白狐が並走していた。白き疾風が森を突き抜けて行った。