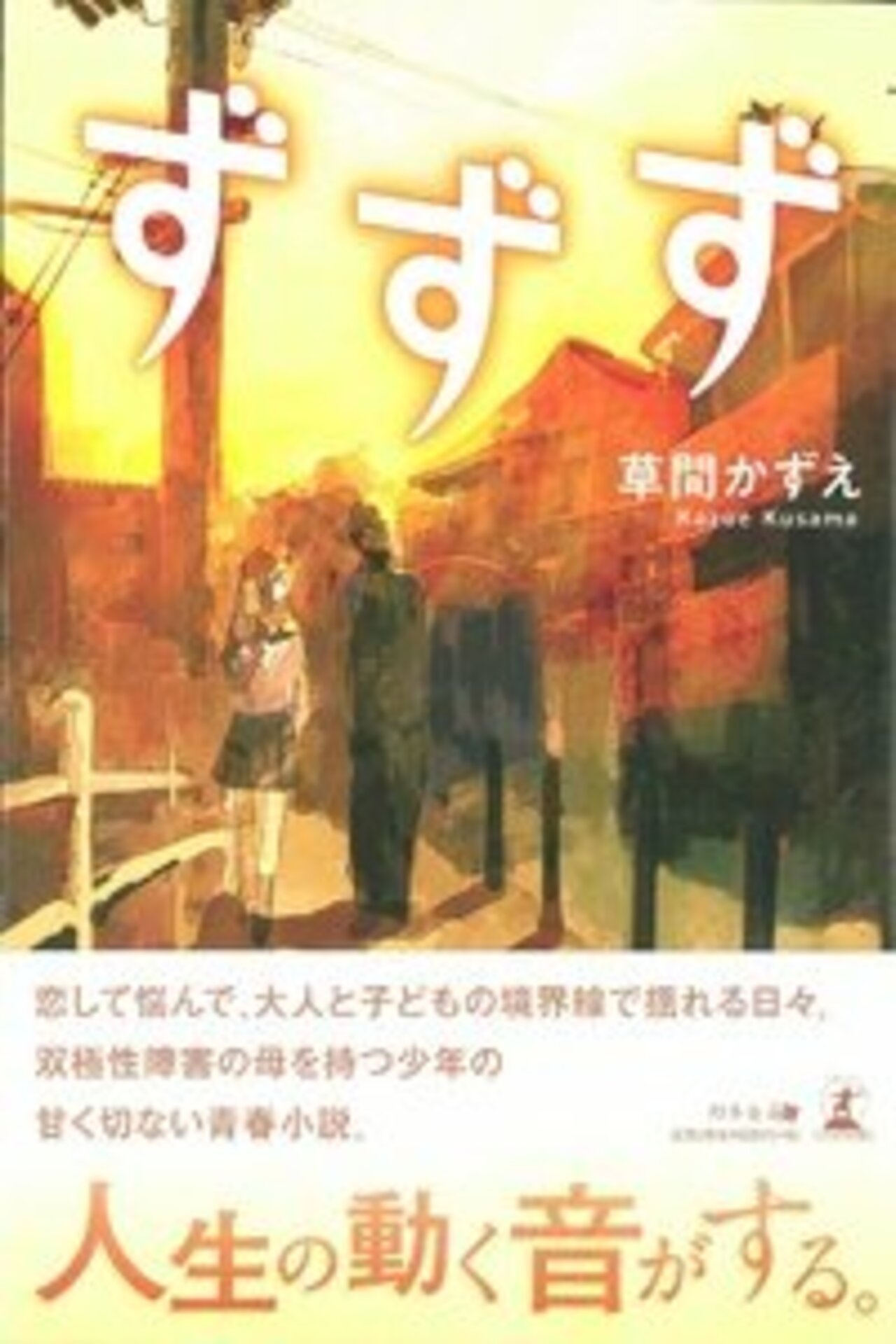もちろんアッキーもなかった。びっくりする程、ふぁっと軽くて流線の形をしたそのドーナツの食感にひまりが歓声を上げた。
「田畑さん、すっごい美味しい~美味しい、美味しい~です」
「良かった。悩んだけれど、これ、アッキーママも大好きでね、差し入れをすると喜んでくれるんだ。アッキーママはドクターの許可が出ないから、売店に行けないんだよ」
「えっ、売店に行けないんですか? どうしてですか?」
「どうしてなんだろうね? 僕にもわからないんだ」
「アッキーママは、このフレンチクルーラーが好きなんですね、私も好きになりました」
ひまりと田畑さんの二人は会話が弾んでいた。それなのに、アッキーのフレンチクルーラーはまだ透明な小さな袋に入ったままだった。
田畑さんはアッキーに『どうぞ、食べて』と言わないのである。けれど、どうぞと言われてもご馳走になる気持ちにならずに、透明な小さな袋をただただ、見つめているアッキーだった。