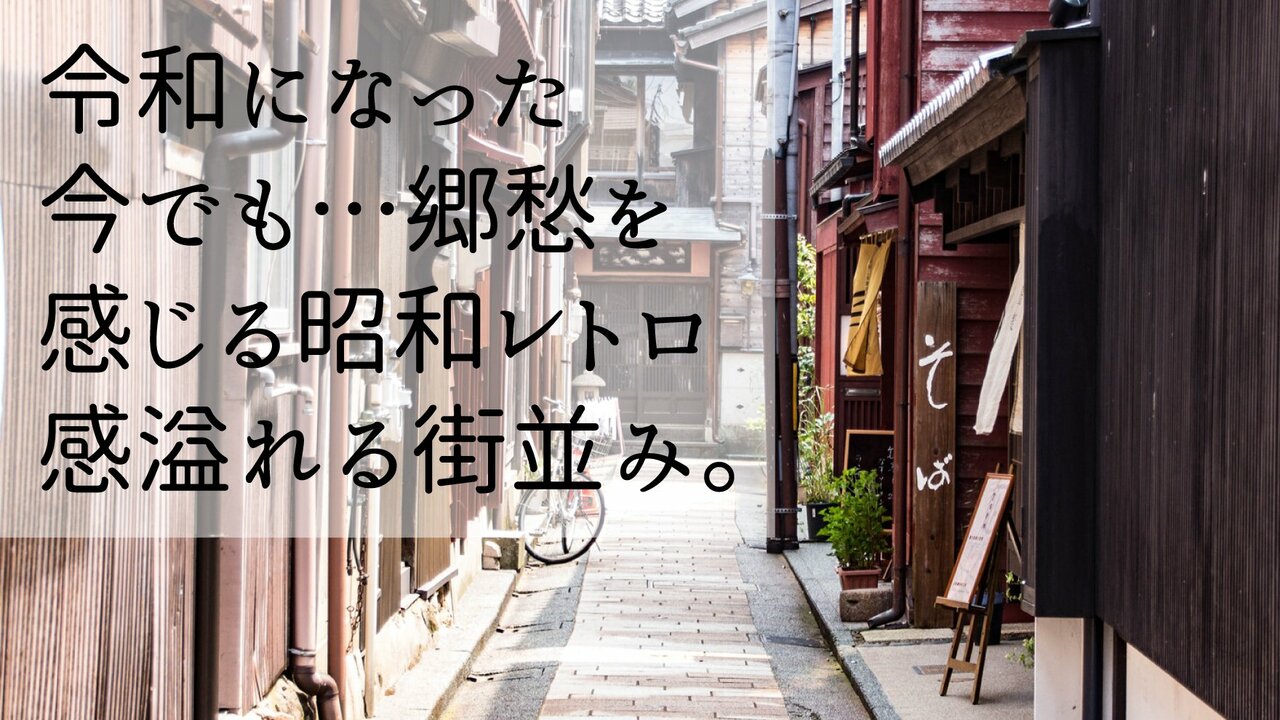お楽しみの風呂は、外国の団体客との鉢合わせを避けるべく、午後十時からと遅めにする。大浴場には、先客が数人しかおらず、ほぼ貸し切り状態。仄(ほの)かな硫黄臭を楽しみ、熱めの湯に浸かる。湯は多少ヌルヌル感がある程度。
露天風呂に入ろうと外に出る。「寒い」。思わず声が出てしまう。八月なのに、改めてここは北海道だと実感する。檜風呂で夜空を眺めていると長男・次男が来て、僕の隣に並んで浸かる。僕は、幸せな気分に浸(ひ)たる。
似た顔が三つ並んで湯に浸かっているので、僕たちの前に浸かっているお爺さんの視線が、僕・長男・次男、そして次男・長男・僕、またまた僕・長男・次男と往復するのがおかしかった。
息子たちの成長につれて親子の会話は減っている。この絶好のシチュエーションで会話を弾ませたいが、もう胸が一杯になっており、それに何故かテレてしまって言葉が見つからない。
芥川龍之介の小説に「芋粥」がある。平安の世のこと。摂関家に仕える貧しい侍が、たまたま以前から楽しみにしていた芋粥を食べる機会に恵まれた。
「これを飽きるほど食べたいものよ」と呟いたのが、同席していた摂関家に連なる裕福な藤原某の耳に入った。藤原某は侍を自分の領地に招き、大鍋一杯の芋粥を出したところ、たちまちに侍の食欲がなくなり、茶碗一杯の芋粥を食べるのに難渋したという話である。今の僕は、まさにこの侍である。
結局、出た言葉が「お父さん、先に上がるから」だった