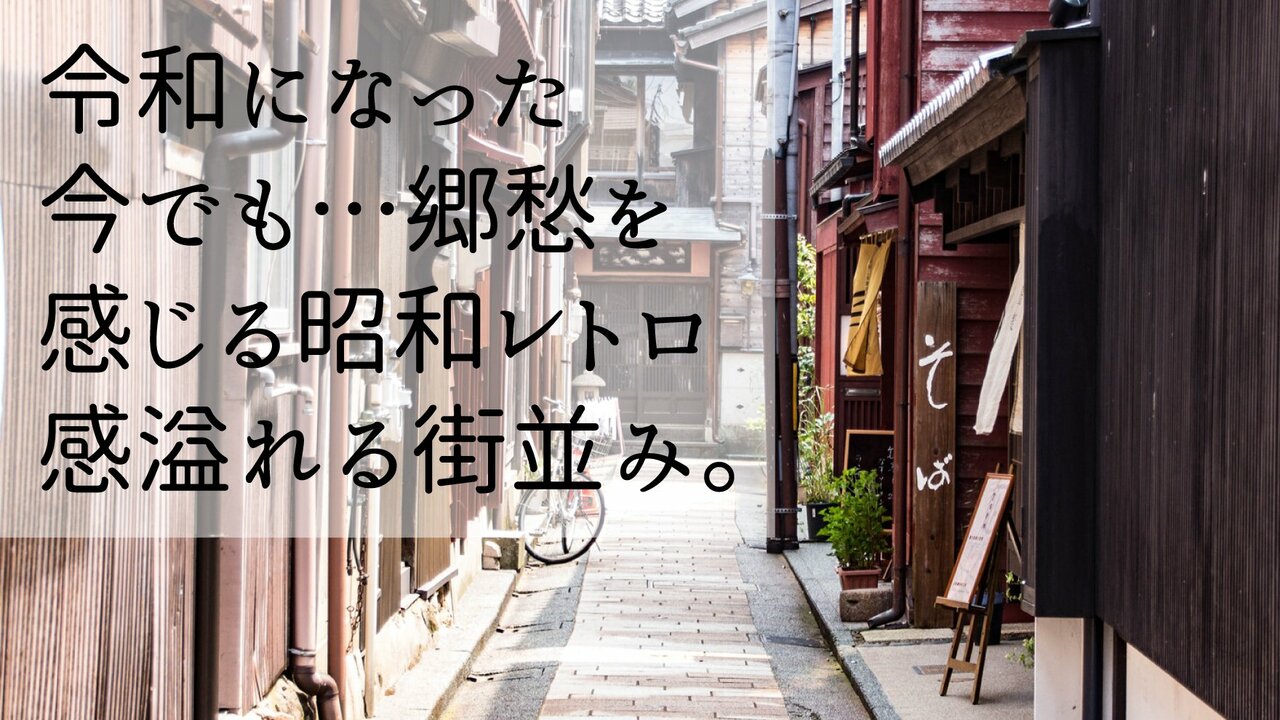廃屋満タン 二〇一六年五月
懐かしい汲み取り式便所の臭いに噎せつつ足を踏み入れる。
何だ! これは。凍りつく体。古雑誌、割れたビン、名も知らぬ虫の死骸が床一面に散乱する。天井の至るところには蜘蛛の巣。
二つしかない男性用小便器の一つには、新聞紙と雑誌が無造作に詰め込まれ使用不能状態。ひび割れて茶色く変色した窓ガラスを通して差し込む陽光は便所の空気をセピア色に染める。
真昼というのに、すでに夕闇が支配している。スティーブン・キングのホラー映画の世界に迷い込んだのではないだろうか。
夜ならば、怖くて絶対にここで用を足せない。むしろ、県道の明るい街灯の下で、行き来する自動車を眺めながら安心して用を足すことを選ぶ。怖いんだもの。
しかたなく、残った一つの小便器で用を足し始める。ドンドンドン。威嚇するように壁を叩く音が聞こえる。音は店内からではない。
音の出所は、小便器とならんである大便用個室からだ。家族連れはまだ店内だし、作業着の男性は既に食べ終わって車で出て行った。他に来客の姿を見ていない。
じゃあ誰が、いや一体何が中で……。ドンドンドン。「アカンがな、アカンがな。ヤバイことになってるでぇ」。
何故か、恐怖を関西弁で誤魔化そうとする僕(九州男児なのに)。ドンドンドン。しつこく壁を叩き続ける。ドンドンドン。
「ち、ちょっと待って……、お母ちゃん、助けてぇなぁ」。
ドンドンドン。
「早う、終わってぇー、僕のオシッコ」。
窓の外では、女房が春の日差しを浴びながら、眩しそうに田園風景を眺めている。二人の状況のなんと見事なコントラスト。スティーブン・キングの映画のストーリーならば、このあと僕は惨殺され、僕を探しに便所に入った女房も……。
駐車場には持ち主を失った車がそのままに。ドンドンドン。「堪忍してぇーな」。
永遠にも思われたオシッコが終わり、今は恋しくてたまらない退屈な日常の世界へと僕は飛び出していった。
二〇一九年十二月 秘湯への憧れ
ここは、俵山温泉。
今、僕は、湯に浸かり、胸・腹・背中・腰といったところに二十㎝はありそうな切り傷を持つ男たちに囲まれている。
さすがに、ジロジロ見るのは憚られるので、目のやり場に困る。浴槽内で泳ぐことはマナー違反であるが、先程から、目が泳ぎっ放しである。
なぜこのような事態になったのか。一週間前、仕事帰りの通勤電車内。年末にどこの温泉に行くべきか悶々と悩んでいた。かねがね秘湯に行きたい、秘湯に浸かり侘び湯を堪能したいと思っていた。