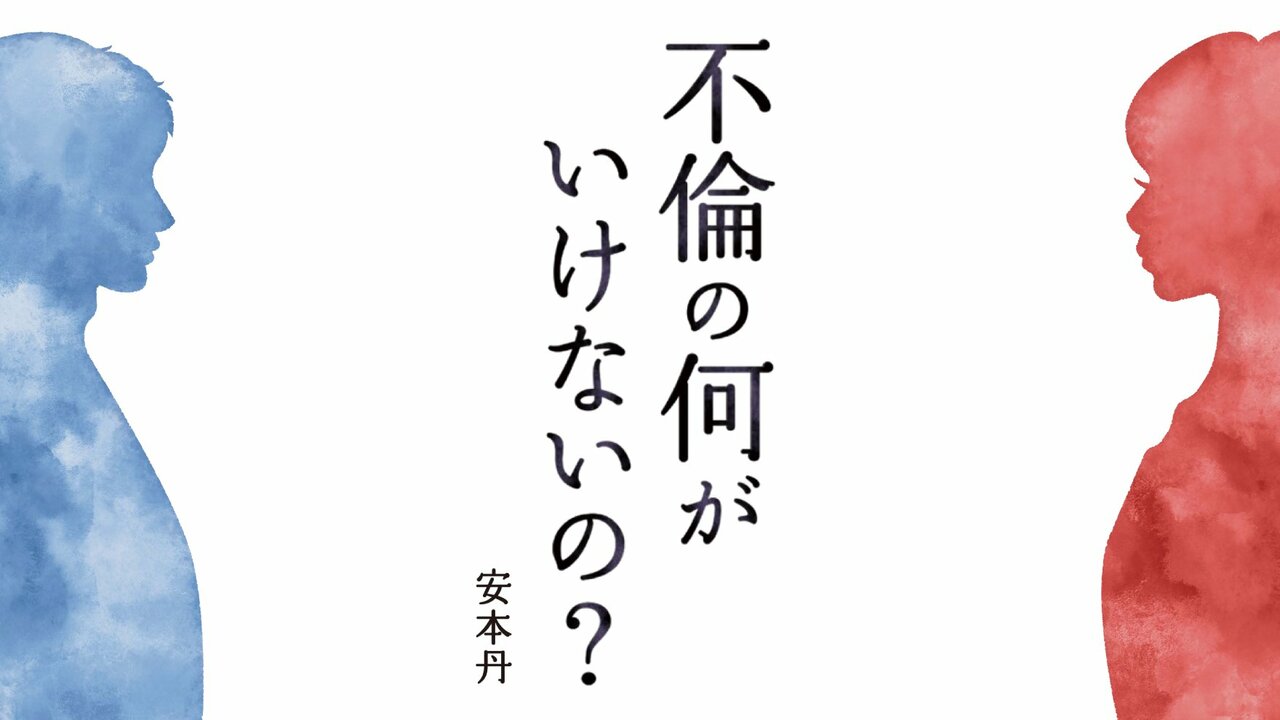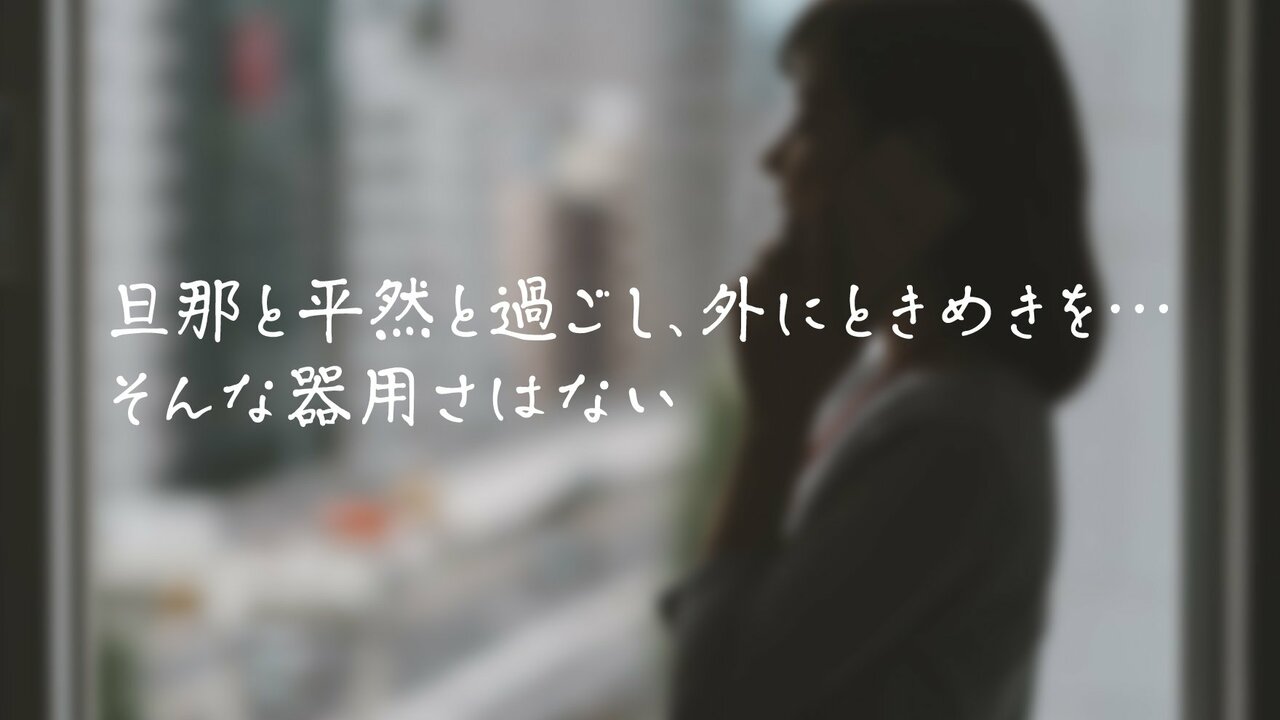第十一章 インフルエンザ
身体を弄(まさぐ)ったのが故意だったのか、寝ぼけていたのかやはりはっきりさせたいと思ってしまった。彼のバルセロナの土産話とは全く脈絡もなく、私は話を切り出した。
「さっき、私に抱きつかなかった? ごめん、私の夢かもしれなくて、確証はないんだけど」
私も眠っていた。もしかして、私の悪夢なのかもしれなかった。旦那への嫌悪感が募るあまり見てしまった悪い夢。
もし夢であれば、抱きつかれたというのは私の妄想に過ぎない。そのような妄想をしたことを吐露する恥ずかしさよりも、私は彼の行動の真意をはっきりさせることを選んだ。
すると旦那はふと思い出したかのような口ぶりで話した。
「あぁ、僕も夢かと思ったんだ。君に抱きついた気がして。でも夢じゃなかったんだね」
無意識だったことが分かっても、私の気持ちが晴れるわけではなかった。旦那も男なのだということを、どうしても認めたくなかった。
彼は男らしさとは対極にいる存在だった。それは普段の振る舞いしかり、性欲の少なさしかり。私が僅かでもセックスに対して消極的なさまを見せれば、彼はそれ以上求めてくることはない。
しかし、無意識に求めてしまうことは、彼自身防ぎようがない。こうして同じベッドで寝ているということは、そういう危険を孕んでいるのだ。
それで――。旦那が続けた。
「急に抱きつかれて、どう思ったの?」
なかなか核心を突いてきたな、と感じた。ここでの回答は明らかに今後の夫婦生活を左右する。一緒に暮らしている以上、あまり険悪な雰囲気を漂わせるのは得策ではない。ある程度、旦那の機嫌も取っておかねば、ショウ君とのデートにも支障が出かねない。
しかし、嬉しかった、そんな心にもないことを言える筈もなかった。そこから始まる情事に、私は応えられないからだ。上手く不倫をするのなら――、私は考えた。そう、私がしているのは紛れもなく不倫だ。不思議なことに、その意識は驚くほどに希薄だった。罪悪感すらない。
むしろ、私に不倫をさせている旦那の甲斐性のなさを情けなく思うほどだった。