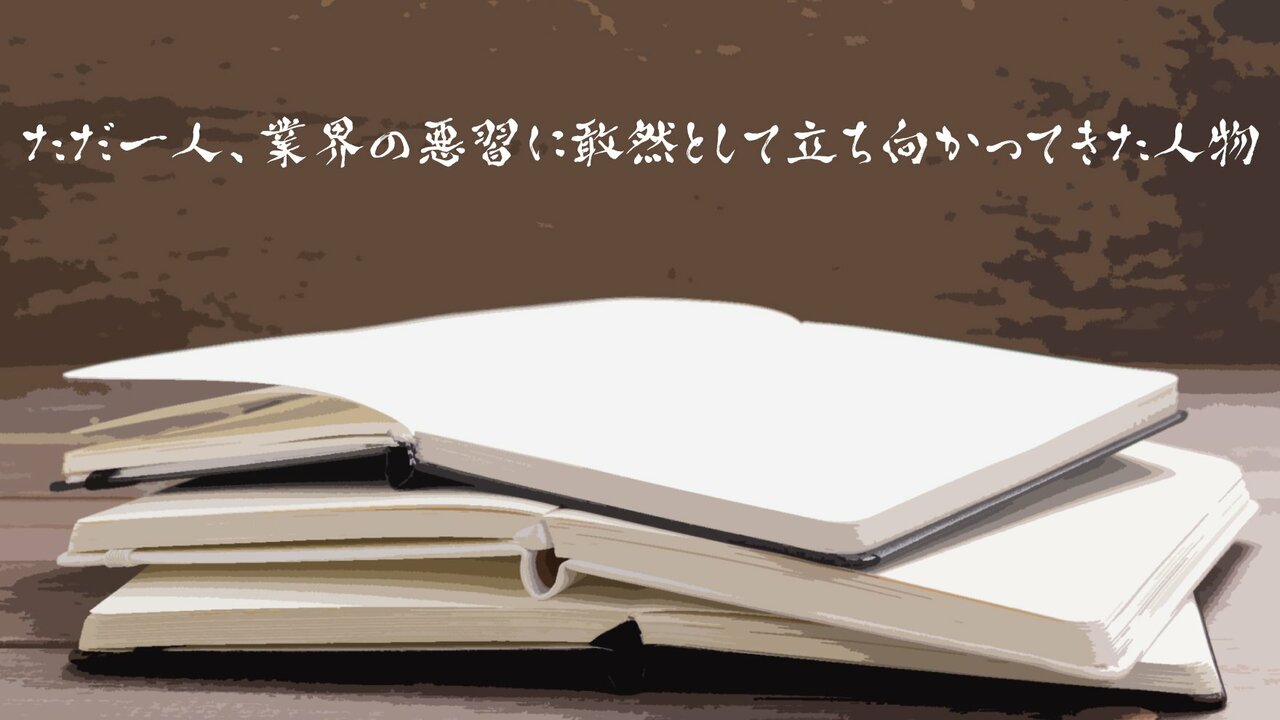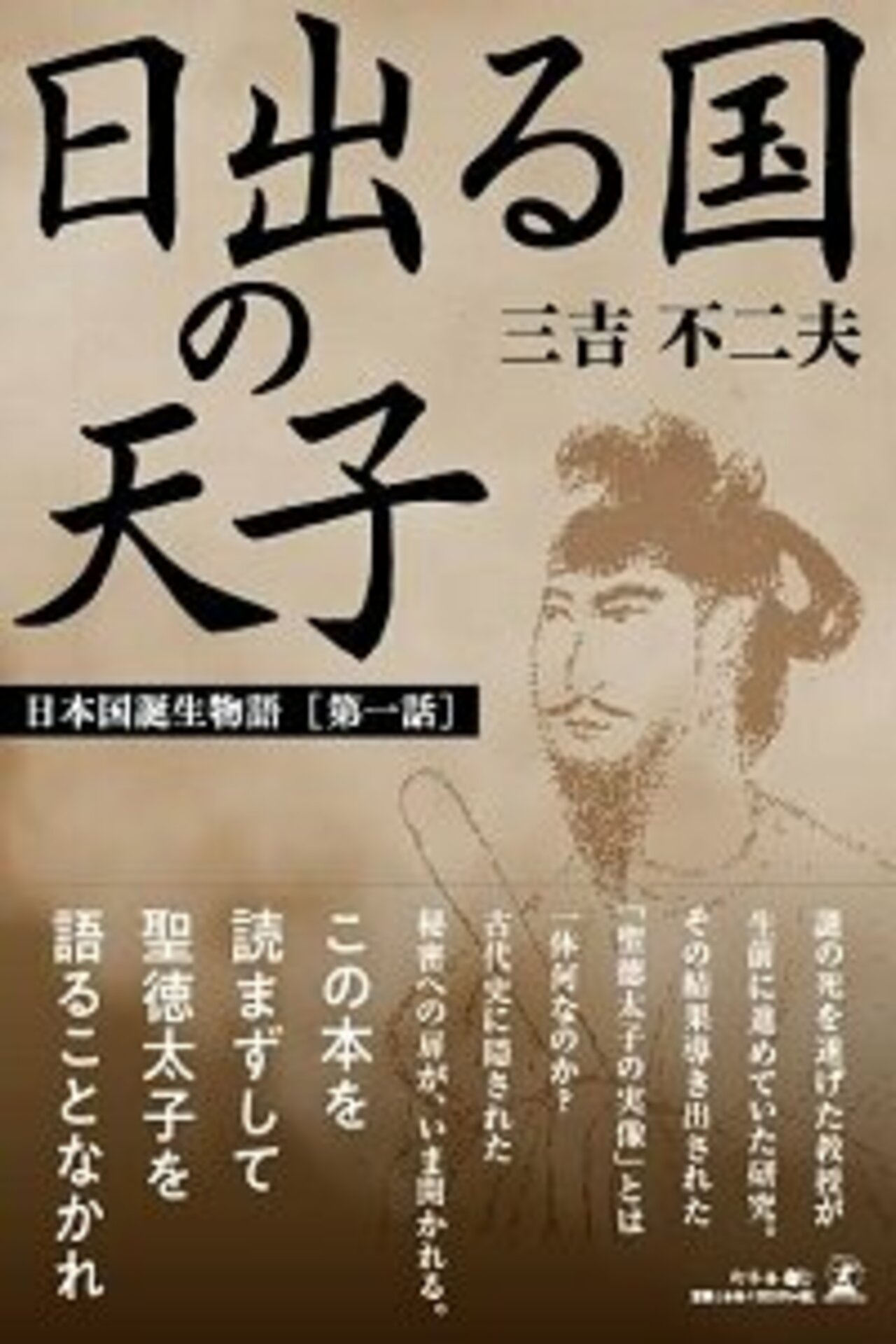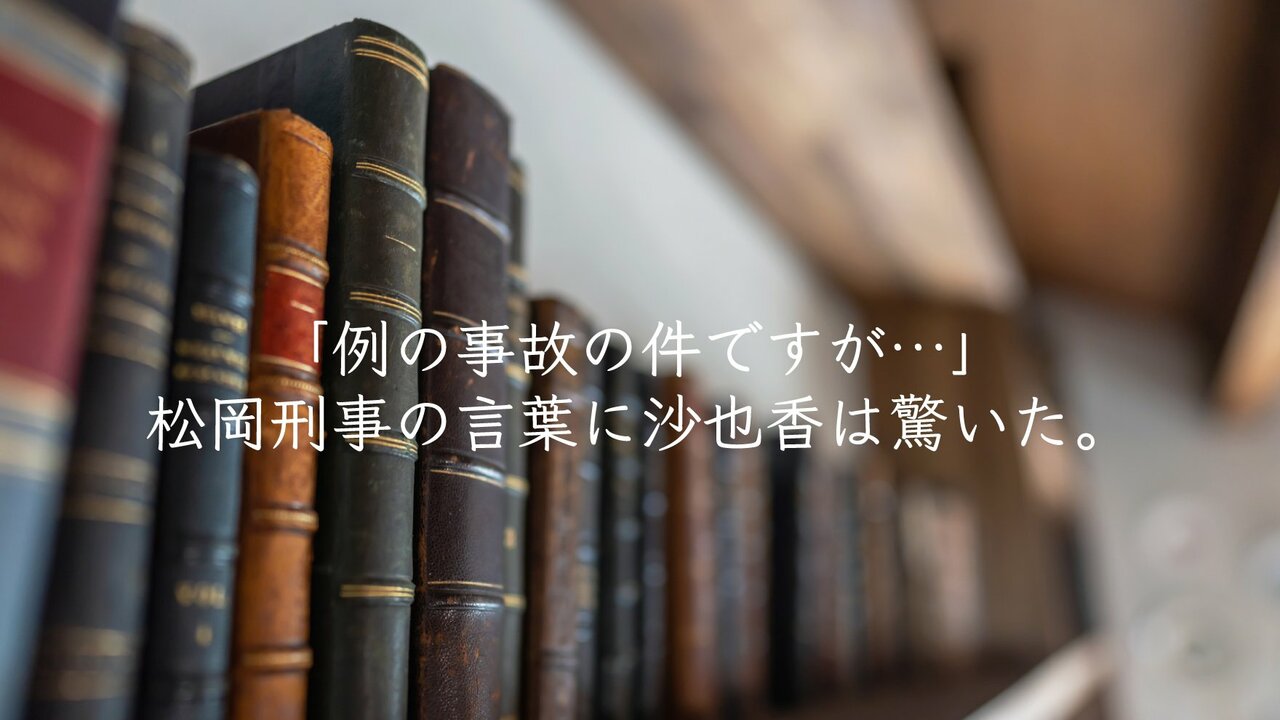第一章 ある教授の死
4
「いいえ、そんなにお礼をいわれるほどのことではありません。これはわたしの研究のためでもありますから」磯部は笑いながらいった。「じつはここに来て資料整理を手伝っているのは、高槻先生がどんな研究をされていたのかを知りたいという目的もあります。むしろその目的のほうが大きいかもしれませんね」
「なるほどな。研究成果を盗もうというわけや」
山科が感情を見せない声でいった。よけいなことをしてくれる、という表情(かお)だ。
「そんな卑しい根性からじゃありません」磯部もむっとした表情になったが、すぐに平静さを装った。「高槻先生は、まずこれから行う研究の目的と方向性を整理し、次には途中経過、そして結果の整理、それらを分析してみたとき、そこからどんな成果が得られたのか──そういったことをきちんと記録として残されています。これは研究者として見習うべきことです。今回、それを改めて教えていただきました」
磯部には、なぜ山科が不機嫌な態度をとり、沙也香に辛辣(しんらつ)な言葉を投げかけるのか、その理由がよくわかっている。
素人はただの直感だけで、なんの学術的な根拠もなしに、学者が精緻な研究成果をもとにして導いた結論に茶々を入れてくる。それに対して反論すると、言い訳だという。まともな議論が通用しないから、学者側としては無視するしかなくなる。
ただし、その反論が学者の詭弁というべき場合も多くあり、正統な論が在野の研究者から提出されることがしばしばあるということも磯部は認識している。
だがそうした正論さえも、学者は無視してきた。そんな悪癖に対し、磯部は義憤を感じることがある。だが自分の研究者としての安泰を思うとき、長いものには巻かれろという日本人の慣習に逆らうことはできなかった。
しかし、彼の知るかぎりではただ一人だけ、そんな悪習に敢然として立ち向かってきた人物がいる。それが彼の恩師、高槻教授だった。
「たしかに高槻君は立派な研究者やった」山科教授は突然口調を改めていった。「しかし、それは彼の何十年というまじめな研究生活のたまものや。それをやな、素人はんがほいっと出てきて、彼の研究成果を理解したろういうたかて、そんなことできしまへんで」
「それはよくわかっております。ですからわたしは、一から勉強させていただく覚悟できています」
「そんなこと、無理や、無茶や、いうとんのやがな」
「やってみなければわからないでしょう」
山科から一言いわれるたびに、沙也香の心の中で意地の虫がどんどん大きく成長していた。その虫が心を征服するのを阻止することはもはや不可能になりつつある。
「なんとまあ、気の強いおなごはんやな」山科もさすがに苦笑した。「そんなら気の済むまでやってみなはれ。せやけど、一生かかっても高槻君には追いつけんと思うけどな」