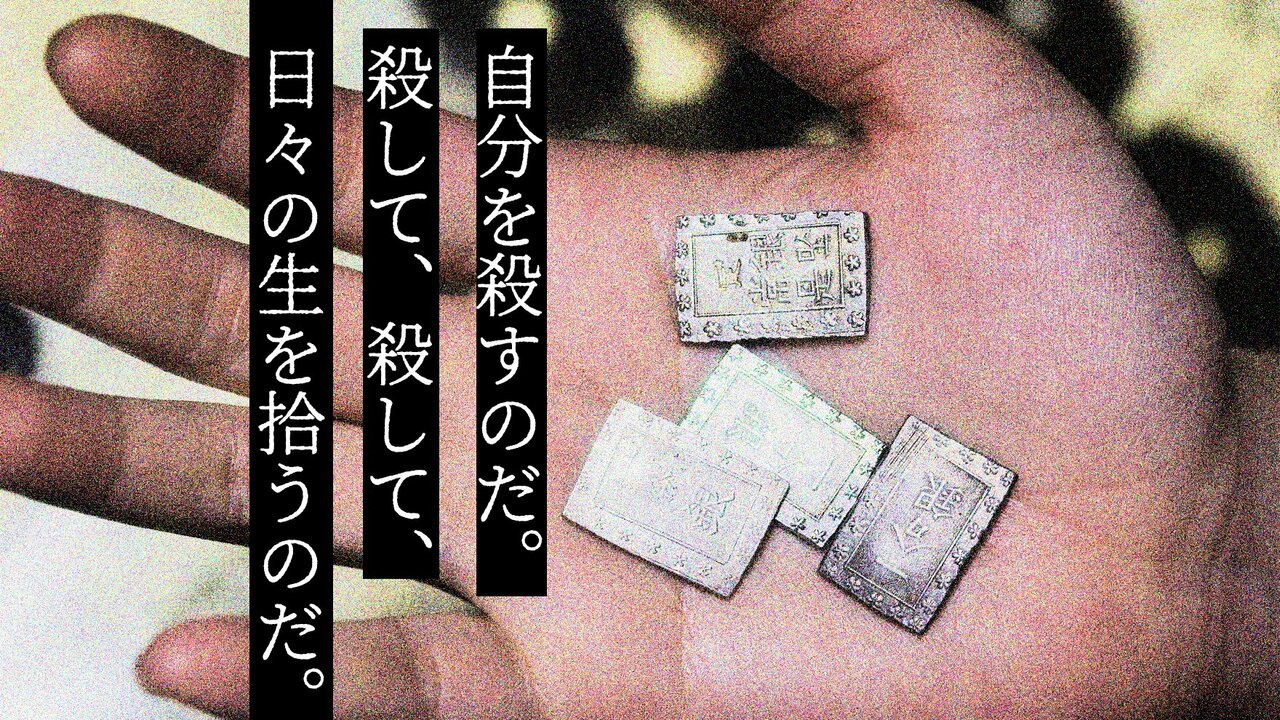弐─嘉靖十三年、張(チャン)皇后廃され、翌十四年、曹洛瑩(ツァオルオイン)後宮に入るの事
(3)
とびらの前立っていたのは、管姨(クァンイー)である。
「石媽(シーマー)が、病気だって?」
「脈をみてみましたが、ただのカゼでしょう。二、三日もすればなおると思います」
「医者でもないくせに、よけいなことをするんじゃないよ」
せなかに罵声をあびながら、門外へ出た。
屋台をすえて、幌をかける間も、管姨(クァンイー)の憎々しげな顔がチラチラした。
――忍辱(にんにく)行は六波羅蜜(ろくはらみつ)の一、無上のさとり阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)へ通ずる道なり。
――自分を殺すのだ。殺して、殺して、日々の生を拾うのだ。
そんな言葉を反芻するものの、心は晴れない。抑えようとしてもむくむくと頭をもたげて来る反抗心。捨てなければならないものにちがいないが、はたして、心が捨てられるものだろうか……空があかるくなって来るのとはうらはらに、気分は暗くしずむばかりであった。明けない夜はないというが、ほんとうかね?
はーっ。
ため息をつくと、わき腹のあたりから、女の声がした。
「あまったの、くれないかい?」
回教徒の隊商がやって来たとき、目抜き通りに連れて行けとせがんだ女であった。わるいが、今はそんな気分ではない。
「ほかの店に行ってくれ。いそがしいんだ」
「なんでもいいんだよ。あたしみたいな人間にもほどこしをあたえるような人は、きっと、いっぱい功徳をつむことになるよ」
物ごいの鼻は、押してもどうにもならない人種と、情に訴えれば何かが出てくる人種とをちゃんとかぎわけて、後者だとみれば、かんたんにはひき下がらないのであった。
「……これで、どうだ」
湯(スープ)をとっただしがらをさし出した。女は礼もいわずに、骨から落ちそこねた残り肉をこそげとって、口へはこんだ。
「今日も、いないねェ」
「うん?」
「あんたのお友だちだよ」
このところ、おもちゃ屋のおやじが姿をみせず、屋台一軒ぶんの空間が、まるまるあいている。