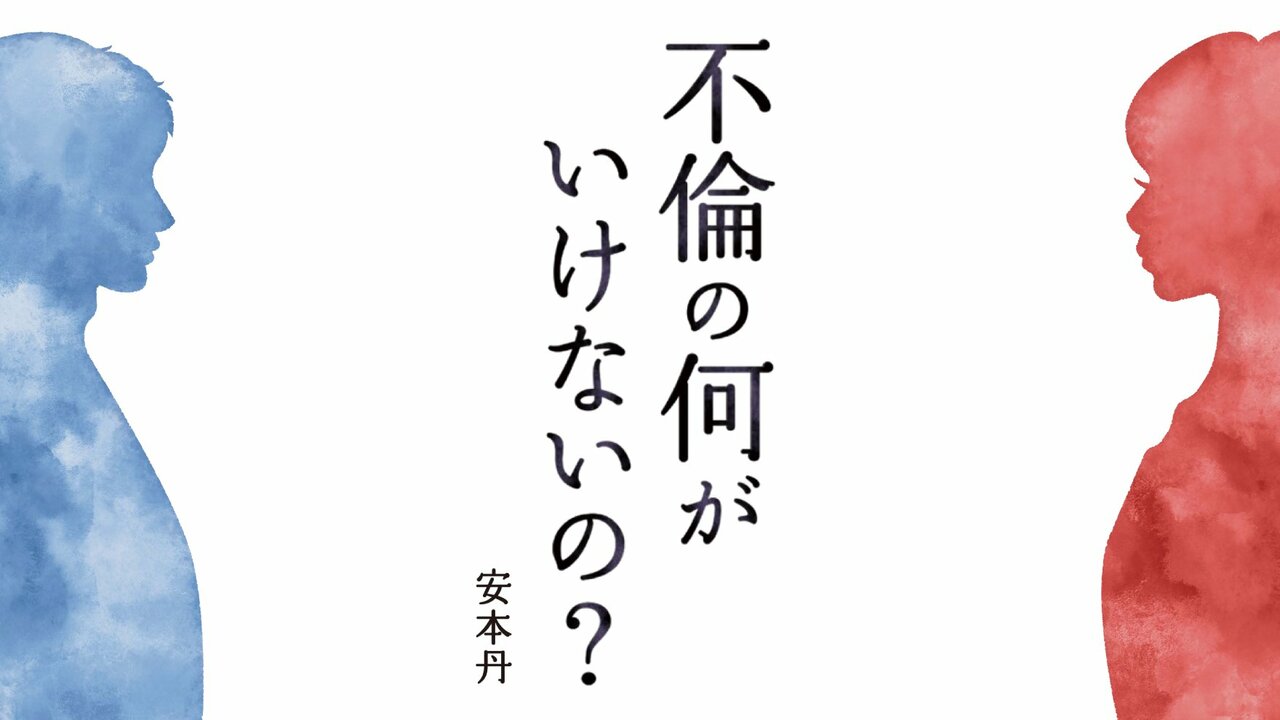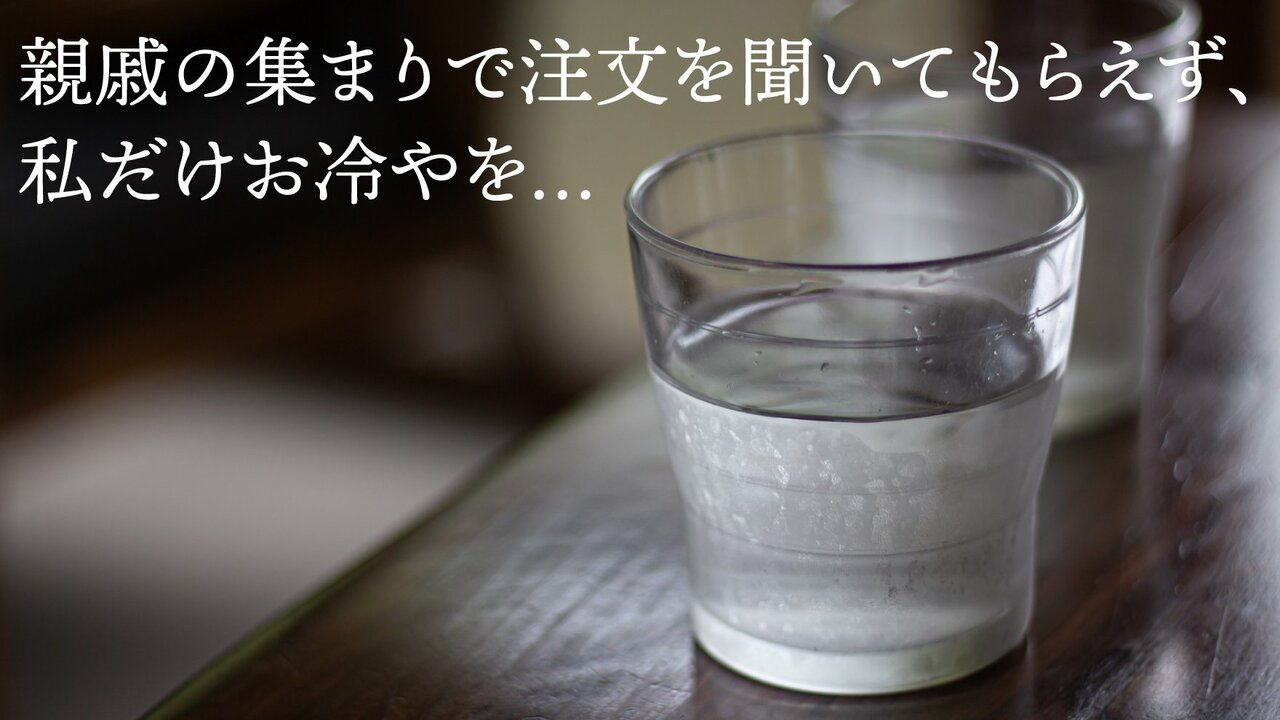第八章 結婚の理想と現実
離婚している姑との付き合いはもっぱら姑側の親戚達も含めた食事会が多かった。主な参加者はハギの祖母にあたる姑の母親、姑の兄夫妻とその子供たち。姑はその集まりではリーダー格で全てを仕切っており、会話は全て姑を中心に回っていた。姑は全員に会話のパスを回したが、私には一切触れることはなかった。私はまるで空気のようにただそこにいるだけだった。
家に帰り、もうあの集まりには行きたくないとハギに愚痴をこぼした。
「そんなに嫌なら次から参加しなきゃいいんじゃないの?」
まるで他人事のように彼は言った。空気のように扱うくせに、いざ参加しないと言うと姑は、親戚の集まりすら顔を出さないなんてろくな嫁じゃないと私を罵るのだった。
ある時はレストランで、姑が一人ずつに飲み物の注文を聞いていたのだが、私の注文だけ聞いてもらえないことがあった。
「烏龍茶が五つと、カルピス二つね!」
私以外の注文を受けた姑が代表して、朗らかな声で店員に話しかけた。私は仕方なく一人だけお冷やを飲んだ。
そんな混沌とした光景に、ハギを含め誰一人として疑問を持たないのが実に不可解であった。いや、気づいていても何も言わないのだろうか。この集まりでは、姑が法である。
不思議と辛いとは感じなかった。むしろあまりにも子供じみた姑の態度に呆れ果て、共感を得ようとハギに小声で訴えた。しかし彼はたまたまだと一蹴した。しかしその後、食後のデザートを頼むときも、やはり私だけ注文を聞いてもらえず、ハギを見ると彼は黙って自分のデザートを私に分けただけだった。
「どうして! どうして何も言ってくれないの? たまたまじゃないでしょ? 目の前で見てたでしょ?」
家に帰ってからハギに詰め寄ったが、彼は私を庇うことは火に油を注ぐことになると言うのだった。私は納得できなかった。この人は自分の親が怖いのだ。そして私なんかより親のほうがよっぽど大切なのだ。
ハギは私に対してはなんとか優しくしようと努力してくれる。しかし私はハギに強い不信感を抱くようになった。
そんなある日、私はハギの携帯を勝手に見てしまった。きっかけはバドミントンサークル『ジョイナス』への久しぶりの参加だった。
結婚と同時に実家があった地元を離れ、お互いの職場がある都会に引っ越してからも、私はジョイナスに時折顔を出していた。
ジョイナスの参加費は一回五百円。しかし地元までの高速代は往復二千円もする。それを払うのは馬鹿馬鹿しいので、私は下道で二時間かけて帰省できる時間的余裕があるときにしか、ジョイナスに参加しなかった。