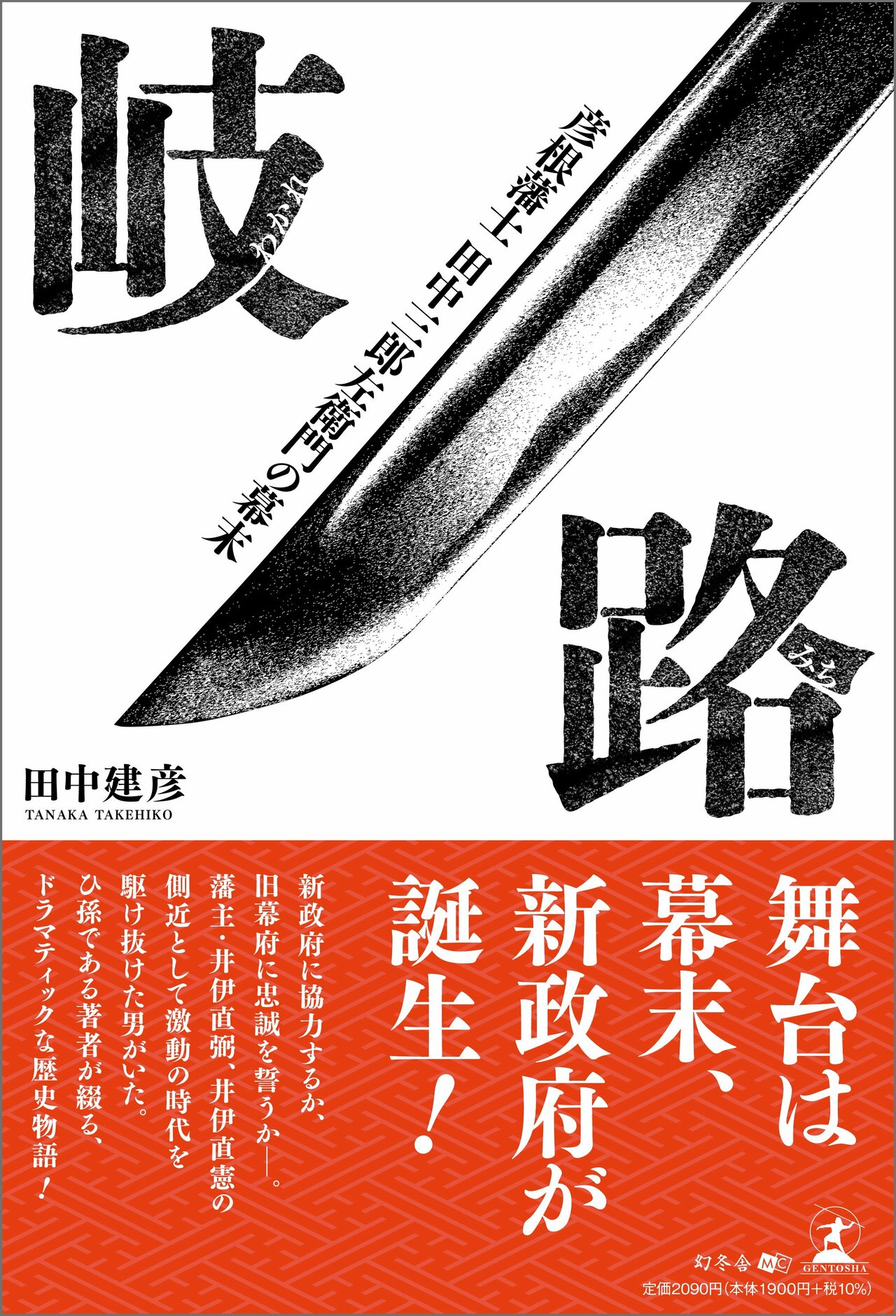弘化二年(一八四五年)、殿が参勤のため江戸に向かった。徳三郎も小姓として随行した。直亮はすでに藩主の座にいること三十年、一度は大老にもなったことがあったが、この頃は国事にも藩政にもあまり積極的な関心を示さなくて、重臣たちに任せっぱなしであった。それでも何か言い出すと重臣たちの意見に耳をかさずに強引に我意を通すというところがあった。
幕政を担当している老中たちや諸藩の学者たちの中には、阿片戦争で隣国清を打ち破ったヨーロッパ諸国が、次に攻めてくるのは日本ではないかという危惧を口にし始めていたが、殿はあまり関心を示す様子がない。
中屋敷留守居の、村山長紀、三浦鵜殿(うどの)ら、また表用人の田中三郎左衛門、新たに表用人に加えられた宇津木六之丞、表用人補佐役の山本伝八郎らが走り回って情報を集め、それを分析して重臣会議に提出して彦根藩の取るべき道を進言していたが、殿は「ふむ、ふむ」というだけで、特別な関心を見せず、「よきにはからえ」というだけであった。
弘化三年(一八四六年)の正月の諸行事が一段落した十三日、父三郎左衛門は表用人のまま城使役を兼帯するように言われた。
城使というのは江戸城に藩の使いとして出向き、幕府の藩に対する指示を受けたり、あるいは藩の要請や質問を届けて答えをもらってくる役目である。
父が城使役となって間もない一月の二十五日、徳三郎は上屋敷での小姓の役目を終えて中屋敷に戻ってきた。昼食時、この日非番であるはずの父の姿がなかった。
芳蔵に聞くと、「奥に御上がりでございます」というだけで、何の用事で出向いたのか一向に要領を得ない。「奥」というのは中屋敷の「奥」で、そこには次の藩主となるべき世継ぎの直元の居室があった。
徳三郎は何か直元と相談することがあったのであろうと、軽く考えていたが、夕食時になっても父は戻ってこなかった。
なんとなくいつもと中屋敷の様子が違うように思えたが、それが何か判然としないまま時を過ごしていた。
【イチオシ記事】「抱き締めてキスしたい」から「キスして」になった。利用者とスタッフ、受け流していると彼は後ろからそっと私の頭を撫で…