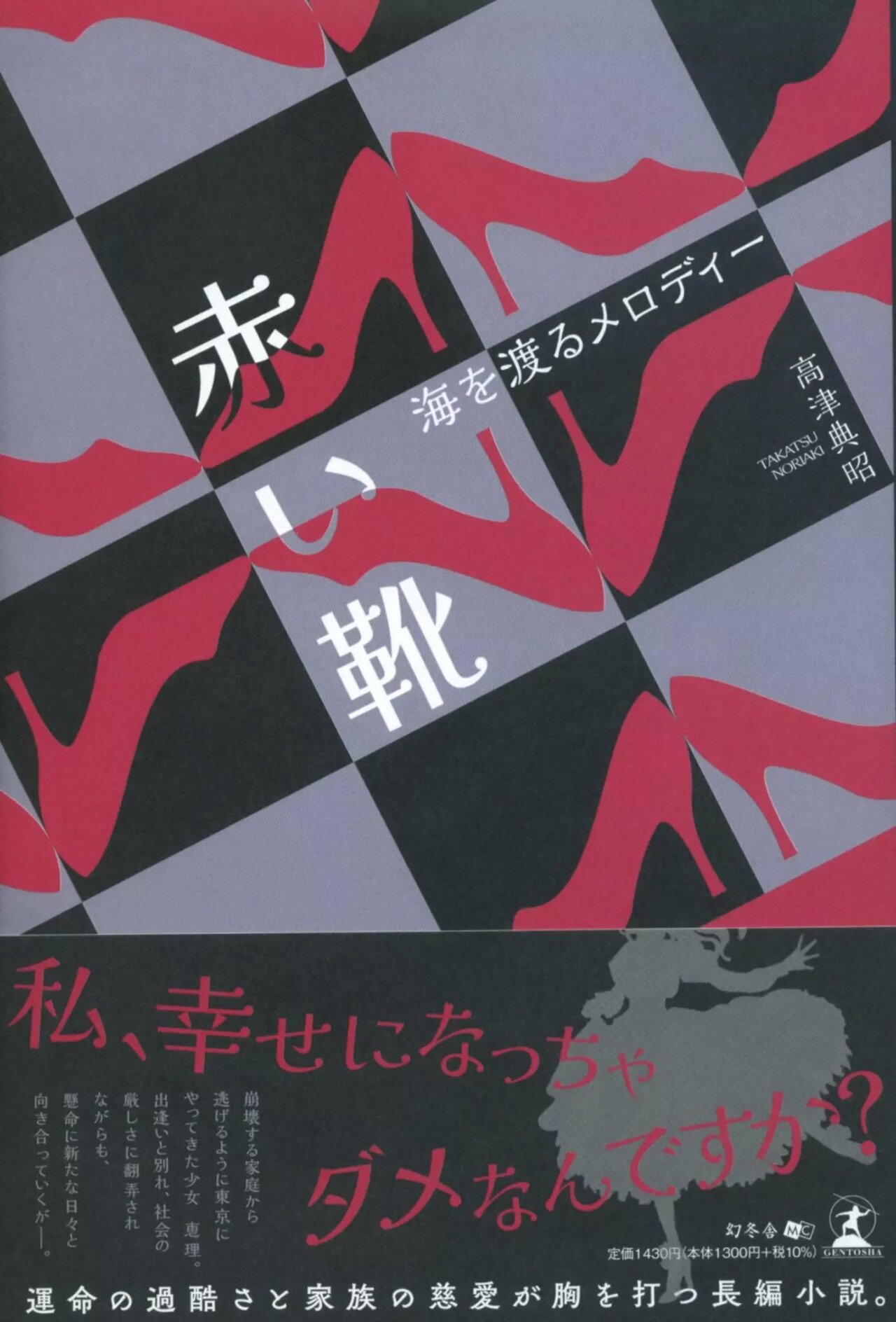翌朝、学校は春休み中とはいえ、来年度の生徒の受け入れ準備や会議のため野口は通常の出勤日である。野口も恵理も目覚ましで起きた。やはり、二人の間には何も起きなかった。
「おはよう」
「おはようございます、野口さん」
「あ、君はまだ寝てていいよ。出航時間は13時だろう?」と言いながら机の引き出しを開けた。
「この名刺持って行きなよ。俺の親友なんだ。渋谷の広告代理店で営業マンしてる。いい奴だからいろいろ世話をしてくれるだろう。この名刺には携帯の電話番号も書いてあるから東京に着いたらすぐにでも頼ればいいよ。俺からも彼に電話しておくから」
「何から何までありがとうございます。それじゃあ、名刺いただきます」
「いただきますって、その名刺食べちゃあだめだぜ」
「やだあ、先生。食べる訳ないじゃん」
「そうか、それなら良かった。じゃあ、俺は仕事行くから。君は適当な時間までこの部屋でゆっくりしていればいいよ。出る時は、この鍵をかけてね。鍵は郵便受けに入れといてね」
「はい、そうします」
「それじゃあ、東京で頑張ってな。それが元担任から贈る言葉だ」
最後まで野口は恵理に対して誠実だった。
【イチオシ記事】「明るくて…恥ずかしいわ」私は明るくて広いリビングで裸になる事をためらっていた。すると彼は「脱がしてあげるよ」