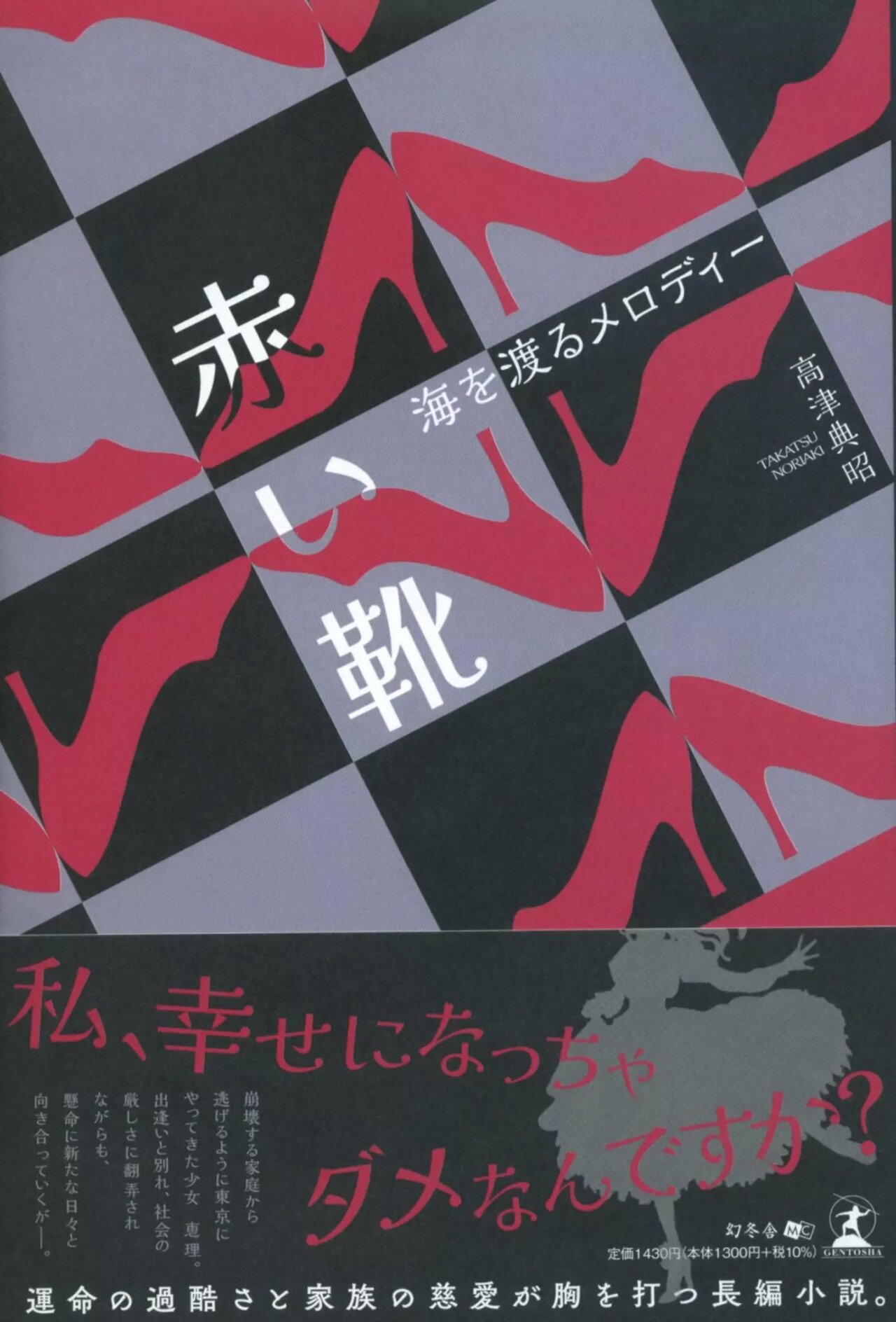さあ、好みの女子が転がり込んできて、泊めてくれと言っている。野口の頭の中は天使と悪魔が交錯している。
「お布団敷くね。シーツは洗濯してあるのに替えるから。そっちで寝て。俺はこのホームゴタツで寝るから」
何と、野口は恵理と話していくうちにすっかり煩悩が消えて何処かへ行ってしまった。
この先、恵理の持つこの素直さ・清らかさにいろんな男たちが通り過ぎていくことになる。
野口は(大丈夫だよ、僕は未成年の女性を襲ったりしないから安心してね)と言いかけようかと思ったが、そんなことは冗談でも言えないぐらい恵理が幼く感じたから言わなかった。
ただし、恵理からもし誘ってきたら、据え膳食わぬは男の恥だ。その時は成り行き任せだとも思っていた。
「着替えるから野口さん向こう向いててね」
やはり幼い。野口は自分の願望が遠ざかっていくのが見えるようだった。
ところで、このシチュエーションだ。恵理は初恋の人が同じ部屋にいる。
実は恵理は(野口さんを温めてあげたい。泊めてもらえるお礼に。
どうせ、さっきお父さんに襲われてロストバージンになったばかりだ。
それなら野口さんを誘惑すればいいじゃん。
初恋の人である野口に抱かれれば、父親に無理矢理犯されたことを少しは忘れられるのではないか。野口さんを独身の寂しさから温めてあげようか? でも、女の自分からは言えないな)と、大人だか子供だかわからない、微妙な気持ちでいた。
「それじゃあ、おやすみ」野口はいい人であり続けることにした。
(恵理からのアプローチはやはり自分の思い込みだな。俺から誘ったらいい人じゃなくなってしまう。まだ中学を卒業したばかりの純粋無垢な子じゃないか。俺の考え過ぎだな)と納得し、灯りを消した。
「おやすみなさい」恵理には、本来ならあまりにもショッキングな日。
それこそ睡眠薬でも飲まなければならないような精神状態であったが、野口によって救われたのだ。信頼してやまない野口の部屋で安心してすやすや眠れた。