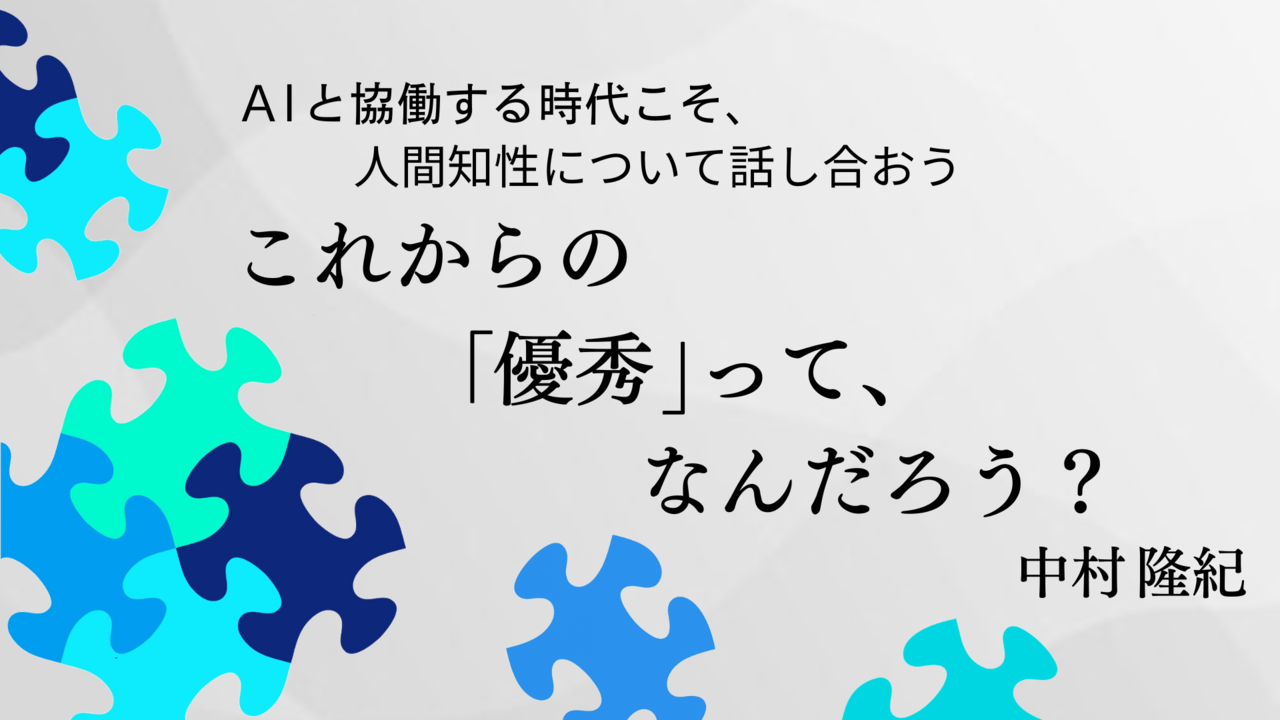【前回記事を読む】時代に求められる、「うつろえる」力とは…「なにが好きで、なに屋になりたいのか」分からないことにメリットがある。
第三章 さようなら、ホモ・エコノミクス
清野は、これからのひとたちが希望をもって仕事に打ち込んだり、思いもしない職業を発明したりするエネルギーに、少しでも着火しようとしているんだ。そのためには、停滞と仲良くするなって。あのオッチャンの言っている「逃げろ」は、「攻めろ」なんだよ。
アッちゃんが、ひとり残った。
モニターや大テーブルのスペースは電気が消され、カウンターまわりだけが、おだやかな光に包まれていた。タエさんが、アイス・アールグレイをデキャンタで置いてくれた。
普段より少し落とした声で、アッちゃんはネイビーに、ひとり語りをはじめる。
――あたしは、いわゆるリケジョなんだ。理工学部応用化学科。でも就活は総合職で応募して、欧州系総合メーカーの日本支社に決まった。4年目に、運よくビジネススクールへ行けることになって。修了後は、間をおかず、スイス本社へ転属になった。
そこで繰り広げられていたのは、アフリカ大陸の希少資源を狙う、熾烈な利権競争だった。富と覇権を奪い合う酋長になることを、あたしにも要求されているのかと思い悩み、すこし心を傷めて退社した。
――日本に帰国後は、科学未来センターのイベント企画を手伝うようになった。
ある時、金沢で催されたコロンビア大学のDeath Lab(都市と死について考える研究チーム)の展示を観に行った。クリエイティブ・ショウケースの中に、印象深いものがあった。
ニューヨークに、マンハッタン・ブリッジというランドマークがあるでしょ。その橋の下に、無数のお棺が安置されている。お棺に内蔵されたバイオマスのテクノロジーで、人間が土に還る最後のエネルギーをいただいて、橋のあかりを灯す、というアイデアだった。
……科学技術の行き先は、もっと文学的なファンタジーじゃないのかな。あたしは自分の学んできたことに、すこしだけ希望を取り戻した。
――イベントの手伝いをするうちに、子ども向けの科学マガジンから、編集の仕事をいただけるようになった。
ある日、地方の大学に所属する研究所を取材した。そこでは毎夏、地域の子どもたちを招いて科学の実験イベントを開催していた。研究所を率いるのは、フンボルト賞を受賞するような立派な研究者さん。リモートのインタビューで、その先生が話してくれた。
「子どもたちに会うのが、毎年毎年、ほんとうに楽しみだったんですよ」
当時はコロナ禍で、ほとんどのイベントが中止を余儀なくされていた。
「子どもってね、我々でもアッ! と思うような質問をしてくる。研究者同士で話をするより、よっぽど面白いんだ。早く子どもたちに会いたいです」
――あたしたちは、いつ、どうして、すごい科学者がアッと驚くようなイマジネーションを失ってしまうのだろう。あたしの関心は、次第に科学から、子どもの無心な感性へと移っていった。
「よく、キラキラのビジネススターが『やりたいことをやれ!』っていうけれど、あたしはなにをしたいのか? ブラブラ働きながら、ずっと考えていた。あるとき、わかった……これから旦那をみつけられるか、できるかどうかはわからないけど」
アッちゃんは最上さんの名刺をカウンターの上でくるくる極細に丸めながら、顔を上げる。「あたしは、いいお母さんになってみたい……それじゃ、ゆるいのかな」
ネイビーは、グラスを拭きながら、眼尻の笑い皺をいっそう深くしてつぶやいた。
「……アッちゃんも、ヒューマンなんだよ」