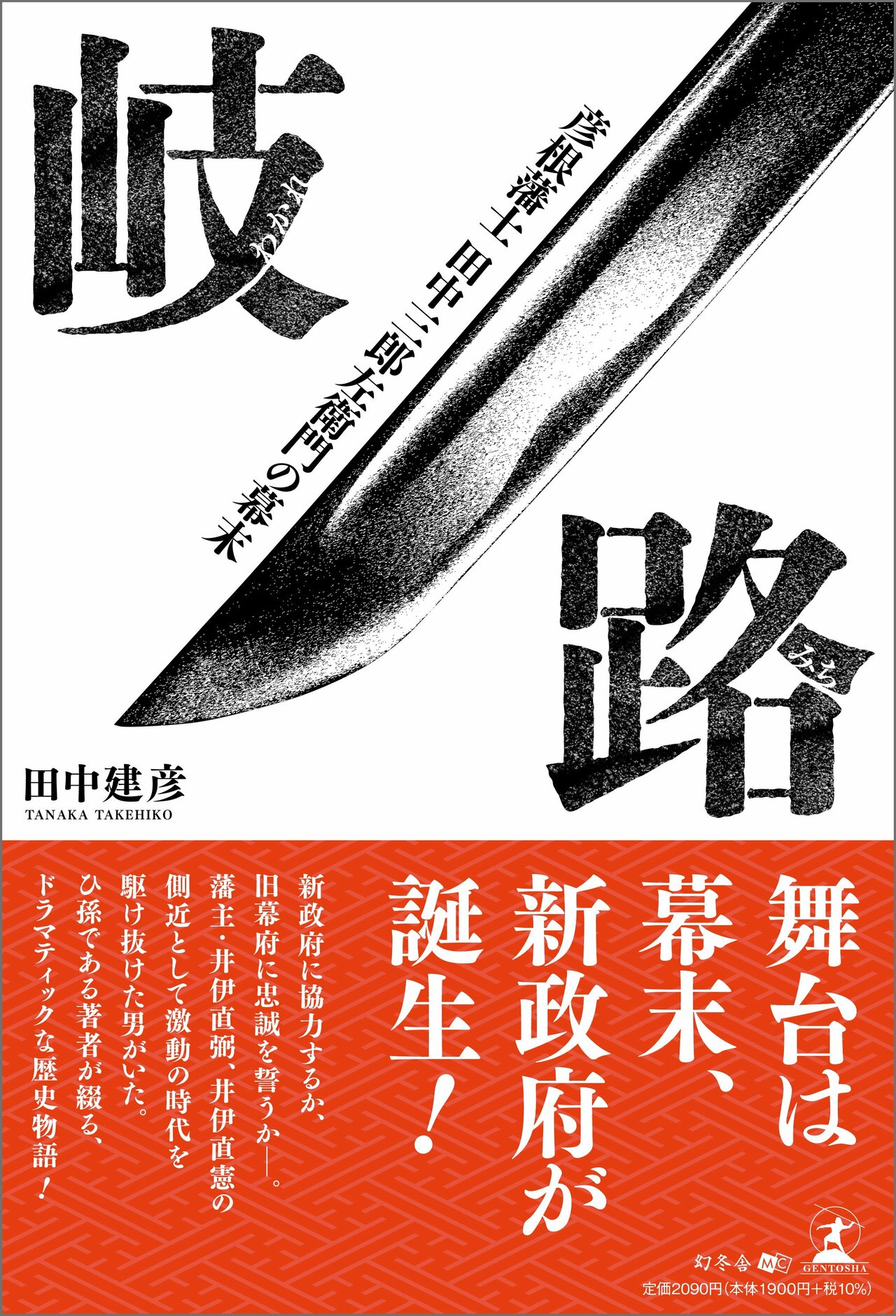「誰だろう。名を言ったか」
「はい、熊吉とか申しておりました」
「あの野郎、また出てきやがった」
給仕をしていた芳蔵が、驚いて大声を上げた。徳三郎は、父に旅の途中であった熊吉との出会いの一部始終を話した。父はその奇妙な出会いの話を聞きながら、途中何度も笑い声を上げていたが、徳三郎の話が終わると言った。
「なるほど変わったやつだな。熊吉とやらの顔が見てみたい。私が会ってみよう」と言い、門番に「そやつを御用部屋の庭先に連れてまいれ。万が一のことがあってはいけない、私が行くまで側についておれ」
上屋敷での宿直の仕事を終えて、翌日の午後徳三郎が中屋敷に戻ってくると「おかえりなさいまし」と、満面の笑みを浮かべた熊吉が出迎えた。傍には芳蔵が苦虫をかみつぶしたような顔をして立っている。
「お父上様が、若様の小者として使ってやれとの仰せで……」
芳蔵は大いに不満そうだった。
熊吉は徳三郎に「迷惑」と言われて、ようやくあきらめたが、もう昔の稼業に戻るまいと決心して、人足をしながら食いつないできた。ある日、薩摩藩から桜の苗木を数十本江戸城に献上するということで、その運搬の仕事に駆り出された。
その時、登城する井伊家の殿様の行列に行きあたって、徳三郎を見かけたという。その場で声をかけることもできずに、そのまま帰ったが、どうしてももう一度徳三郎に会いたいという気持ちを抑えきれずに来てしまった、というのだった。