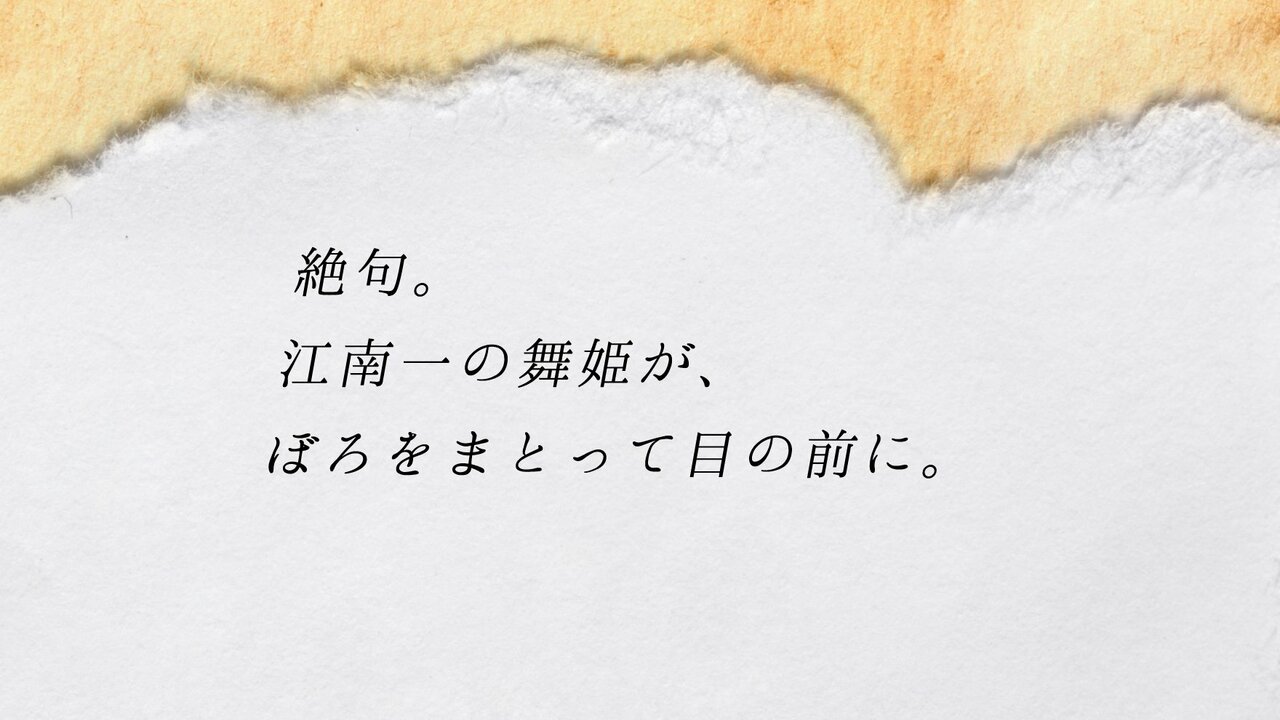壱─嘉靖十年、漁覇翁(イーバーウェン)のもとに投じ、初めて曹洛瑩(ツァオルオイン)にまみえるの事
(6)
言葉につまった。まさか人身売買を手がけているかも、などとは言えない。
「すみません……なにも、存じて、おりません」
「なんだ、何も知らぬのか」
「はい……漁覇翁(イーバーウェン)は、何も語られないというか、私ごとき下っぱの前には、姿をみせることさえありませんの で。なにかご存じならば、教えてくださいませんか?」
「はっはは……質問したのは、こっちなのだがな」
田閔(ティエンミン)が、口をはさんだ。
「師父が材木の手配をしていると、どうやって知ったのでしょうね?」
「まあ、抜け目ない商人は、いろいろと網をもっているものだ」
李(リー)師父も、十年で、司礼監の頂点ちかくまでのぼりつめた人である。漁覇翁(イーバーウェン)に、自分と同じにおいをかぎつけているのかもしれない。
「よかろう。当代随一の商家と会って話をしてみるのも、一興であろう。叙達(シュター)、帰って主人に伝えよ。李清綢(リーシンチョウ)が、おまねきを受けると」
「李(リー)師父、ぜひ、教えていただきたいことがございます」
「なんだ」
「私、非才ではありますが、いずれはぜひ正規の宦官となり、皇帝陛下、ひいては明朝のために、はたらきとうございます……正戸(チャンフー)となるためには、いかほどの銀子が要るものでありましょうか」
師父は、私の顔をじいっとのぞき込んで、しばらく沈黙した。ようやく発されたのが「往け」の一言―。
「……はい」
引き下がるよりほかに、道はない。一礼して、二、三歩あとずさり、再び一礼して、退出しようとした。そのときである。
「叙達(シュター)!」
田閔(ティエンミン)の声であった。指を五本、立てている。銀五十両という意味だ。私は両ひざをついて、深々と頭を下げた。