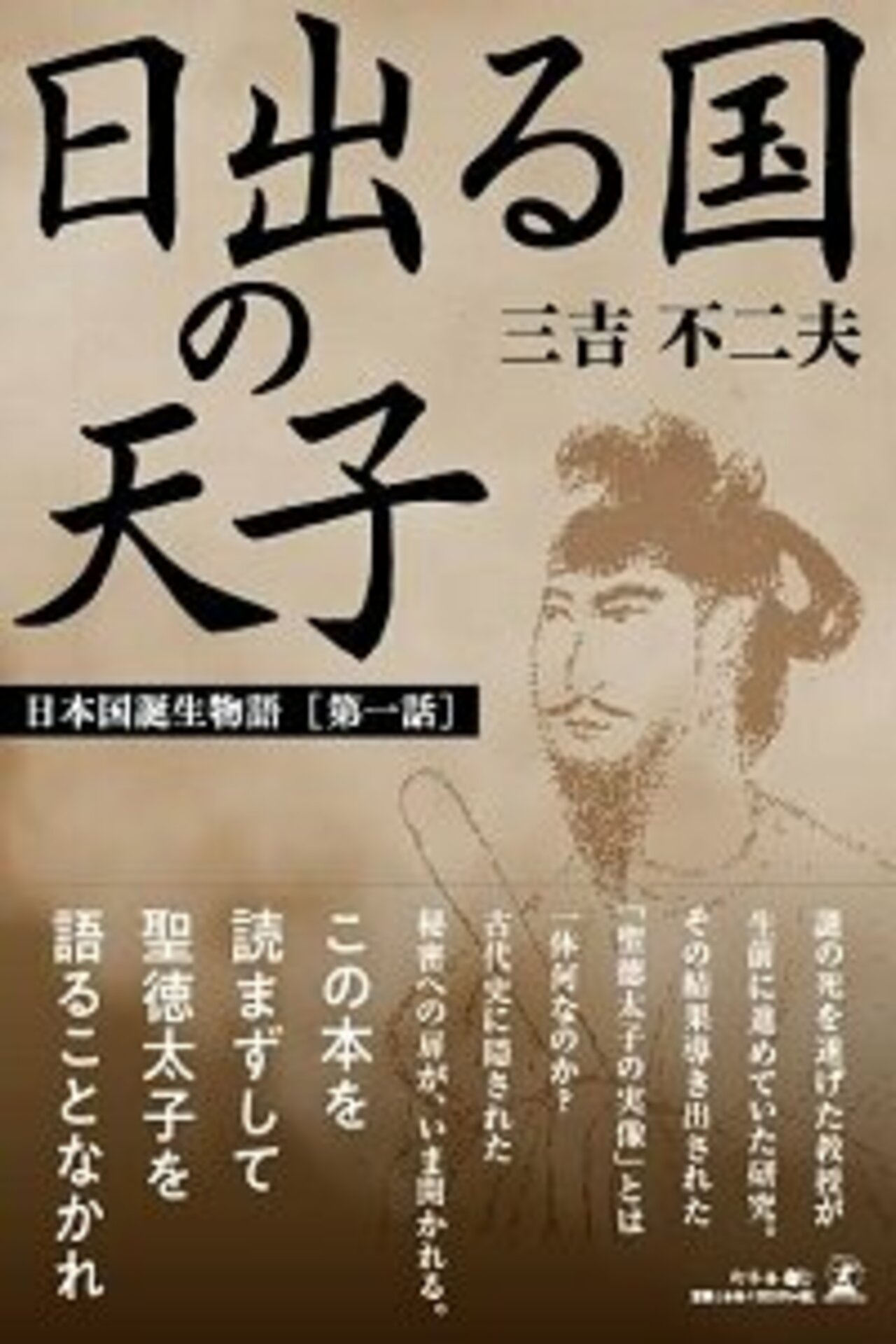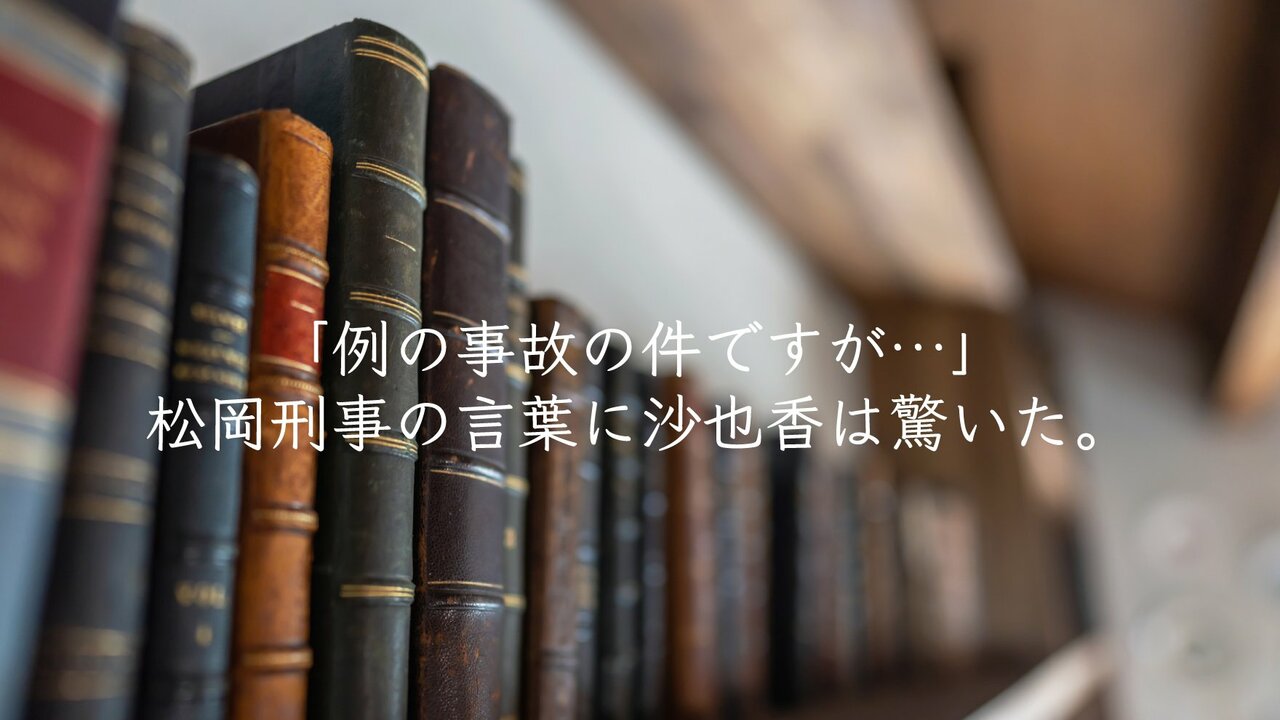第一章 ある教授の死
1
高槻義則(たかつきよしのり)は、少しばかり昂(たか)ぶっている心を抑え、首都高速道路を慎重に走っていた。さいわい心配したほどの渋滞はなく、この調子だと予定時刻より早く目的地につけるかもしれない。
しかし焦りは禁物だ。なにしろ一世一代の勝負に出たのだから。
彼はシートに座り直し、さらに慎重にハンドルを握った。するとそのときだった。
突然、がくんと車のスピードが落ちた。一瞬なにが起きたのかわからなかった。
特別な操作はなにもしていない。だが急ブレーキを踏んだように車は速度を落としはじめている。
彼はあわててアクセルを踏んだ。しかし車は速度を上げるどころか、逆に減速し、プスンプスンと異常音をあげはじめた。
反射的にダッシュボードを見ると、スピードメーターの針は四十キロから三十キロの間をふらついている。そしてスピードメーターの横にある温度計の針が異常な数値をさしていて、赤の警告ラインを大きくオーバーしていた。
「ええっ、うそだろう! オーバーヒートだって?」
高槻は思わず大声を上げた。こんなトラブルを起こしたことが信じられなかった。なにしろ、一週間前に点検に出したばかりなのだ。
「くそ! 点検修理代金を返してもらうからな」
憎まれ口を叩きながらハンドルを切って、車を左側いっぱいに寄せる。左の遮音壁のそばまで車を近づけたとき、プスン……という音を立ててエンジンが止まった。
彼は大きくため息をつき、駐車ブレーキを踏んだ。足元にあるボンネットを開くレバーを引き、後続車に気をつけて道路に降りた。
ボンネットを開けようとして手をかけた瞬間、熱気が噴き上げてきて、あわてて手を引っこめた。少し火傷したかもしれない。ボンネットを触った指先を見ると、油で少し汚れていたが、大きな火傷には至らなかったようだ。
「なんてことだ! どうしてこんな大事なときに……」
思わず口をついてグチがこぼれる。しかし起きてしまったものはしかたがない。
「とにかく、JAFに連絡しなきゃ」とひとりごとをいいながら、また運転席に乗り込んだ。開いたまま助手席に置いていた覚え書きのノートをカバンにしまい込み、ダッシュボードに入っているはずのJAFへの連絡用カードを探す。カードを見つけると、携帯を取り出して電話した。
「すみません。高槻と申しますが、首都高でエンストしてしまったんですが」
状況を話すと、現在位置をくわしく聞かれた。羽田方面に分岐するジャンクションを抜けてすぐの急カーブだというと、そこは交通量が多くて危険なところですよ、といわれた。危険なところだといわれても、そこで動かなくなってしまったのだからしかたがない。