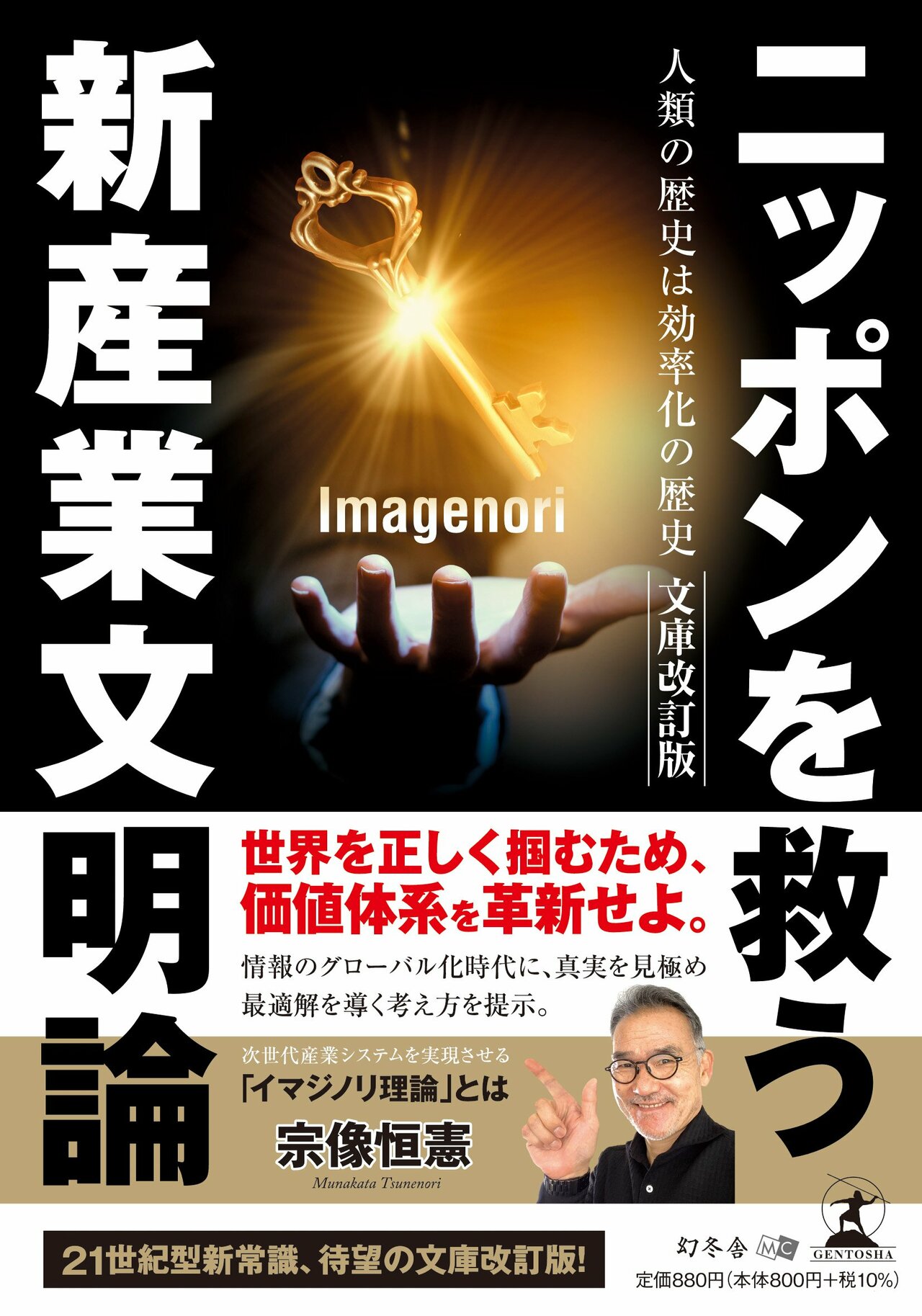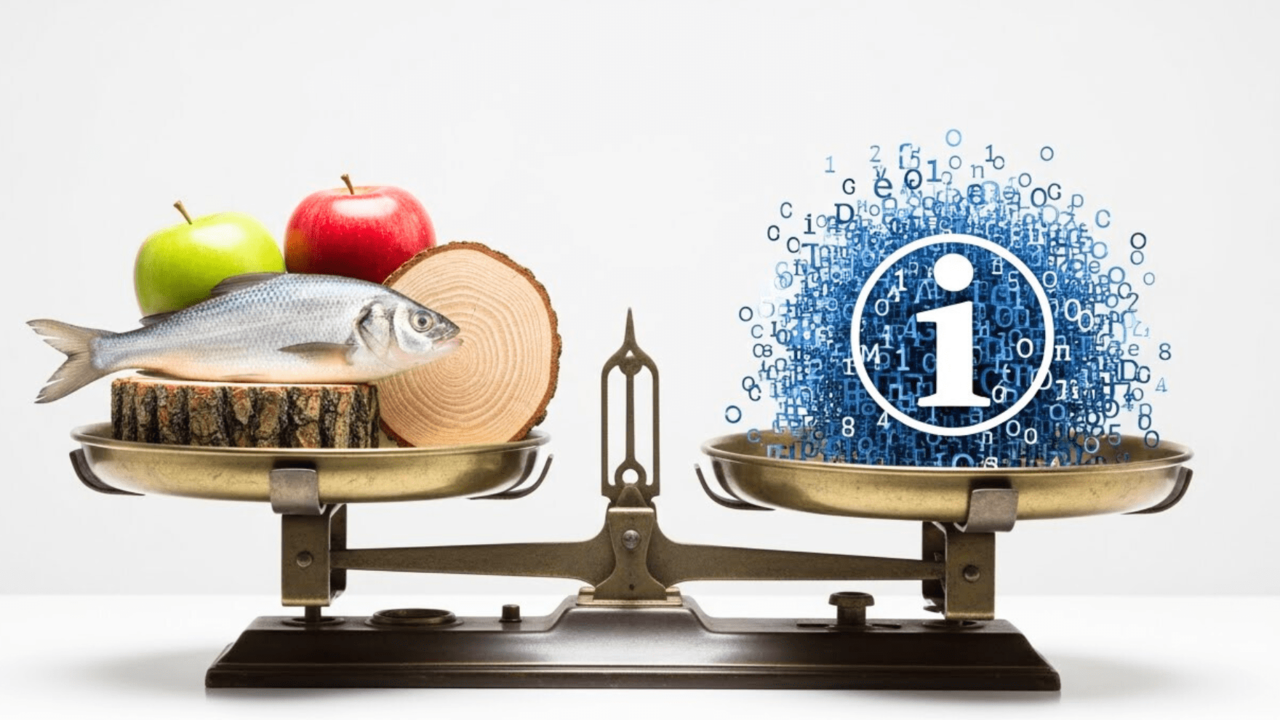(3) 1931年 ─ ワルター・ホフマンの産業分類
ワルター・ホフマンは、1931年『工業化の段階と類型』という著作の中で「工業化」とは迂回生産が進むことであると主張しました。迂回生産とは、最終目的の消費財である製品を作るには、そのための製造設備などの資本財が必要です。そこで彼は工業化の度合いを測るために消費財の増減を直接見るのではなく、費やす資本財との比率でもってその工業化の度合いが判断できると考えました。
彼によると工業化の進展は年々生産する製造業製品の用途に変化を生み、消費財に対する投資財の比率が高まっていくはずであるとして経済発展は消費財を生産する段階から製造設備などの投資財を作りこれを利用し生産性を高める段階への変化として捉えたのです。
したがって、産業を消費財産業と投資財産業とに2分類し、「消費財産業の付加価値額」÷「投資財産業の付加価値額」=ホフマン比率として見ることで経済発展の段階がわかると考えました。
ホフマン比率は、工業化の進展につれ消費財産業から投資財産業へ比重が移ることにより段階が低下していくものと考えます。第1段階では5・0、第2段階では2・5、第3段階では1・0、第4段階はそれ未満となります。
しかし彼の法則は産業連関(れんかん)分析(産業ごとの生産・販売などの取引額を行列形式にした指標分析)が発達した今日から見れば2つの産業区分に厳密性を欠いており、耐久消費財の比重が高まった今日においては妥当性に難点があるとされています。
そこで、次に登場するのが日本人にとって最も馴染みのある産業構造理論であるぺティーとクラークの産業分類です。
(4)1941年 ─ ぺティーとクラークの産業分類
英国の経済学者であるコーリン・クラークは、1940年『経済的進歩の諸条件』において産業を第1次産業、第2次産業、第3次産業の3つに分類しました。
彼は世界各国の長期にわたる経済資料を分析した結果、それぞれの産業の就業者数は経済進歩の進まない段階では、第1次産業が圧倒的に高い比率を占めるが、経済の進歩とともに第2次産業の就業者比率も高くなり、やがて第2次産業と第3次産業の就業者比率が第1次産業を上回り、第1次産業の就業者の比率が低下する。
さらに経済が進歩すると、第2次産業よりもむしろ第3次産業の就業者比率が高くなり就業者では最大の部門となっていくとしています。
彼は『経済的進歩の諸条件』の中で、農業、製造業、商業という順に収益が高まるという17世紀後半の英国の経済学者ウィリアム・ペティの法則を採用しました。そのため、両者にちなんで、この分類は「ぺティー・クラークの産業分類」と呼ばれています。
・第1次産業:農業・林業・漁業
・第2次産業:鉱業・建設業・製造業
・第3次産業:電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業、金融業、運輸業、小売業・サービス業など非物質的な生産業
👉『ニッポンを救う新産業文明論 人類の歴史は効率化の歴史 文庫改訂版』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】「私、初めてです。こんなに気持ちがいいって…」――彼の顔を見るのが恥ずかしい。顔が赤くなっているのが自分でも分かった
【注目記事】「奥さん、この二年あまりで三千万円近くになりますよ。こんなになるまで気がつかなかったんですか?」と警官に呆れられたが…