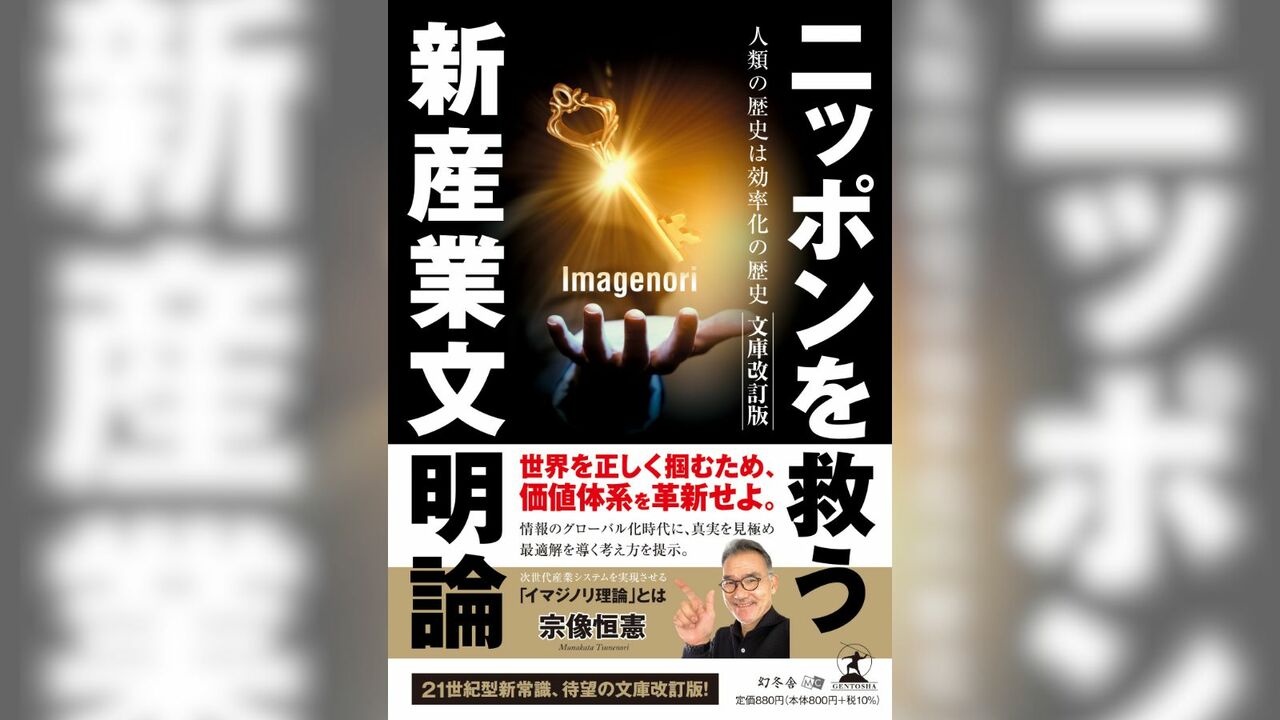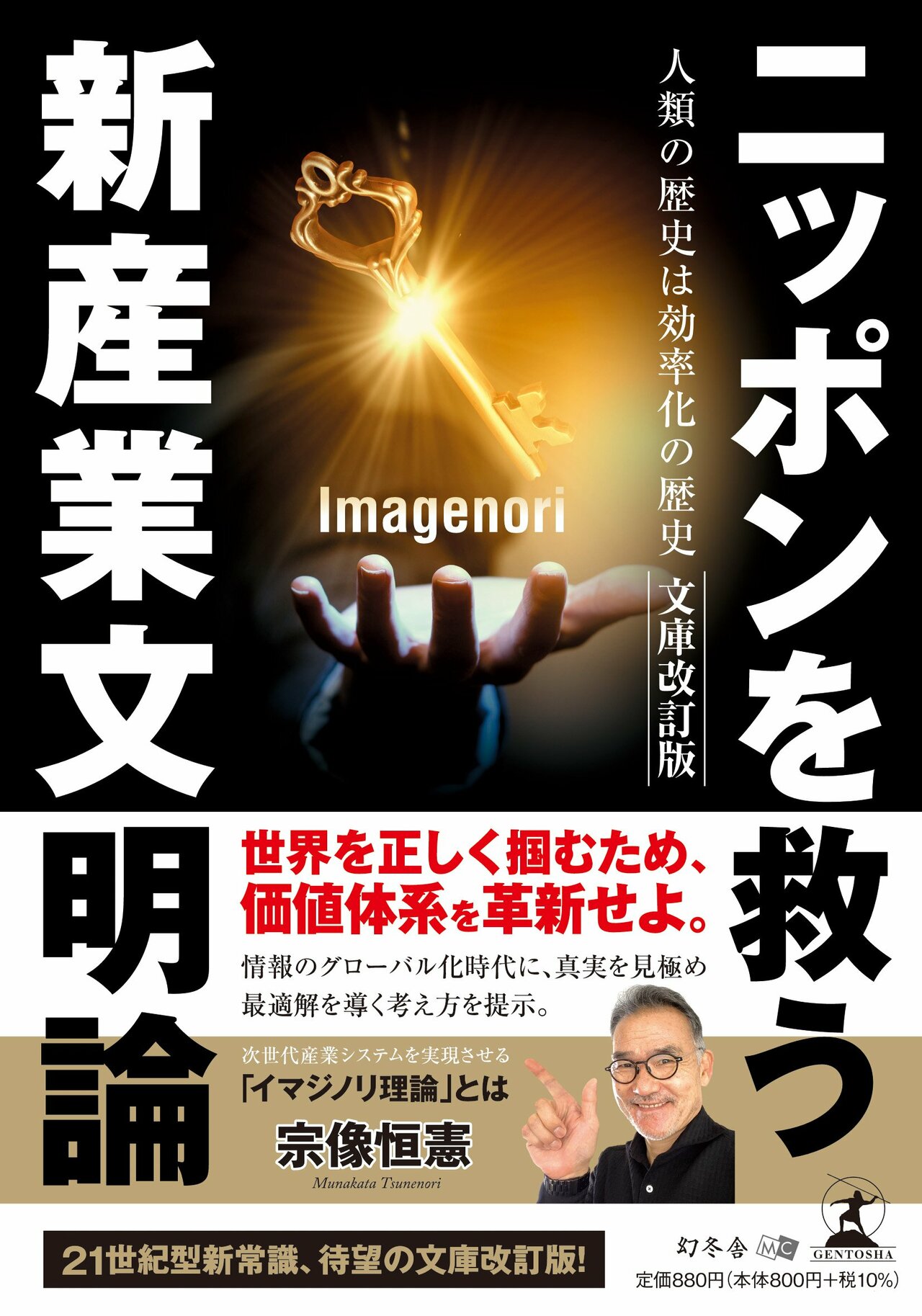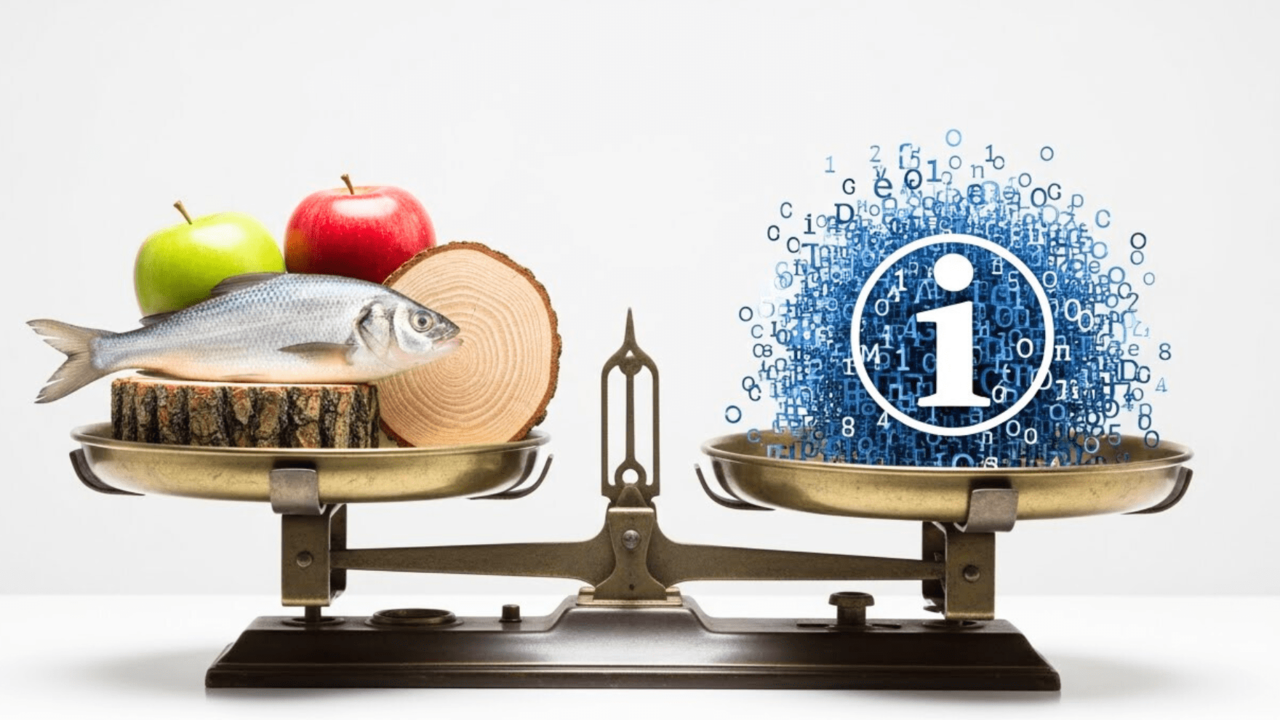【前回記事を読む】「グローバル化」という名の「植民地政策」。インターネットで情報が平等化し、一見、国家間の支配関係は影を潜めているが…
はじめに
それゆえ、これまでのような絶対的法則に従った社会現象の定点観測を無機質に繰り返す伝統的理論では、今日の実体経済の的確な解明と将来に向けた動向予測に既に困難をきたしているように思われます。
昨今、情報化社会といわれて久しいですが、量子理論を伴ってこれまで予想だにしなかった、情報を観測する「ヒト」(巻末『語句とその定義』を参照)の心や意識、「ヒト」の理念や恣意といったものが情報の重要な副生因子(副次的に生産される要因)として「ヒト」と遭遇するたびに組み込まれ情報が変化していることに一部の人たちが気付き始めたようなのです。
今日の経済と経営を巡る状況は、いまだに2008年に起きたリーマンショックで経験したヒトの心や意識、理念や恣意といったもので集約されているかのようにも思われます。
米国の不動産バブル期(2001~2006年)に、信用力の高い一般的なプライムローンとは別に、さらなる企業利益追求のために信用力の低い低所得者向け住宅ローンである回収リスクの高いサブプライムローンをわざわざ強化していきました。
それは極端な格差社会の米国で大半を占める低所得者層向けに、購入する家を担保にバブル期のお祭りムードの中、積極的にさらなる値上がりを期待させるといったローンだったのです。
ローンを組ませた融資元の住宅金融会社は、そのリスキーなローンを高金利の債権として投資銀行に売却します。買い取った投資銀行側は、債権回収のリスク回避のために大量の債権をグローバルに展開する自社他社のさまざまな金融商品と複雑に紐付けし仕組債権化を果たしました。
併せて見え隠れする彼らの恣意の下、格付け企業に高い評価を付けさせることで証券市場ではさらなる証券価値の高騰を実現させていったのです。
しかしながら結局は、米国中央銀行(FRB)の金利引き上げをきっかけに不動産バブルの終焉を迎え、極端な不動産価値の下落と証券の下落に伴い大量の債権が不良化し世界的に金融危機を招きます。
結果的に多くの債権を抱える世界の金融機関や投資銀行の経営が悪化することになり最も多くの不良債権を抱えていた米国第四位の投資銀行であるリーマンブラザーズが、不幸にも共和党ブッシュ政権の支援も全くないまま破綻していったのです。
そのリーマンショックの背景から明らかなように、従来型の伝統的世界観の体系に基づく限りその本質は見えてこないでしょう。