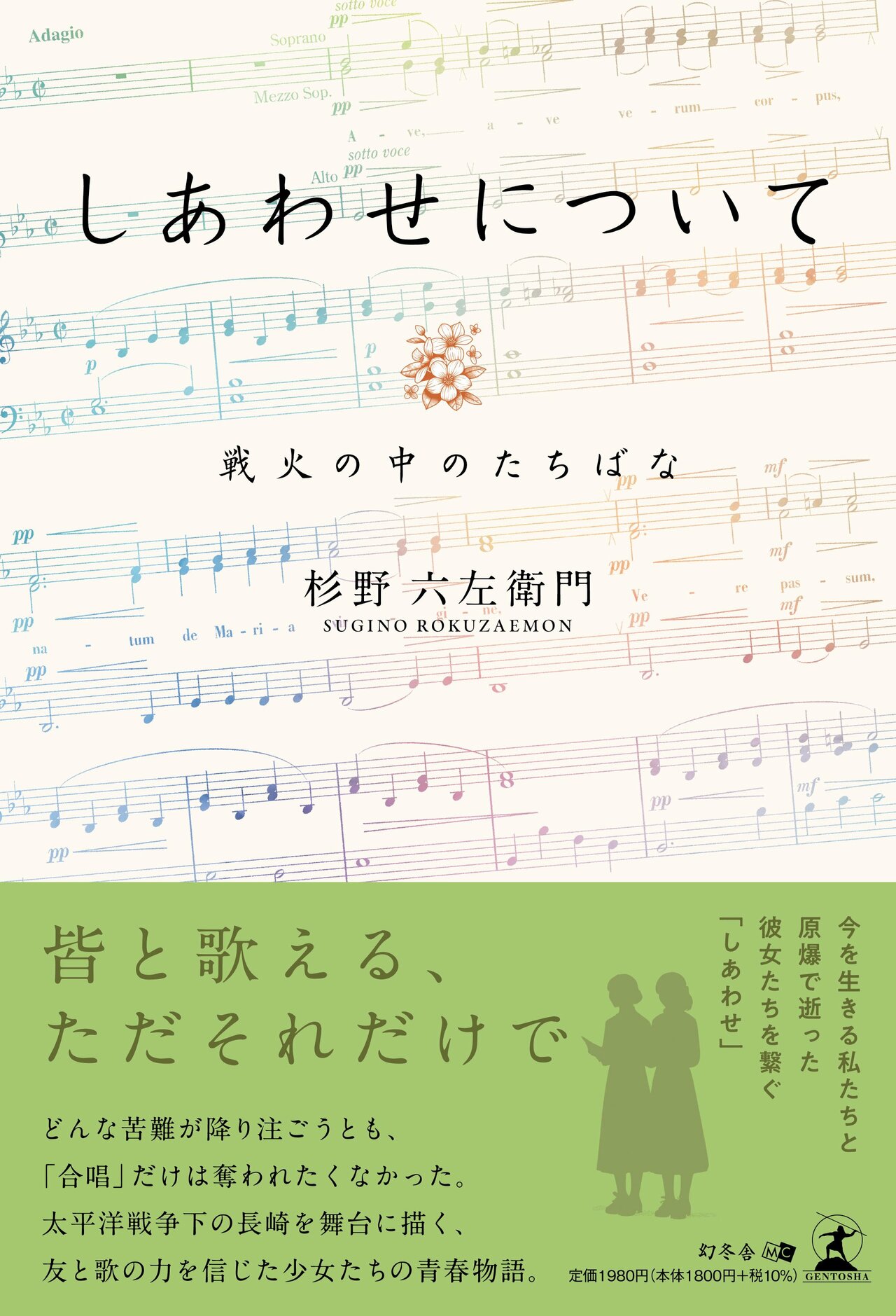「この楽器は何故こんなに乱雑なんだね」
それは常識的に置かれているだけに見えたが、彼には乱雑に見えるらしい。
「本科の生徒が、授業のあとに丁寧に仕舞わなかったのだと思います」
とスギさんが答えた。
「ここは君たちも使うのだろう、気づいた人が整理すべきじゃないか。君たち、やりなさい」
スギさんは、どうせすぐに使うのに、と思ったが、朋たちに手伝わせて楽器を並べなおした。やがて綺麗な直線状を見届けた日生は、満足そうに出て行った。
村山六郎(ろくろう)はより厄介だった。彼は風紀の主任を兼ねていたから生徒の違反を見つけ出し、怒鳴りつけ、矯正することを自分の使命にしていた。それは校則であれ、大日本帝国臣民の心がけであれ、自分の中の規則に反するものは違反として叱りつけるのだった。
「その紺色の靴下はなんだ。靴下は黒か白に決められているではないか」
「安殿奉(ほうあんでん)(天皇の御真影(ごしんえい)を安置した建物)に尻を向けるとはなにごとだ! この無礼者。家でどんな躾(しつけ)をうけてきた」
「教師に歩きながら敬礼する奴があるか! 登校時は停まって敬礼する、と生徒手帳に書いてあるはずだ」
彼の頭の中には校則も生徒手帳も一字一句違(たが)わずに入っている。村山はこの学校に来てから十五年になる五十歳を目前にした男だったが、依然として平教員のままで、ようやく風紀の主任になれたところだった。
だから、多くの風紀違反を弾劾することで有能な風紀主任の姿を見せ、少しでも有利な地位を得ようと、いつも怒鳴る材料を探しているのだった。
彼のこうした思いを生徒は熟知していたから、誰もが彼を避けていたし、こころの底から嫌って、陰では「六郎」と軽蔑を込めて呼んでいた。
学校生活の棘であるこれらの教師のありさまを生徒たちは、ひそかに分析し、批評していたが、なかでもサエさんのそれは厳しかった。
「数学の日生はね、自由な曲線が怖いのよ。自由な曲線はその先がどこに向かっていくか分からないでしょ。だから、行く先がまっすぐに決まっている直線が安心なのよ」
「六郎は職業を間違えたわね。憲兵になっていたら、いまごろ出世は思いのままだったのに。そして、もっともっと人に嫌われたのに」
彼女の寸評はほかの教師にもひろがる。
「家事の松田先生は料理上手よ。でも、先生の言うとおりに作っていたら茶色いおかずばっかりになってしまうわね」
「裁縫の柳先生に服を作らせていたら、反物 (たんもの)がいくらあっても足りないわ。贅沢は敵の時代に合った裁縫じゃないのよ」
「校長先生は偉いわよ。有能な教頭がいれば誰でも校長をやれるってことを体現しているんだから」
サエさんの寸評は生徒たちのあいだで好評だったが、寸評の常として人を褒めることはめったになかった。
【イチオシ記事】「大声を張り上げたって誰も来ない」両手を捕まれ、無理やり触らせられ…。ことが終わると、涙を流しながら夢中で手を洗い続けた