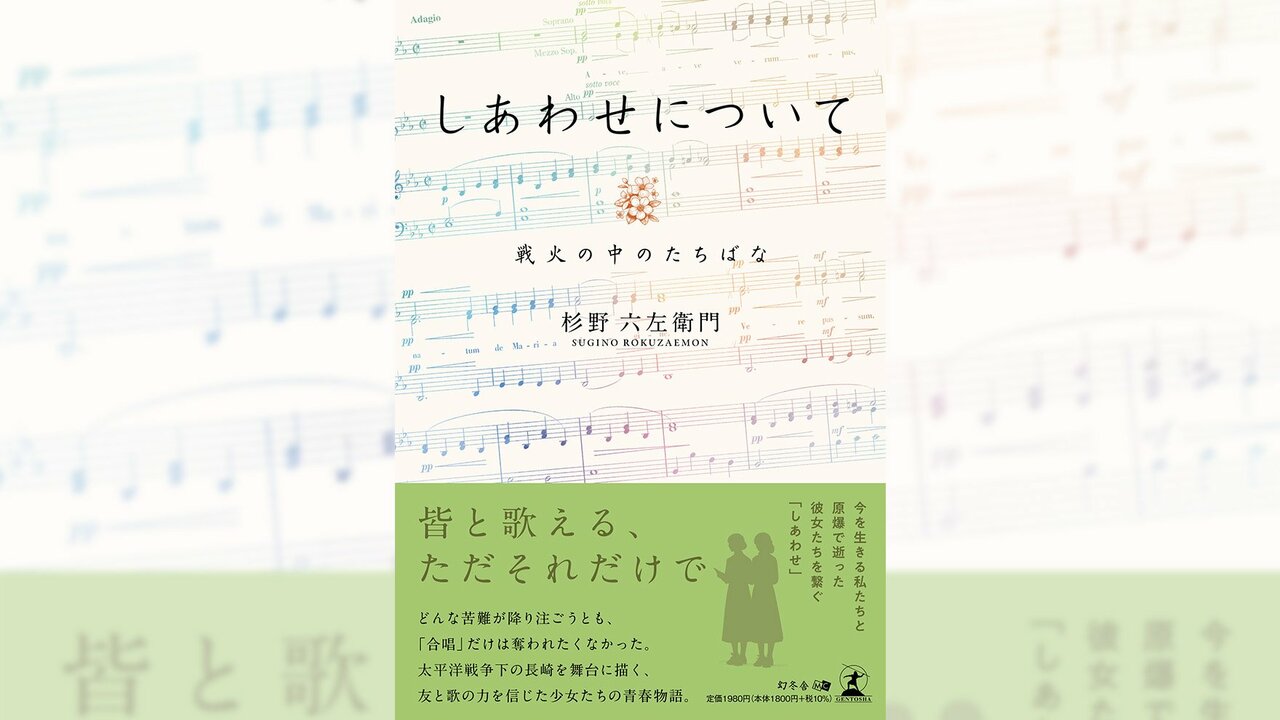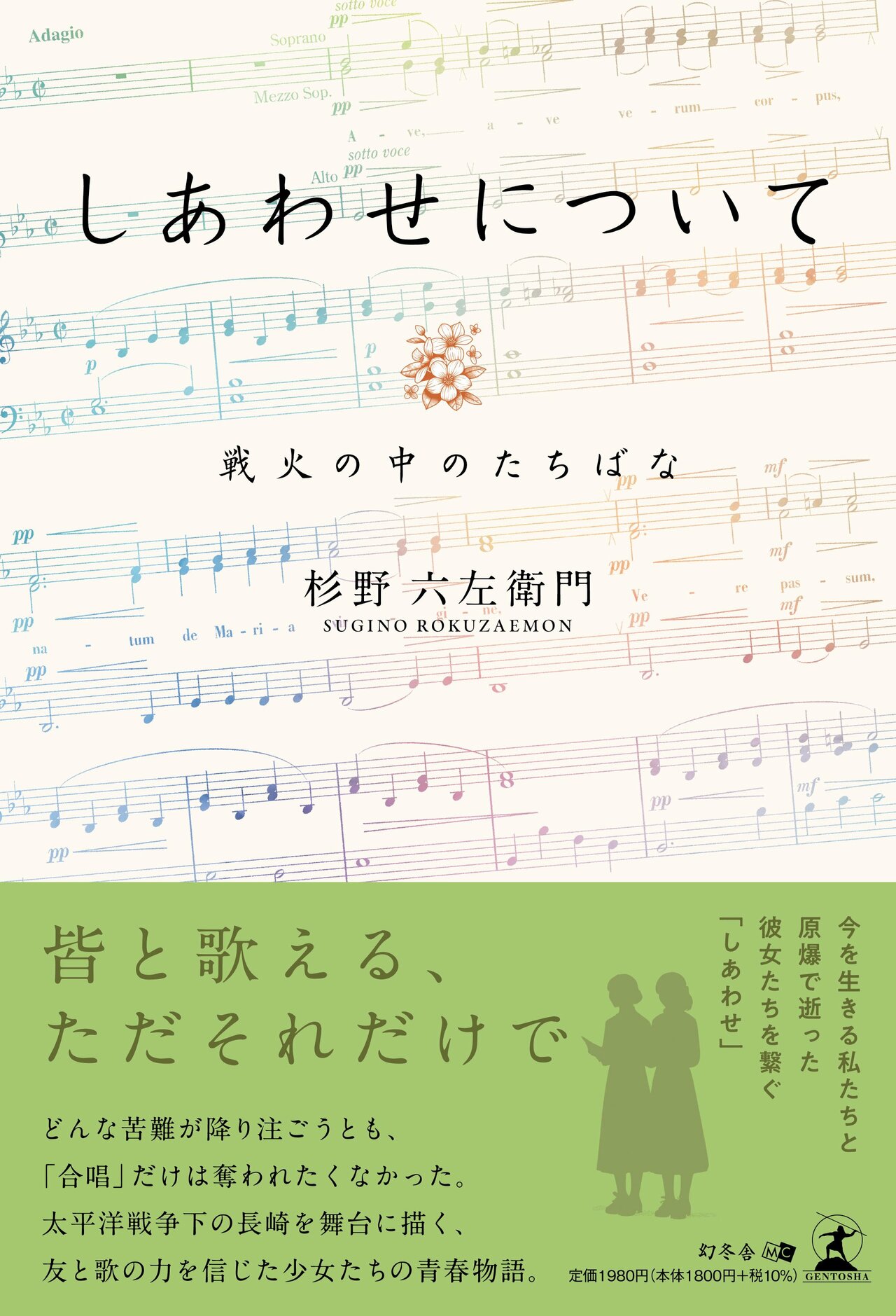【前回の記事を読む】戦時下で非国民あつかいの牧師の娘、嫌われている取り締まり警察官の娘、そして新参者の自分。“あまされ者”たちが集められ…
一年生
松田先生の信念では、料理は何よりも美味しくなければならない。そのためには、しっかりと出汁(だし)を取り、丁寧にアクを取り除いて雑味(ざつみ)をなくし、調味料を塩梅(あんばい)良く加えなければならない。醤油を目分量で回し掛けるなど、もってのほかだ。食材の香りも大切にしなければならない。
食品の香りは長く熱すると失われがちである。味噌汁は長く煮ないようにし、胡椒(こしょう)、カレー、わさびなどをなるべくあとで加えるのはこのためだ。
料理は味だけでなく、栄養が取れなければ意味がない。だから根菜の皮や葉も利用しなければならない。戦時の今はなおさらだ。料理は加熱が必要である。消化をよくし、食中毒を防ぐために。加熱しすぎてもいけない。栄養が壊れるから。
先生の考えでは、料理は科学である。整えられた手順と正確な計測、そして細心の観察。だから、先生の調理実習は生徒たちにとって、いつも真剣勝負だった。失敗したら合格点をもらえない。
そして、先生は、料理は結局のところ感性(センス)であることも知っていた。センスの良し悪しは生来のものであり、それが無い人はどんなに努力をしても報(むく)われることが少ない、と思っていた。はたして朋にはセンスが有るのだろうか?
センスが有っても無くても、専攻科になったら本科生のような子供気分ではいられないことは確かだった。
県女での苦労の種は教師だった。それはどこの学校でも同じように、際立って個性的な教師は、本来楽しくあるべき学校生活に染みのような影をおとす存在で、県女では数学の日生(ひなせ)と国語の村山(むらやま)がその筆頭だった。
日生は、直線をこよなく愛していて、全てが直角に、直線に揃っていないと気がすまなかった。彼は、いかなる曲線も歪みも見逃さない。
その、日生がスギさんを探しに音楽室に現れた。日直だったスギさんに用があったらしい。仕舞われている楽器を見た彼は眉を顰(ひそ)めた。