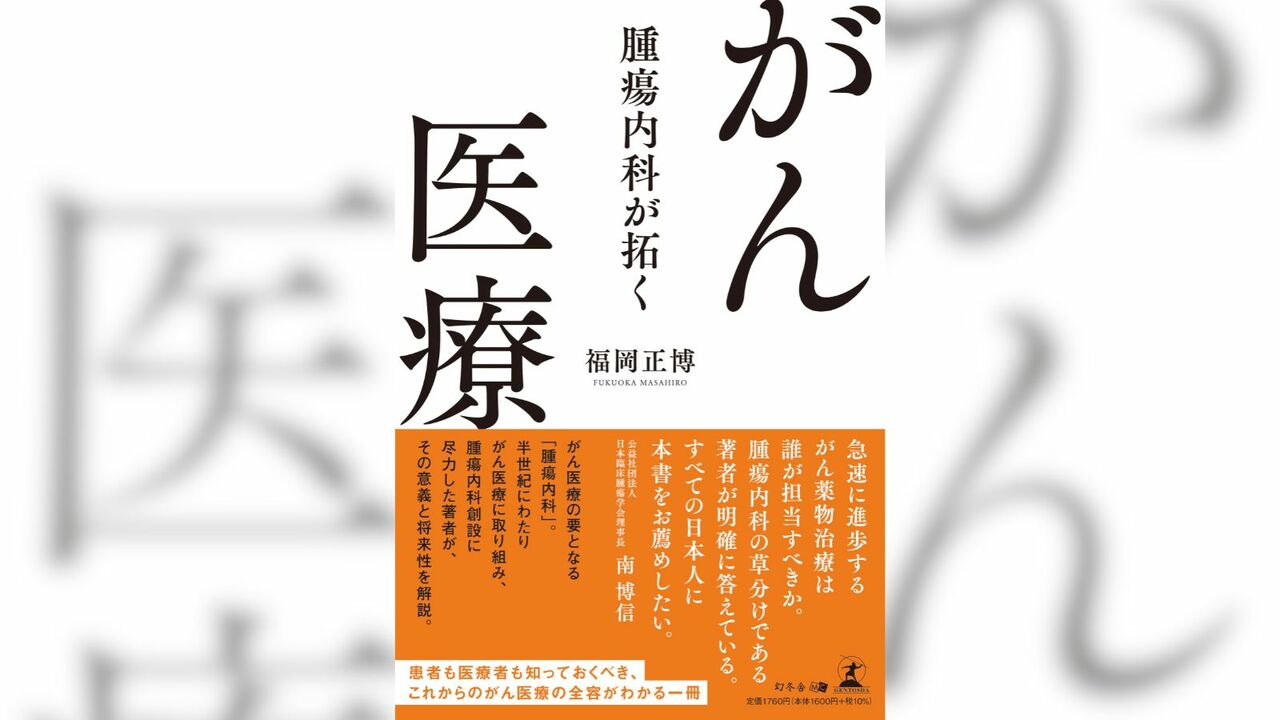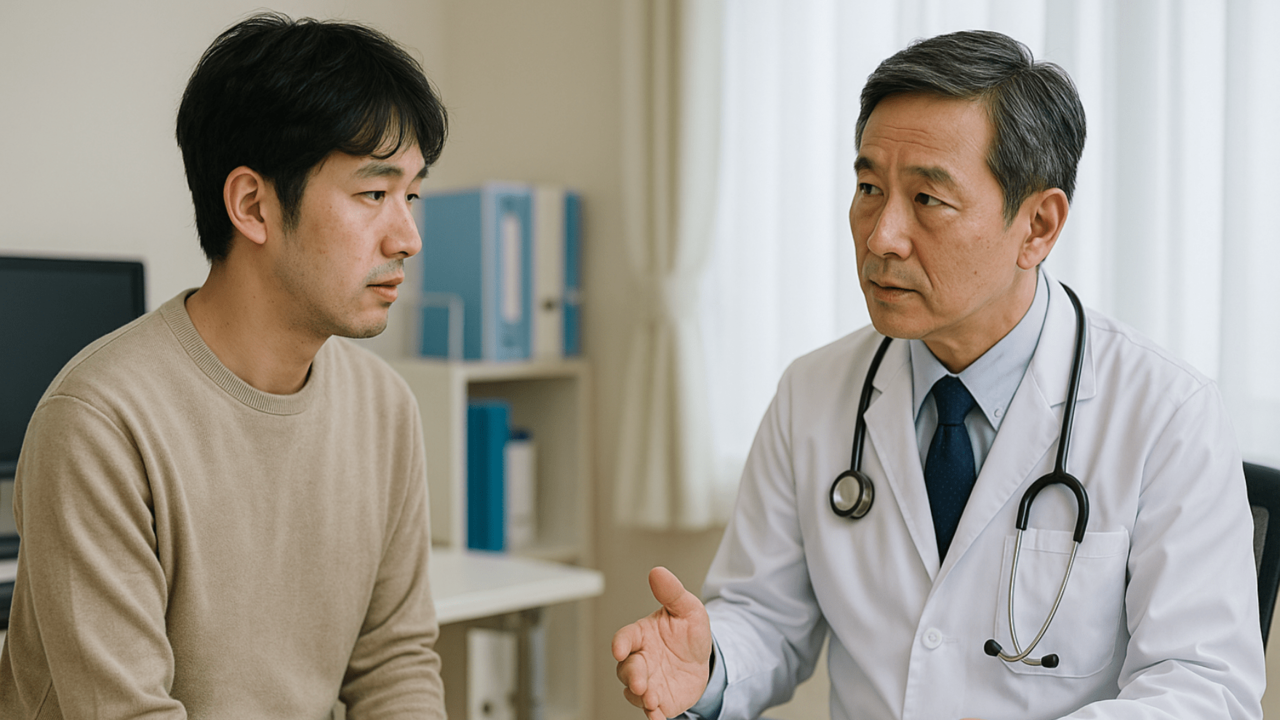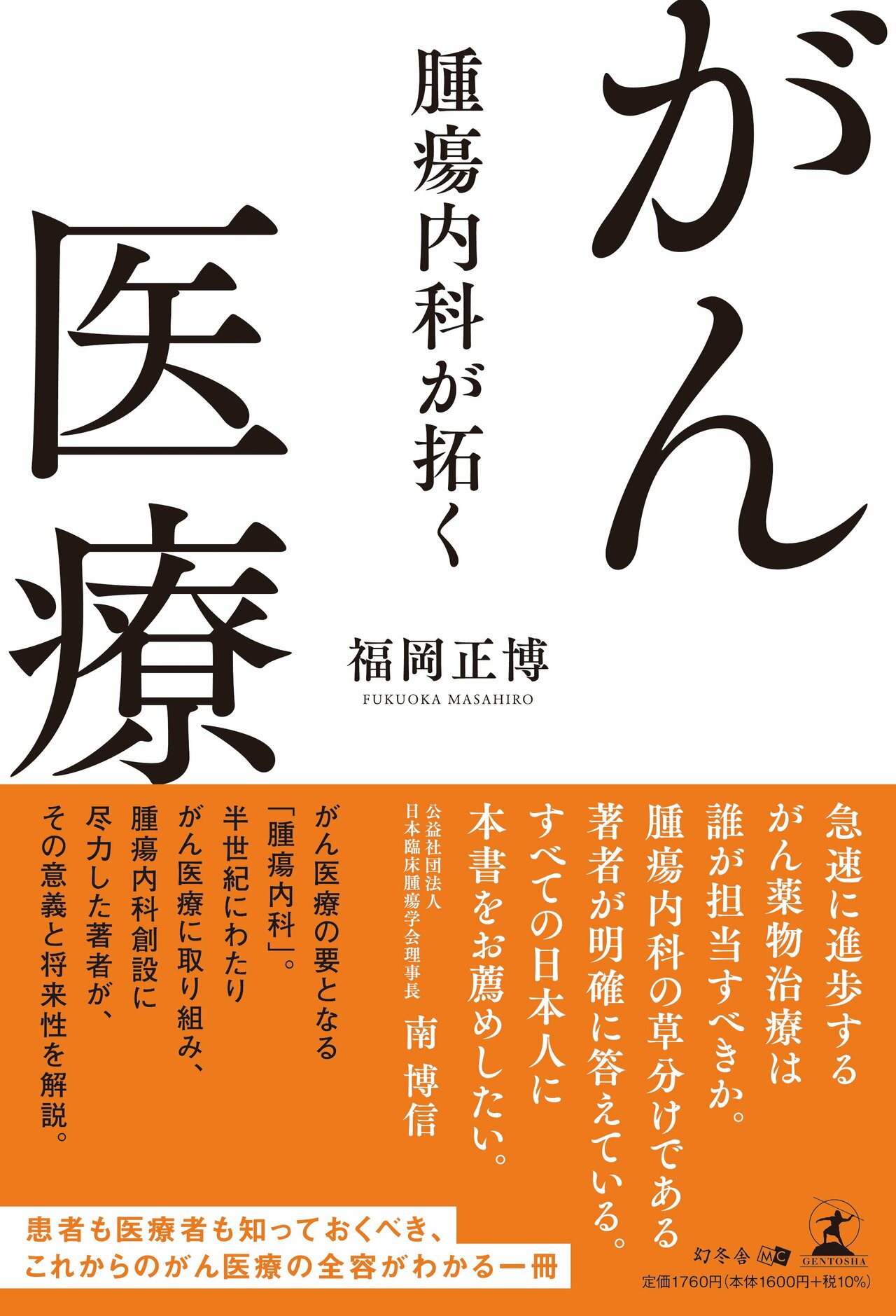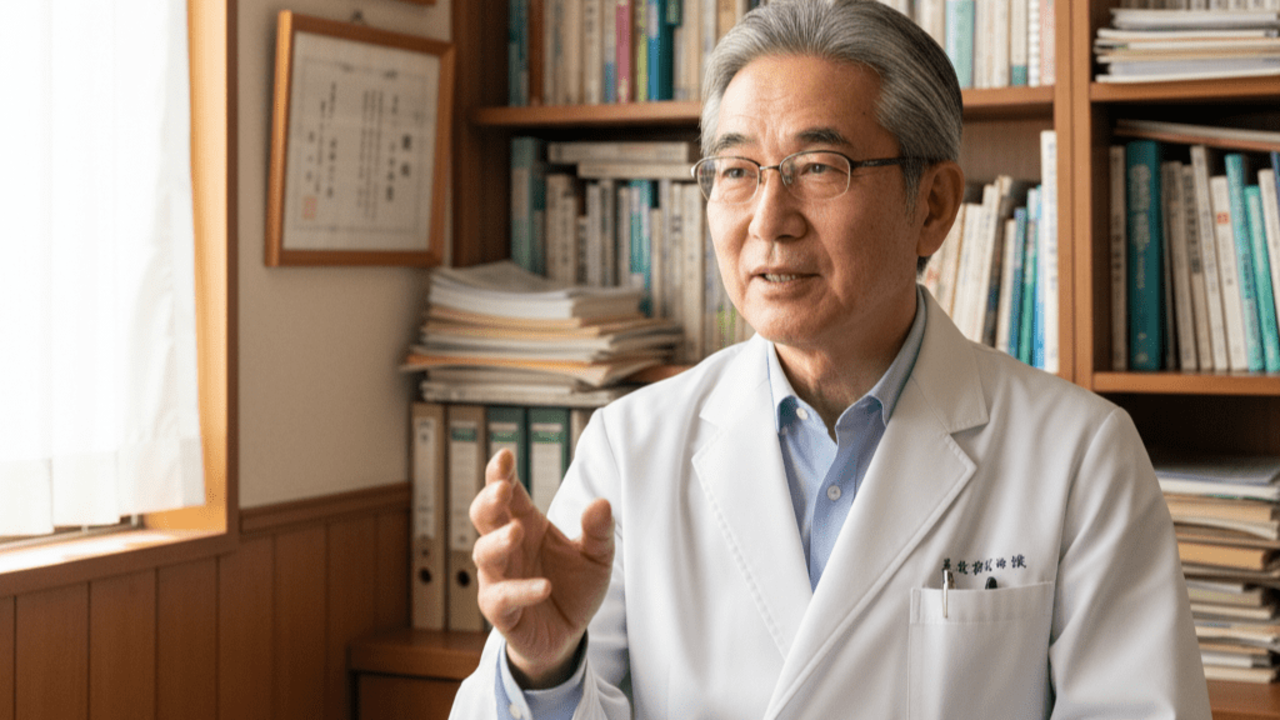【前回の記事を読む】「肺癌なら呼吸器内科」は最適ではない…これからのがん医療の要になる「腫瘍内科」をあなたは知っていますか?
第一章 がんについて
がんという病気
本書では、がん医療、中でも腫瘍内科のことを中心に述べることになる。したがって、まずは“がん”という病気がどのようなものかを説明する(参考資料一)。
がんは、わが国をはじめ先進国においては死亡原因の第一位であり、日本人の場合、生涯を通じて男性の60%、女性の40%ががんに罹り、三人に一人ががんで死亡すると言われてきた。
がんは、ほぼすべての臓器、組織に発生し、肺がんや膵臓がんは治りにくく死亡率が高いが、甲状腺がんや前立腺がんは進行速度が遅く死亡率が低い。また、同じ臓器のがんであっても、抗がん薬が効きやすい場合と効きにくい場合があるなどがんという病気は極めて複雑である。
がんは“遺伝子の病気”と言われる。人の体を構成している細胞の核と呼ばれる部分にあるDNA(デオキシリボ核酸)が遺伝子の本体であり、DNAは、アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(Ⅽ)の四つの塩基の組み合わせで成り立っている。
この塩基の配列に異常が起こることを変異と言う。発がんに関連する遺伝子には、がん細胞の増殖にアクセルとして働く“がん遺伝子”と増殖にブレーキとして働く“がん抑制遺伝子”があり、これらの遺伝子に何らかの要因で傷がついて変異が起こり、がん細胞が発生する。
しかし、通常では免疫作用が働いてがん細胞は消退する。ところが、この免疫反応をすり抜けた異常細胞が蓄積され、増殖して“がん化”が起こる。
がん化した細胞は塊を作り、周囲の組織を浸潤破壊し、血管やリンパ管に入り込んで遠隔臓器に転移し、転移した部位で増殖、浸潤、破壊を起こすことになる。
発がん要因にはさまざまなものがある。最も知られているのは“タバコ”で、タバコに関連したがん腫としては肺がんがよく知られているが、喉頭がんや食道がん、その他多くのがんがタバコと関連している。