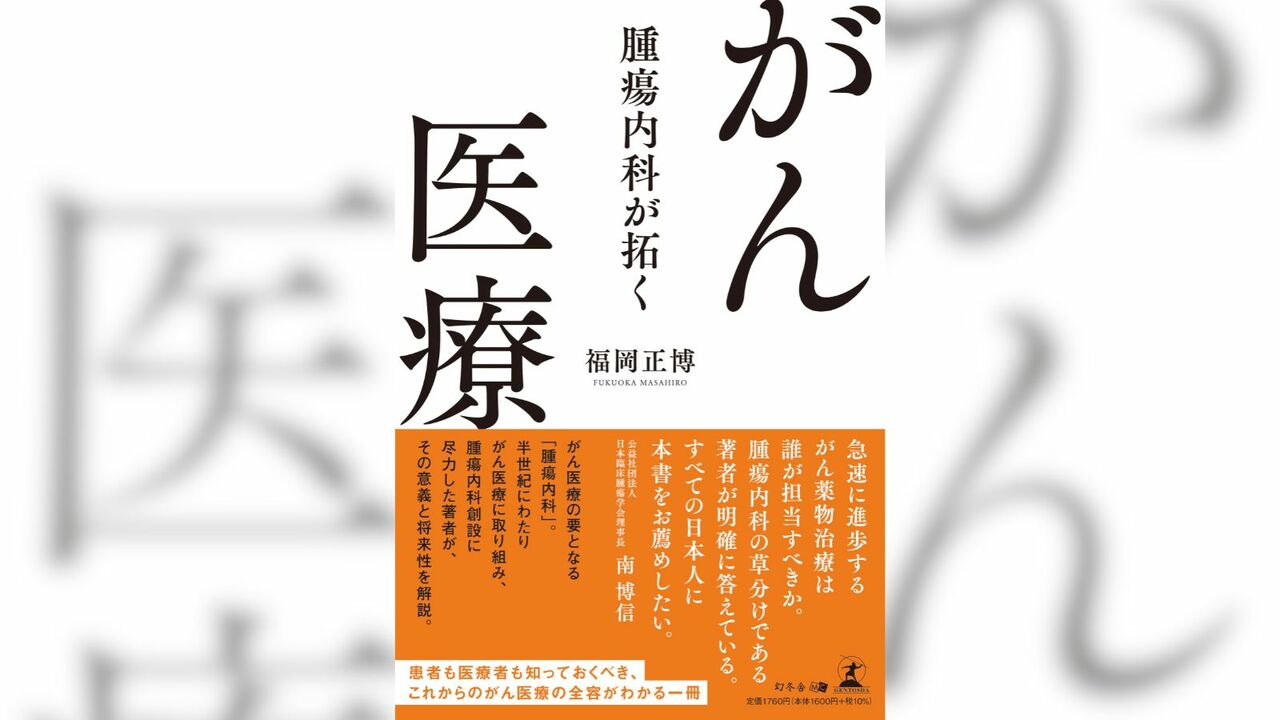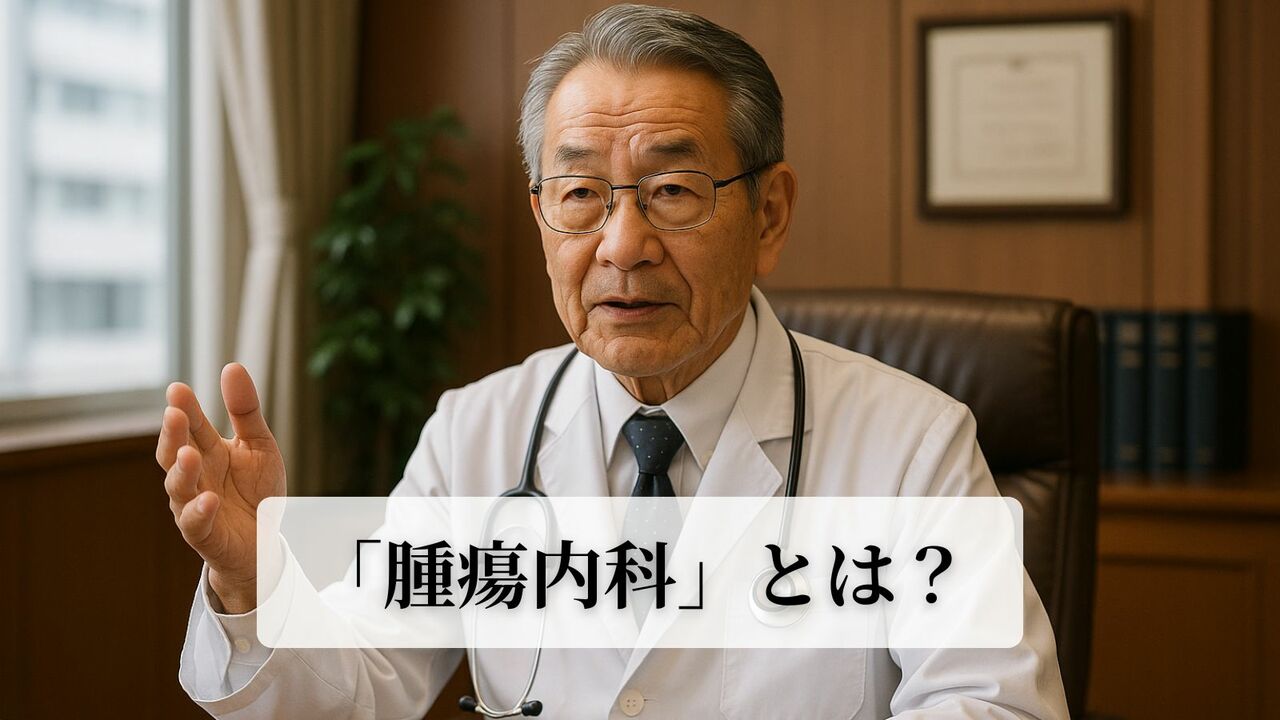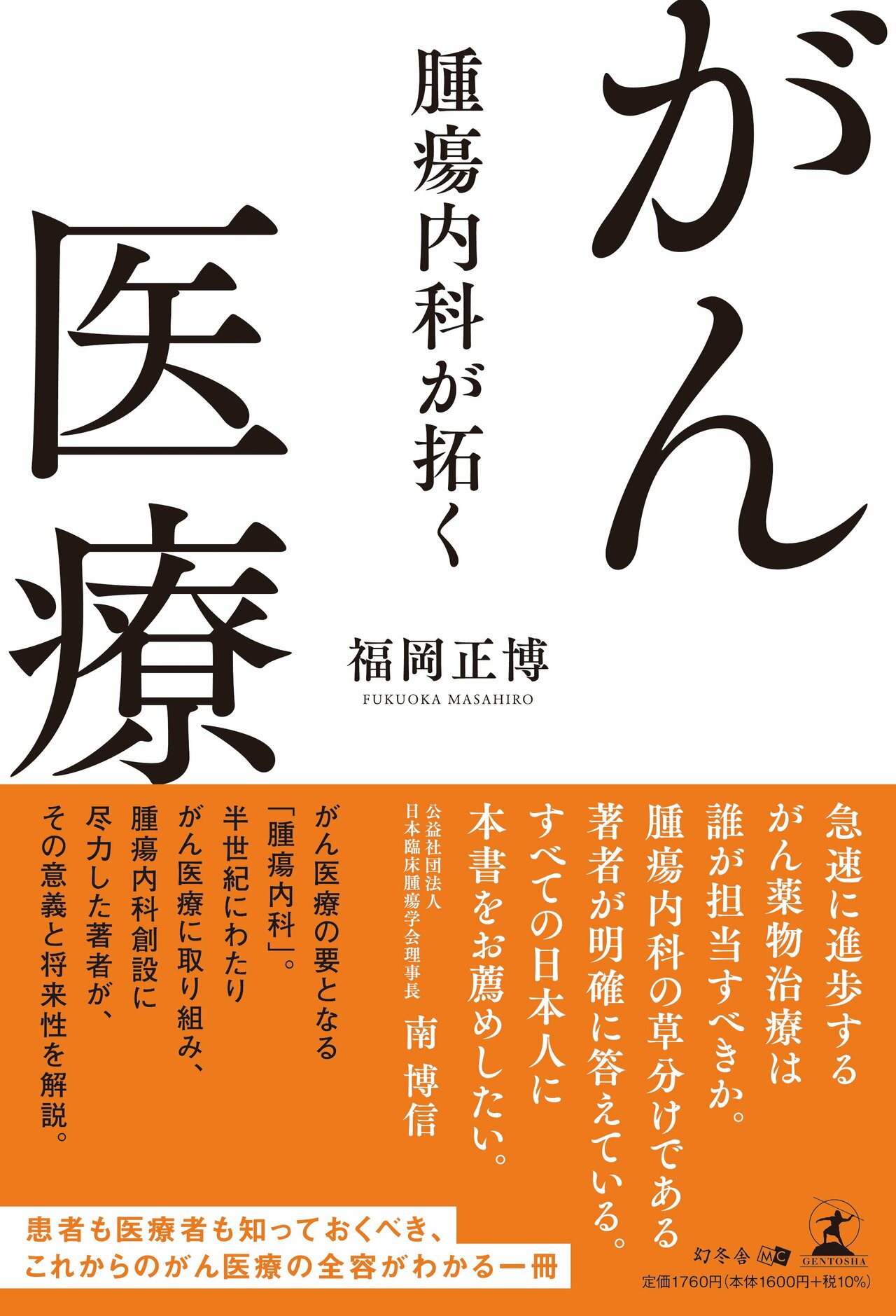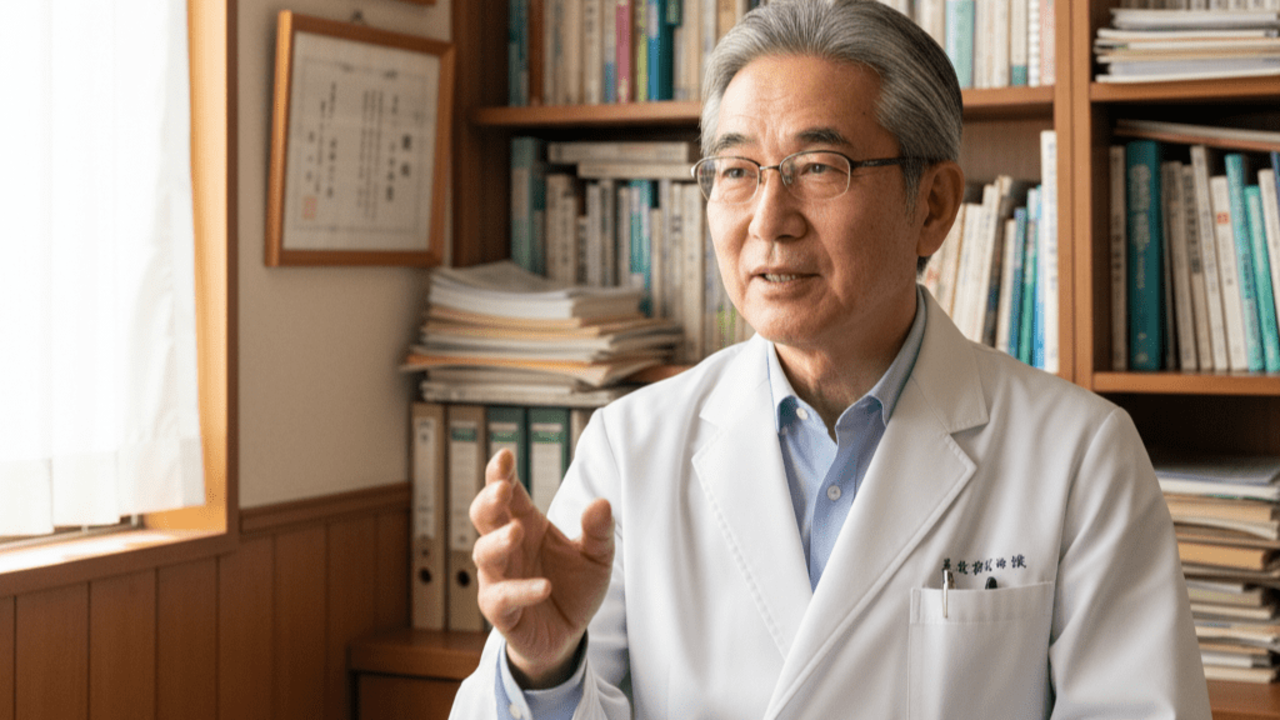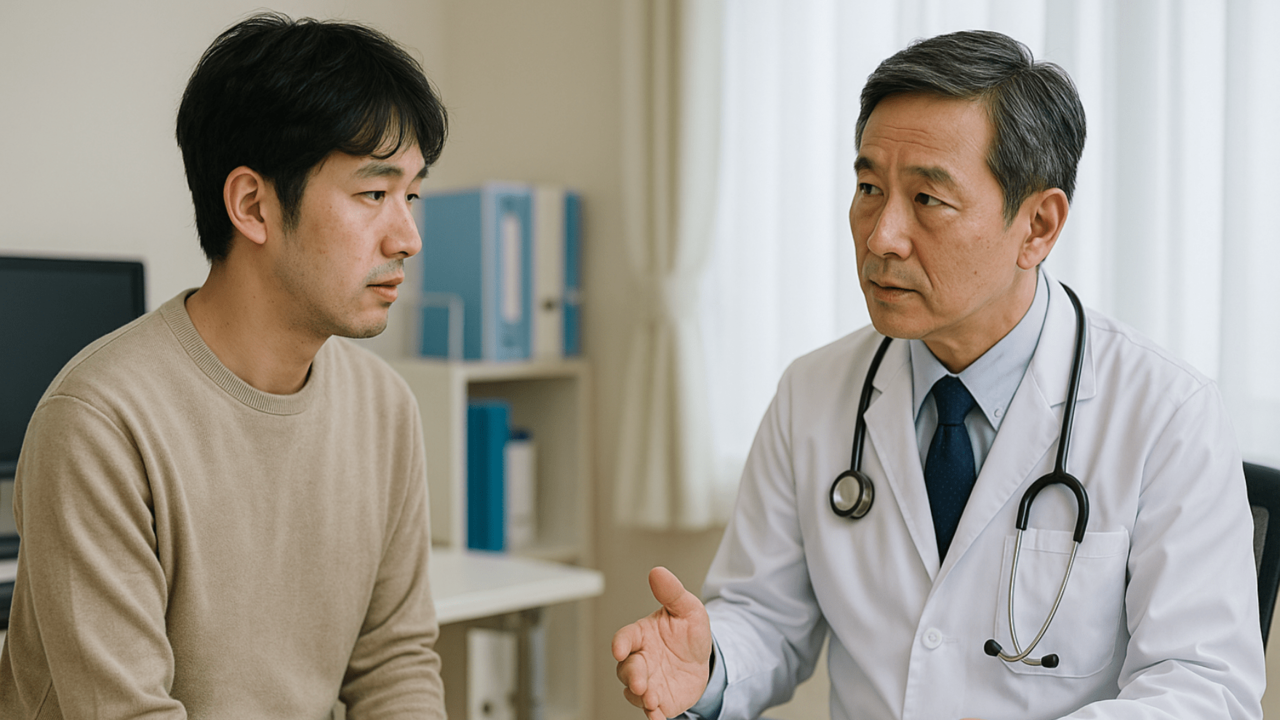はじめに
医学、医療が進歩したとはいえ、“がん”が治りにくい病気であることには変わりはない。わが国の死亡原因を見ると、1981年以来“がん”による死亡が第一位の状態が続いている。2023年の人口動態統計によると、全死亡者数157万人余りのうち、悪性新生物(がん)による死亡者数が38万人余りで24・3%を占め、4人に1人は、がんで死亡したことになる。
がんは遺伝子の異常によって起こるとされ、年齢を重ねるとともにそのリスクは増加し、高齢化が続く限りがん患者の増加も続くことになる。
がん患者の死亡率を低下させるには、がんの病態解明とともに、がん医療の進歩が不可欠である。日本は医療先進国と言われるが、果たしてわが国の医療体制は盤石だろうか。がんに罹ったら、どうすればよいか、日頃から関心を持って考えておかなければならない。
著者は、半世紀にわたってがん医療に取り組んできた。前半30年は、がんの中でも最も死亡者数が多い肺がんの診断や治療、特に薬物治療を診療・研究のテーマとしてきた。後半の20年は、肺がん診療・研究を続けながら、がん医療の仕組み、特にがん薬物治療を中心とした「腫瘍内科」の体制作りに注力してきた。
腫瘍内科という診療科は、一般の方には余り馴染みがなく、患者さん自身がいきなり腫瘍内科を受診することはほとんどない。わが国では、腫瘍内科を標榜している病院は未だ少なく、医師を育てる大学医学部においても、腫瘍内科の講座(大学における教育や研究の組織単位)や診療科(病院における診療単位)が設けられていないところが多い。
腫瘍内科は、そんな馴染みの薄い診療科だが、がん医療の中では極めて重要な役割を担っている。わが国では、未だ発展途上にある腫瘍内科であるが、その内容、意義をぜひ知ってもらいたいとの思いから本書を著すことにした。
がん診療については、本文で詳しく述べるが、“がん”と診断されると、手術、放射線治療、薬物治療のいずれか、または、それらを合わせた治療を受けることになる。手術治療は専門領域の外科の診療科で、放射線治療は放射線治療専門の診療科で治療される。
ところで、薬物治療はいずれの診療科が担当するのだろうか。欧米の病院には、メディカル・オンコロジー(日本語で腫瘍内科)という診療部門で治療を受けるのが普通である。
しかし、わが国で腫瘍内科という診療科ができたのは2000年以降のことで、それまでは、肺がんは呼吸器内科、胃がんや大腸がんは消化器内科や消化器外科で、子宮がんや卵巣がんは産婦人科、腎臓がんや前立腺がんは泌尿器科というように、それぞれの臓器診療科で薬物治療も行われるのが普通であった。そして、現在もそのような病院が多い。