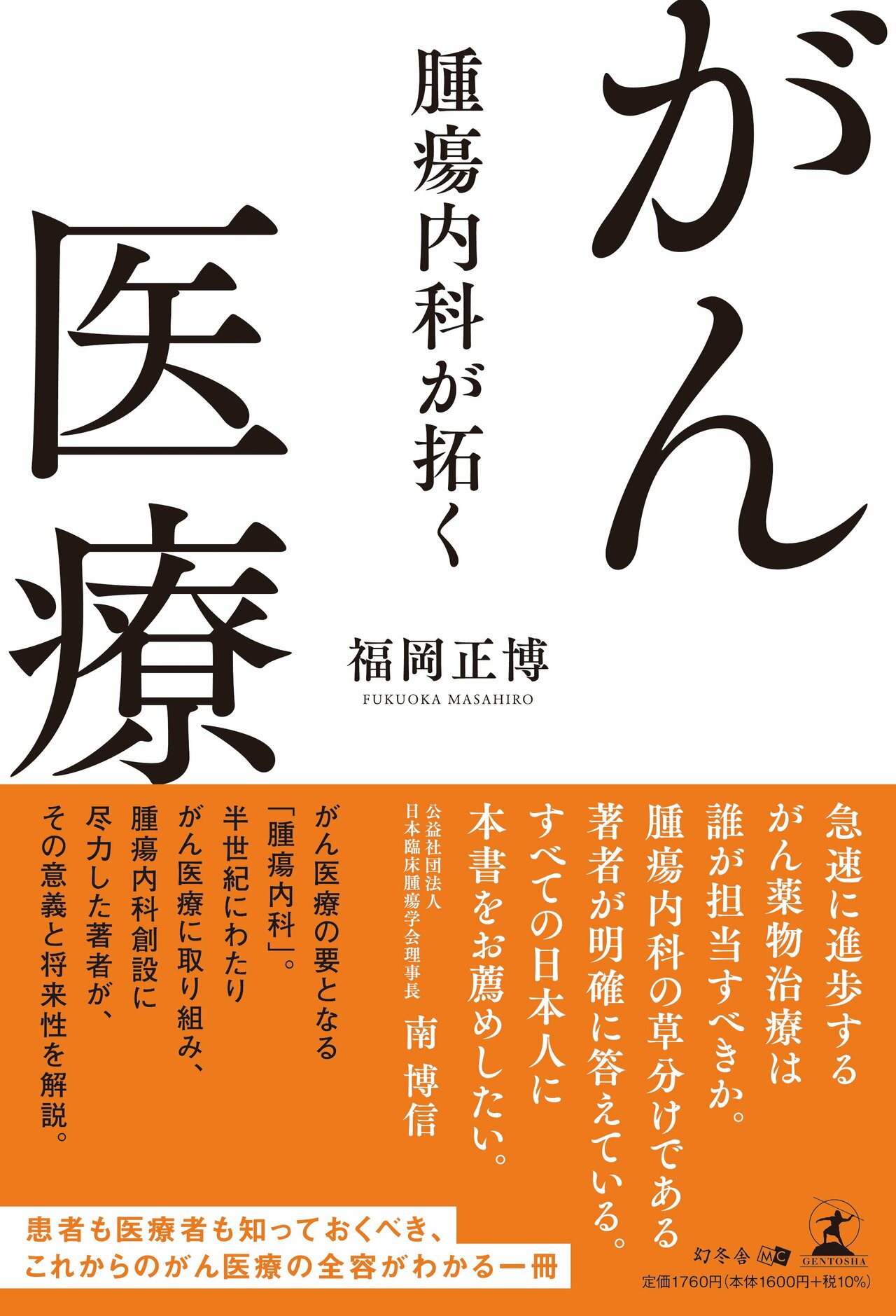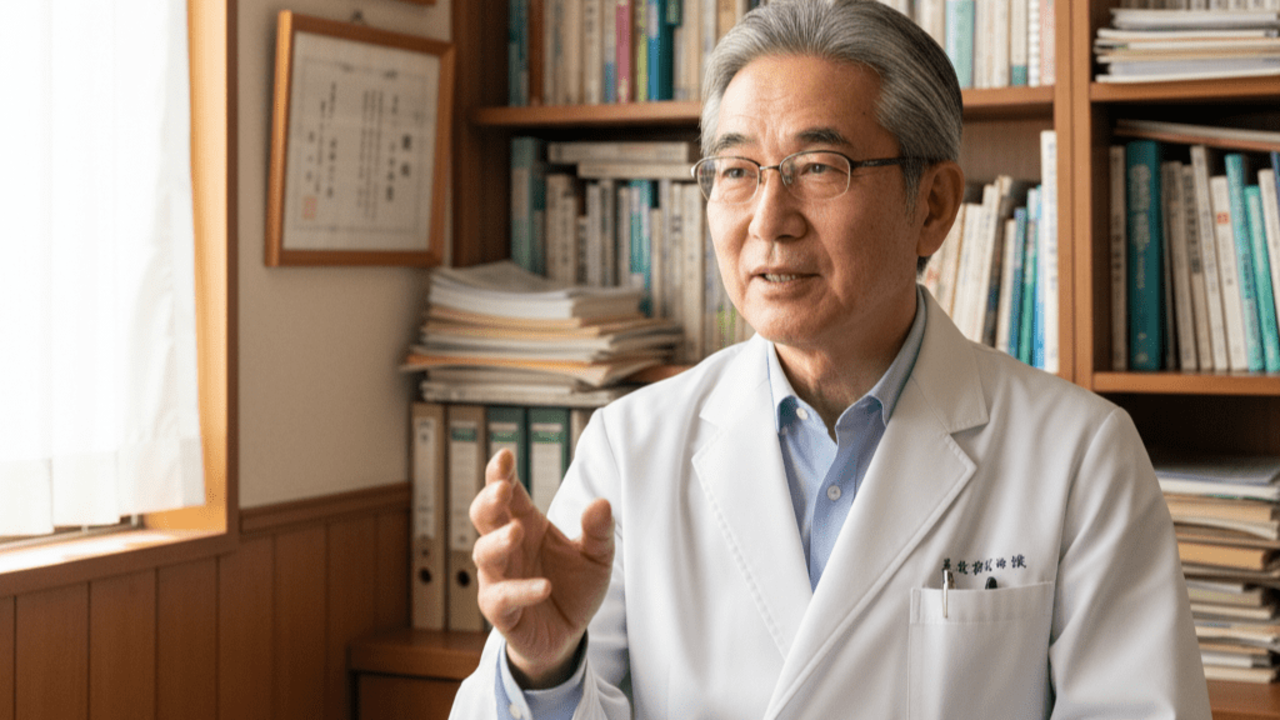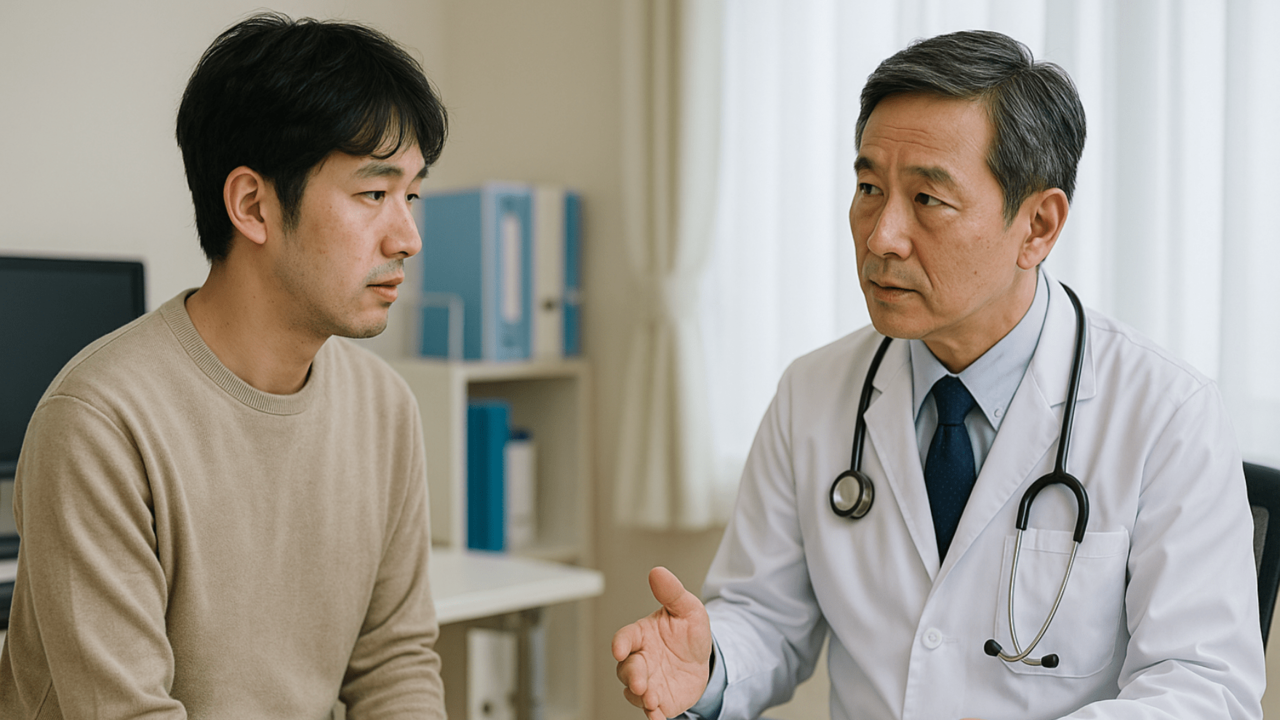大学病院やがん専門病院に「腫瘍内科」が創設されるようになったのは、平成13年(2001)の大学設置基準等の改正により、大学における講座制・学科目制に関する規定がなくなったこと、そして2003年に始まった日本臨床腫瘍学会の「がん薬物療法専門医制度」の導入によるところが大きいと思っている。
いずれにしても、わが国に腫瘍内科を確立することを大きな目標としてきた著者にとっては大変な喜びであった。しかし、それから20年以上経過した現在でも、腫瘍内科の拡がりが十分ではないことに、いささか焦慮している。
ところで、がん医療の中で腫瘍内科がなぜ必要なのだろうか。
本文で詳しく述べるが、がんの薬物治療は、手術治療や放射線治療と同様、極めて専門性の高い分野であり、相次いで開発される新しい抗がん治療薬について、その作用メカニズム、有効性、安全性を熟知した上で、対象となる患者さんに最適な治療法を選択し、十分に説明し納得・同意(インフォームド・コンセント)を得て治療を行う。
そして、効果と副作用を綿密に観察しながら十分な管理のもと実施しなければならない。これらを適切に実施することは決して簡単ではなく、専門的な知識と十分な経験が必要となる。そして、それを実践する人材(専門医)を育成することが極めて重要である。
そのようながん薬物治療の専門医を育てるのが大学における腫瘍内科と呼ばれる教室(講座)であり、がん専門病院における腫瘍内科という診療科である。
このような教室、診療科は、他の診療科から独立して存在することが望ましい。例えば、慢性閉塞性肺疾患、喘息、肺炎など多彩な呼吸器疾患を扱う呼吸器内科で肺がんの治療も行うこと、内視鏡検査や治療、がん以外の疾患を扱う消化器内科で同時にがんの薬物治療を実施すること、外科で手術を行いながら進行がんの薬物治療を実施すること、それが患者にとって最適だろうか。薬物治療は薬物治療専門の内科で取り扱うのは当然のことと思われる。
腫瘍内科の役割は、薬物治療だけに留まらない。新しい有効な治療薬や治療法を開発する臨床試験を実施することも腫瘍内科の重要な役割である。また、がん患者に生じるさまざまな苦痛を緩和する、いわゆる緩和ケアにあたることも腫瘍内科の大切な任務である。
本書は、著者が歩んできた半世紀の経験を基にして、がん医療における腫瘍内科の役割、がん薬物治療のあるべき姿について述べる。まず“がん”とはどのような病気なのか、わが国のがん患者はどのような状況にあるのか、がん医療の政策など、がんの全体像を示し、その上でがん医療における「腫瘍内科」の役割、その重要性を解説していく。
本書が、わが国のがん医療の発展に些かでも役立ってくれることを願っている。読者の方々には、そのような気持ちを汲んで一読いただければ幸いである。
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...