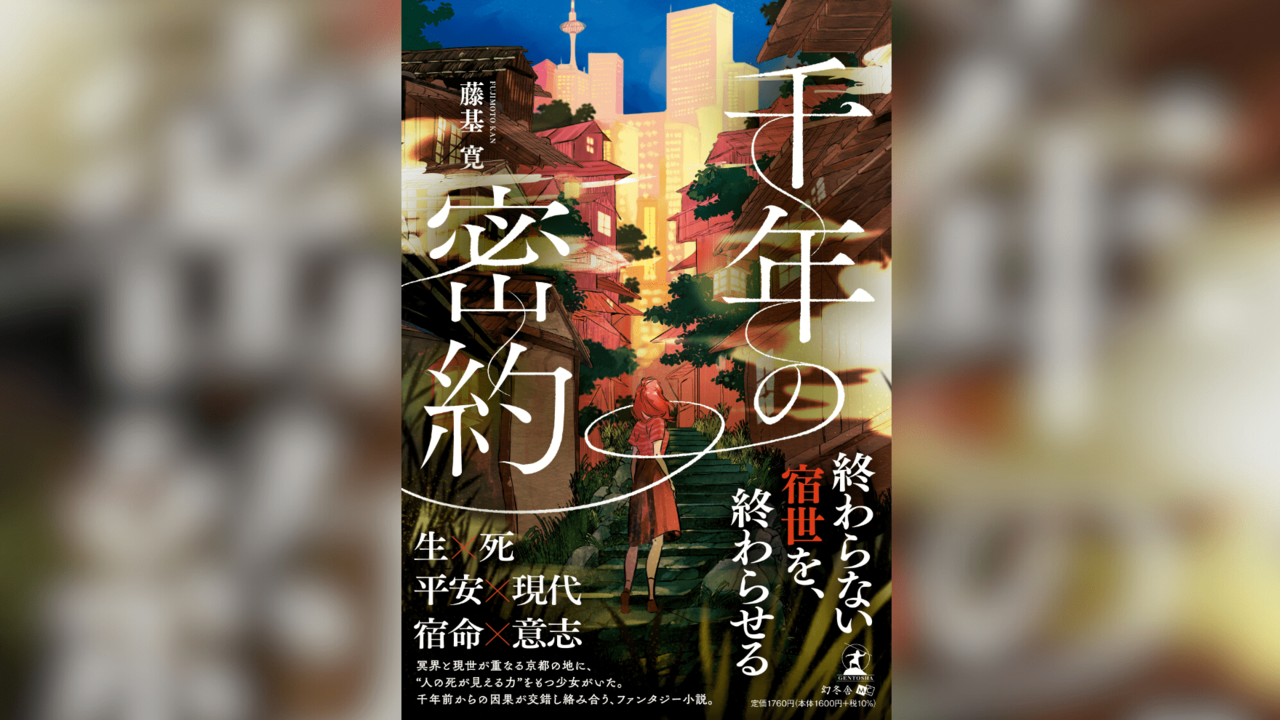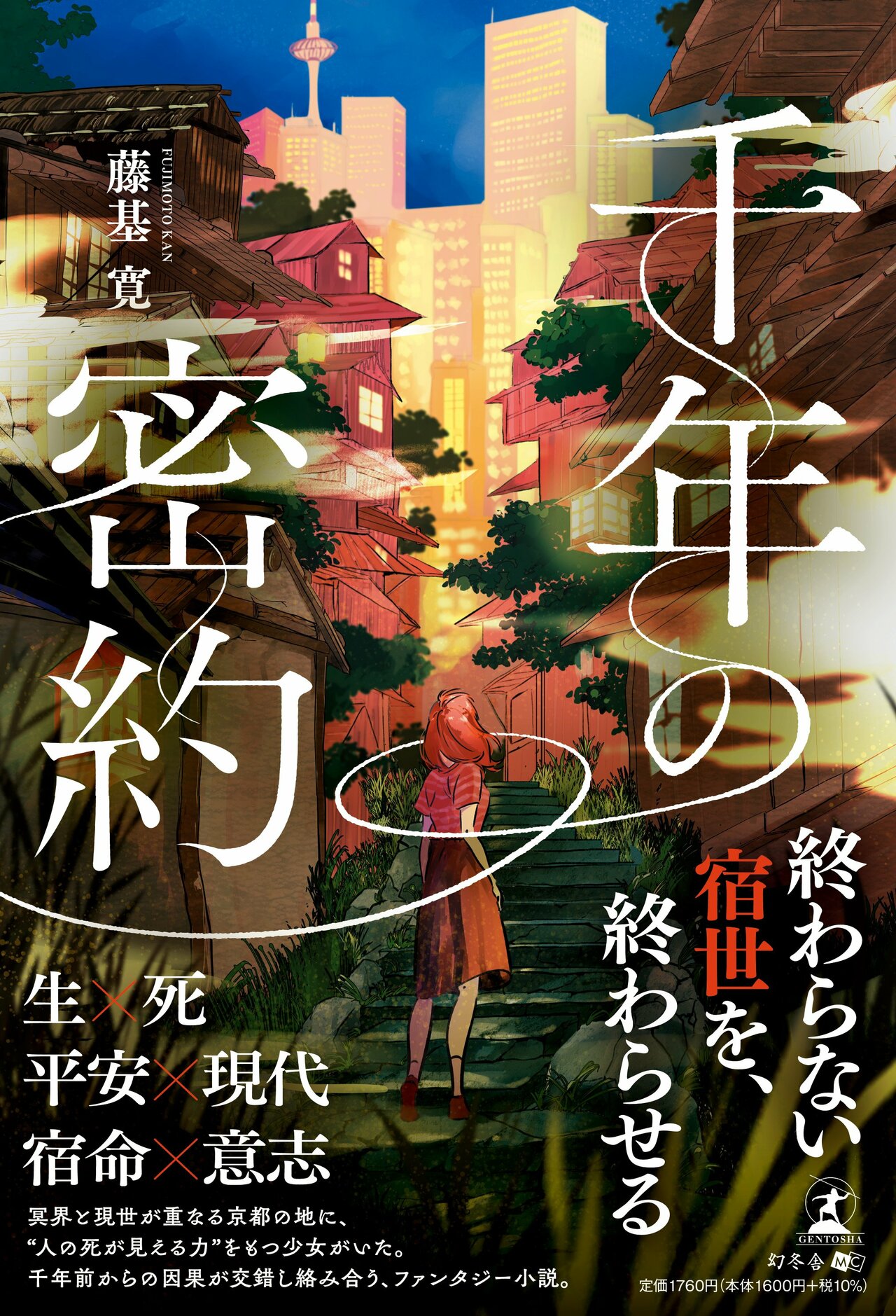【前回の記事を読む】「この条件を受け入れるなら、あと10年の命を授ける」――病に伏す姫君に閻魔が持ちかけた“恐るべき取引”とは?
夢子
鳥の声で夢子は目を覚ました。こんな爽やかな目覚めは生まれて初めてのことだ。そばでは昌子が念仏を唱え、父は比叡からの験者の到着を待っている。乳母のいねも御簾の内に入り手を合わせている。
「いね、いね」
と、夢子が声を掛けるといねはびっくりして、
「姫様、お目覚めですか」
と叫んだ。
「姫、大事ないか」
今度は道長がそう叫んで夢子の手を握り締めた。昌子も大いに喜んで嬉し涙を見せている。父と祖母の顔を見ると夢子もほっとしたが、二人の頭の背後に煌々と輝く光が見えた。
験者が来る前に夢子は元気になったが、道長よりたっぷりの褒美が比叡に寄進された。
夢子はこれまで殆ど口にしなかった食事を美味しそうに食べるようになり、日に日に顔色が良くなって普通の姫と何ら変わりのない様子になっていった。
道長は何とかいい婿を取らせようと思い、参議の一人の藤原為正(ためまさ)の次男である為信(ためのぶ)を婿に迎えることにした。
当時の恋愛は男から文が送られ女が返歌することを繰り返して、男が女の邸に通うというのが普通であったが、今回は親同士の話し合いで婿入りが決まった。為正にとっても為信にとっても飛ぶ鳥をも落とすと言われている道長の申し出を断る理由は一寸たりともなかった。
「殿様、わたくしは幼いころより体が弱く、父上のお情けに縋って生きて参りました。母方の身分が低かったので、父上の他のお子たちとは肩を並べるわけには参りませぬ。そんな私でも宜しいのでしょうか」
夢子は褥(しとね)の上で為信にそう呟いた。平安時代の貴族は親の身分によって人生が決まると言ってよかったし、たとえ左大臣道長の姫であっても母親の身分が低ければそれなりの人生しか送れないのであった。
「始めは父の仰せでそなたに文を遣わしたが、こうして夫婦になると本当によかったと思っておる。左大臣殿から従四位下に昇進する旨仰せがあったばかりだ。そなたのお陰だ」
「まあ、ご出世ですか。おめでとうございます」
夢子は喜んでみせたが、為信の頭の上の光が父のものとは違うことを不思議に思っていた。