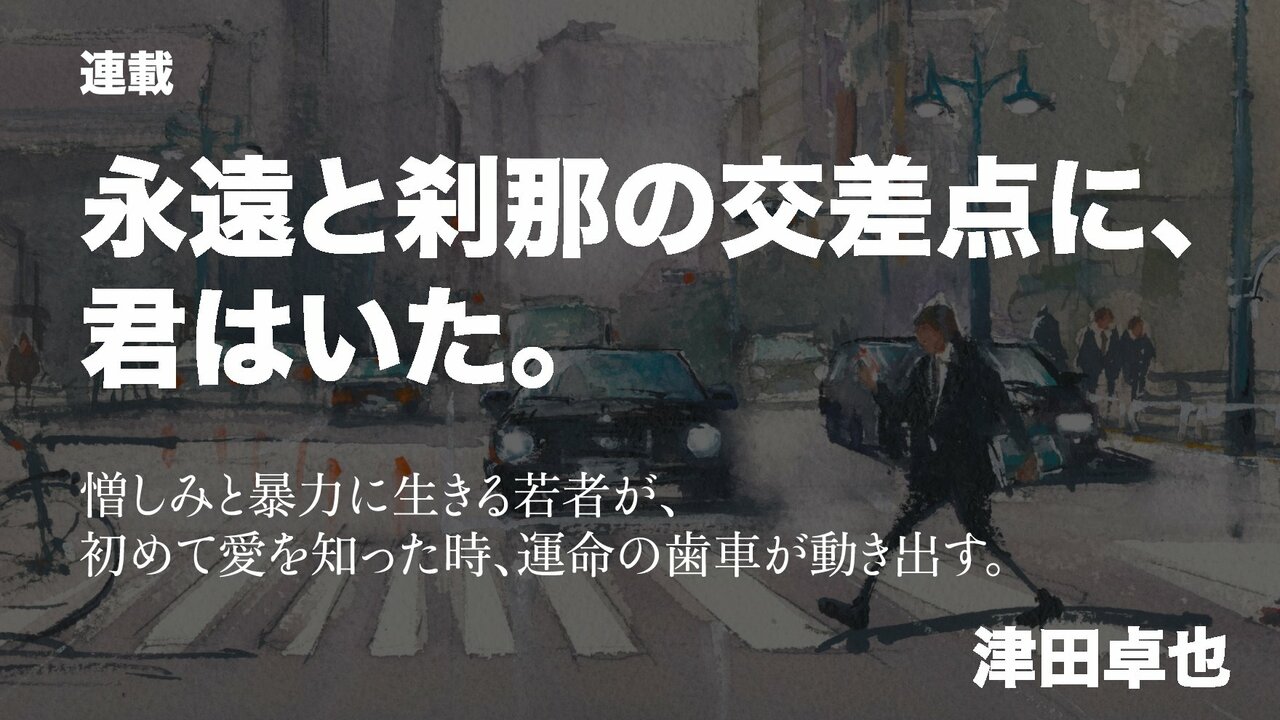【前回の記事を読む】妻子持ちの男。高校生の娘がいる男。私と交わった後、平気で妻と娘が待つ自宅に帰る男――私はこの男を愛しているのか?
第一章
3
稽古場を借りているビルは、下北沢の駅前にあった。
ただし、本多劇場やザ・スズナリなどの劇場がたくさんある南口ではなく、お洒落な雑貨店と、むかしからの商店街が混在する北口を出て徒歩五分くらいのところだ。
下北沢。石を投げれば、売れない役者かミュージシャンに当たると言われる街。地方出身者が大志を抱き、集まる街。
若者の出入りは多いけれど、どことなく俗っぽい印象は拭えない。駅の周りはごちゃごちゃしていて、古いビルと新しい店が並び、小さな飲み屋の並ぶ横町の入り口も見える。駅の正面には中途半端な広さのロータリーがあり、ガードレールに寄りかかっている人待ち顔の男女や、エステサロンのチラシを配る若い女性、所在なげにたむろする若者など、雑多な人々が行き交っている。
ひとりでいたいけれど、アパートの部屋で孤独に耐えられない時、このロータリーにどれほど慰めを得てきたことか。別に何か目的があるわけではない。ただこうやってぼけっと人の流れを見ていると、この街が自分を守ってくれるような気がした。まるで街が抱き締めてくれているみたいに。
今日子はガードレールに腰掛け、コンビニで買ったホットティーを飲みながら、駅の改札を見ていた。
見るともなしに、動く人々を見る。
話し合い、笑い合い、声を上げ、抱き合い、ケータイを見ながら、行き過ぎる人々。
この人たちもきっと誰かと愛し合っている。愛し合ってセックスをする。そう考えると、今日子は不思議な気分になった。
あのお揃いのコートを着ている可愛らしいカップルも、おなかの突き出たサラリーマンも、厚化粧のおばさんも、まだ幼い子供たちも……いつか誰かとセックスをする。昨日の私と河合がしたみたいに。まさぐり、舐め合い、交わる。そう。みんなセックスをする。
どれほどの人たちが本当に愛し合っているのだろう。どれほどの人が心から信頼しあっているのだろう。どれほどの人が死ぬまで一緒にいるのだろう。どれほどの人が……。
また涙が出てきた。
ポケットティッシュで顔を拭った。
結婚願望はなかった。それよりも、とにかく女優として成功したかった。恋愛は二の次、三の次と思っていた。河合に会うまでは。
いまでも結婚願望はない。子供が欲しいわけではないし(どちらかと言うと子供は苦手だった)、ひとりでいることにも慣れていた。そんな自分が、誰かと一生同じ家で暮らすなんて想像すらできなかった。でも、河合とつきあうようになってから、「女優として成功するまでは恋愛なんかにうつつを抜かしていられない」と役者仲間に宣言していたのが嘘みたいに、河合のことばかり考えてしまう。
これが愛というものなのか?
河合はいままでつきあった男たちとはまったく違う人種だった。繊細に見えて、ときに強引で大胆。細かいところに気がつき、今日子の感情を的確に判断し行動する。何より、今日子の知らないことをたくさん知っていた。シェークスピア、チェーホフ、ベケット、別役実、つかこうへい、唐十郎、寺山修司。ぜんぶ河合から教わった。
河合が話す言葉は魅力的だった。豊かな語彙を駆使し、低音で呟かれるその言葉は、今日子には一篇の詩のように聞こえた。
「今回のテーマが、『愛と性』であることに変わりないけれど、今回の『二十分間』の劇場の中は、愛を永遠に閉じ込めた空間であり、また時空を超えて広がる宇宙でもある。劇場は、無限と有限を同時に表現するメタファー。そしてそれは子宮でもある。女優は『罪と罰』のソーニャであり、『二十分間』は新たな生命、胎児の誕生の時間であり、始まりの時間でもあるんだ」
今日子には、河合の言っていることの意味がよく理解できなかった。それでも、河合の話を聞いているのが好きだった。熱っぽく、ときに髪をかきあげ、芝居の構想を話す河合の表情が好きだった。自分の知らない言語から作り上げられる物語は、河合の創造した世界であり、今日子にとっては、ここではないどこか 、であった。そしてそれは、夢の世界でもあるように思えた。今日子には、河合が星の王子さまのように見えた。
ずきん。
突然背中に激しい痛みが走った。耐えきれずに体を曲げた。同時に猛烈な吐き気がした。アスファルトに両手をつく。汗が噴き出す。