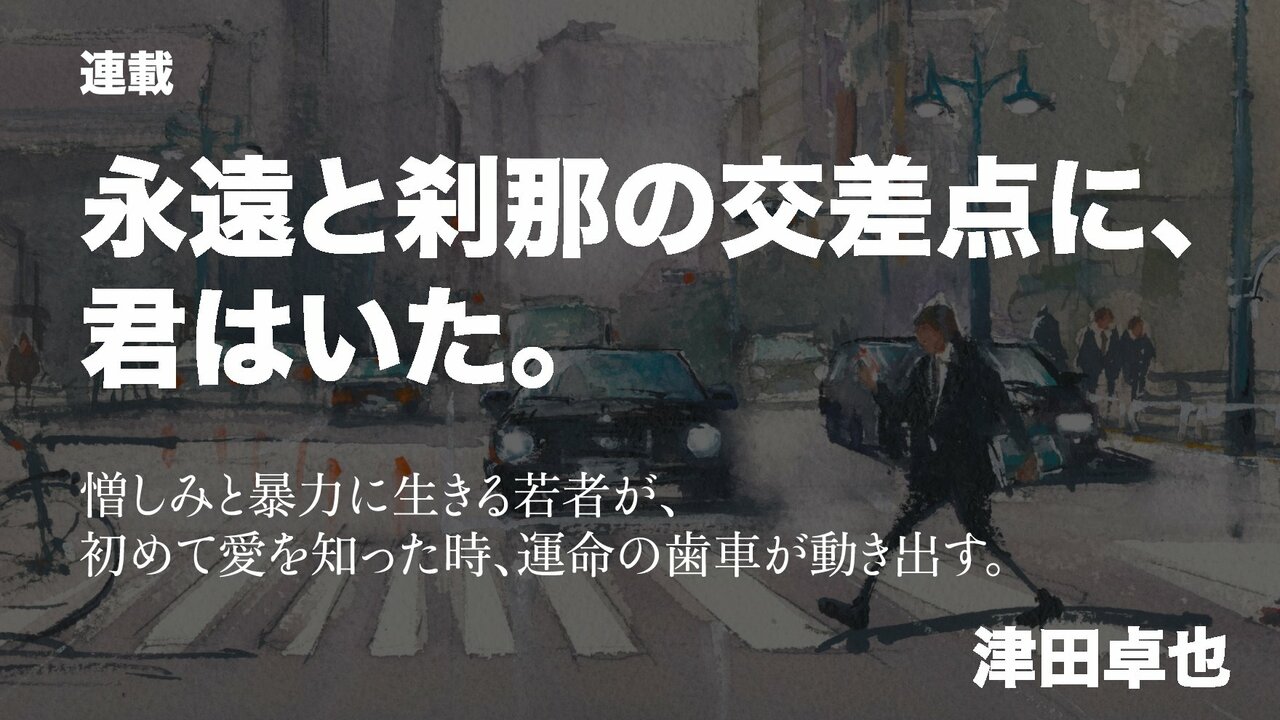【前回の記事を読む】36歳を迎えた息子の誕生日、父が語り出したのは“愛”――沈黙を挟み静かな対話が始まった
第一章
1
父は黙っていた。だが、色素の薄い瞳はしっかりと博昭を捉えていた。
「そんな講釈を聞きたいんやない」と父が言った。その声には抑揚というものがなかった。博昭はどう答えればよいのかわからず、グラスの水をひと口飲んだ。
「質問の仕方がわるかったか?」父は髪を撫でた。肩まで届く長い髪。癖のある髪は、目鼻立ちのはっきりした容貌と相まって、父をますます国籍不明にしていた。
「じゃあ、こう聞くわ。おまえのお父さんや。実のお父さんは、おまえのことを愛してたと思うか?」
博昭は養父を、風間を見た。目が合った。風間の瞳は風のない海のように静かだった。
博昭は大阪の茨木市で生まれた。大阪のベッドタウンであるその街は、高度成長期に栄え、バブル崩壊とともに寂れていった。昭和の末期に建てられた家ばかりの街は、古きよき時代でもなく、新しい可能性に満ちた街でもない、B級映画のセットのような街だった。
実の父と母は喫茶店兼スナックを営んでいた。朝早くから店内を清掃し、珈琲を入れ、店を開けた。ランチの時間には工場で働く労働者で賑わい、スナックに変身すると、深夜遅くまでカラオケの音が響いた。博昭は店の二階で暮らしていた。
ひとりっ子の博昭は、夜中に聞こえる下手な歌声に耐えられず、よく家から抜け出し、コンビニやゲームセンターで時間を潰した。寂しくはあったが、家にいるよりはマシだった。博昭にとって、家はうるさいだけのただの冷たい箱だった。