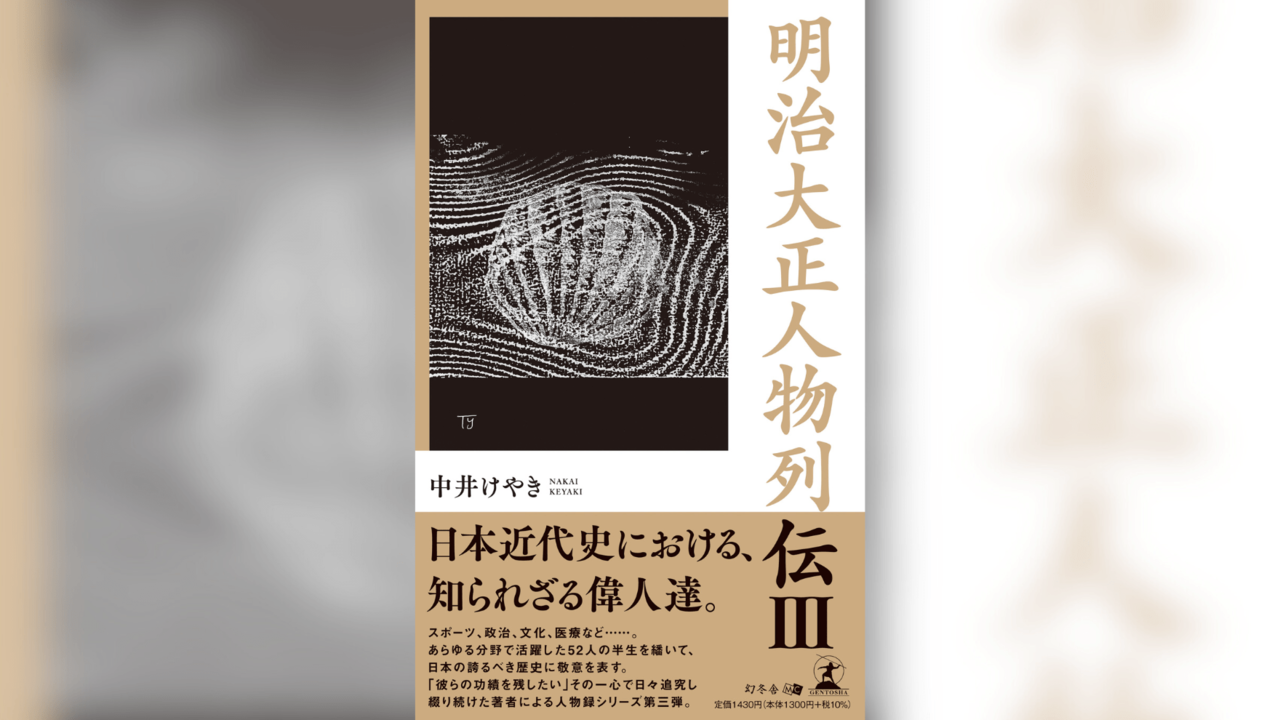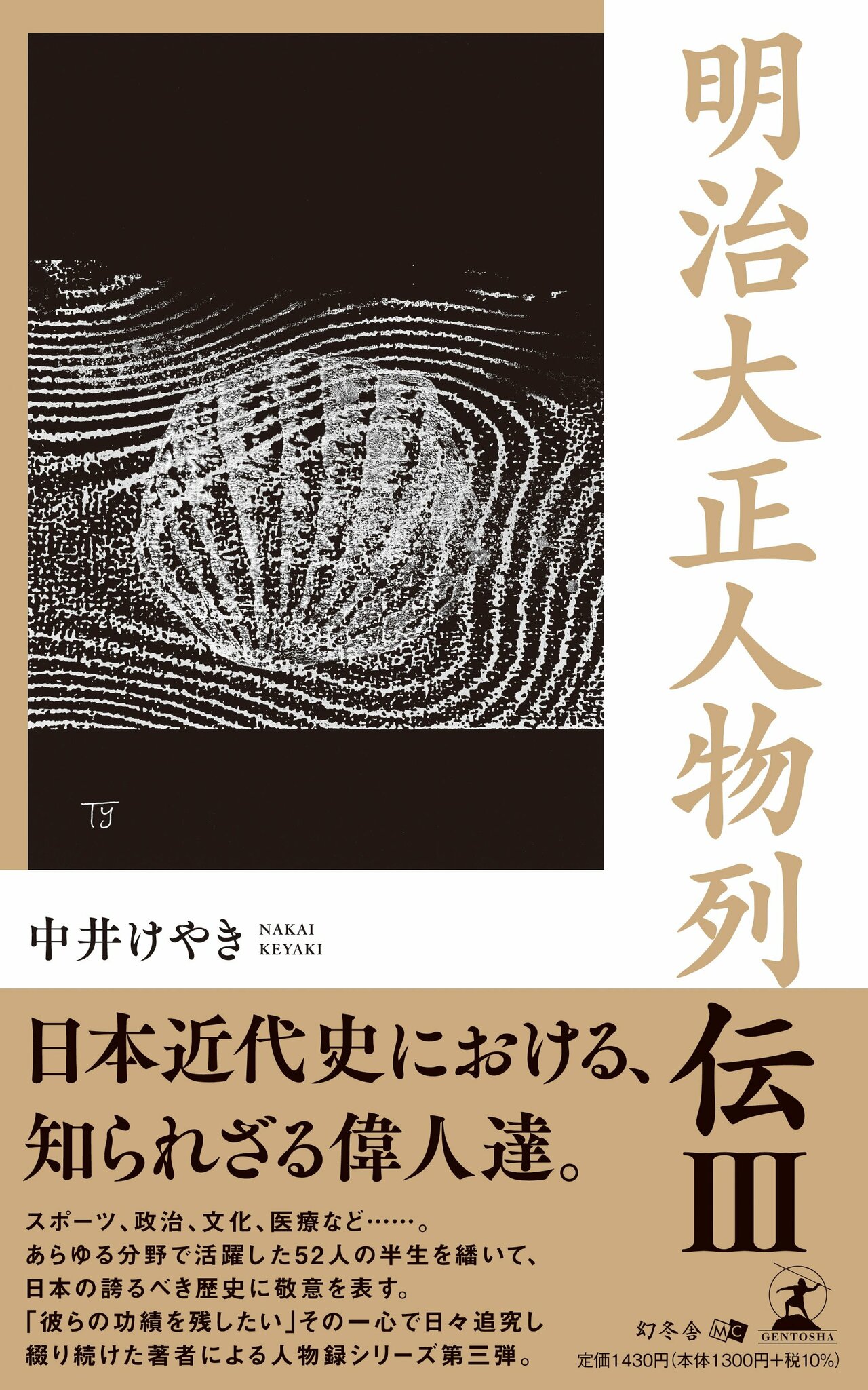【前回記事を読む】【明治大正人物列伝】1912(大正元)年表から、当時の出来事を細かく振り返る。日本の誇るべき歴史に敬意を表して…
春の記
2021 1.9
北海道鉱業開発の先駆者、ベンジャミン・S・ライマン
日本は四季があっていい。樹木の緑に花々、落葉しても樹形が面白い。雪が降れば山や川はむろん見なれた景色が絵になる。しかし残念ながら自然災害があり痛い目に遭う。
昨年は台風こそ来なかったがコロナ禍、とんでもないものに脅かされ、自由な行動を制限されている。
それだけでも困るのにこの冬、度を越す風雪で被害を被り困難続きの地方がある。その一方、東京近辺は晴れ間が多い。
冬型の天候にしても、近年その度合いがひどく被害も大きい。温暖化が拍車をかけているのだろうか。
さて、人の暮らしは天候によって左右されがちだが、産業の盛衰によっても離合集散する。賑わった炭鉱が閉山すると、人が去り鉄道も廃線になってしまう。しかし、それでも、故郷に踏みとどまる人がいる。
――かつて炭鉱の町として栄えた北海道三笠市幌内(ほろない)町の集落で、唯一営業を続ける店がある。大正末期の1920年代後半に創業した「太田金物店」だ。幌内炭鉱の衰退とともに人々が去り、たった二人が暮らす消滅寸前の集落を三代目店主の太田悦子さん(86)が静かに見守っている。
〈大正創業二人の集落いまでも/北海道・幌内/終戦伝えたラジオも〉
――幌内炭鉱は1879(明治12)年、明治政府のお雇い外国人ベンジャミン・ライマン(米国)らによる地質調査を経て開坑された。北海道開拓長官の黒田清隆や伊藤博文も開坑前に現地を訪れており、幌内炭鉱の開発は日本の近代化に向けた国家プロジェクトだった(「元炭鉱のまち照らす金物店」(毎日新聞2020年12月7日 山下智恵)。
鉄道建設など大事業のお雇い外国人はイギリス人と思っていたので、アメリカ人というのが気になった。そして、彼が出ていそうな何冊かを見ると、どれも好意的で興味がわい た。