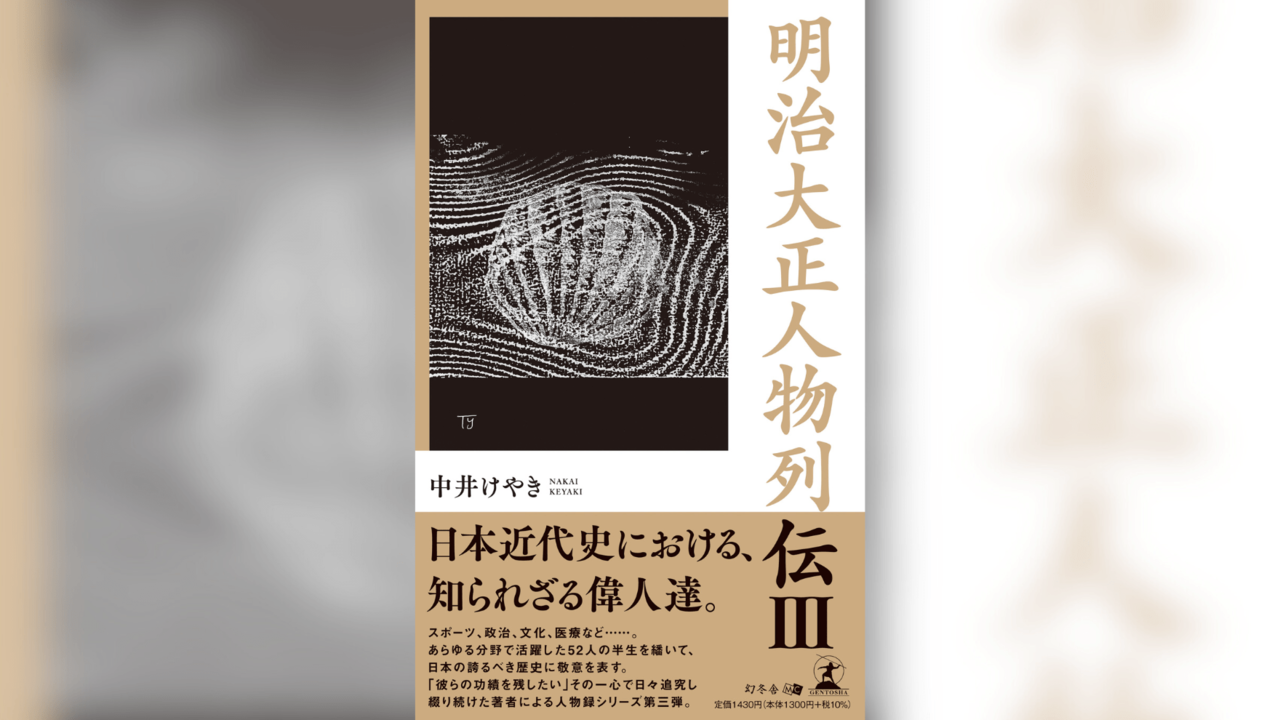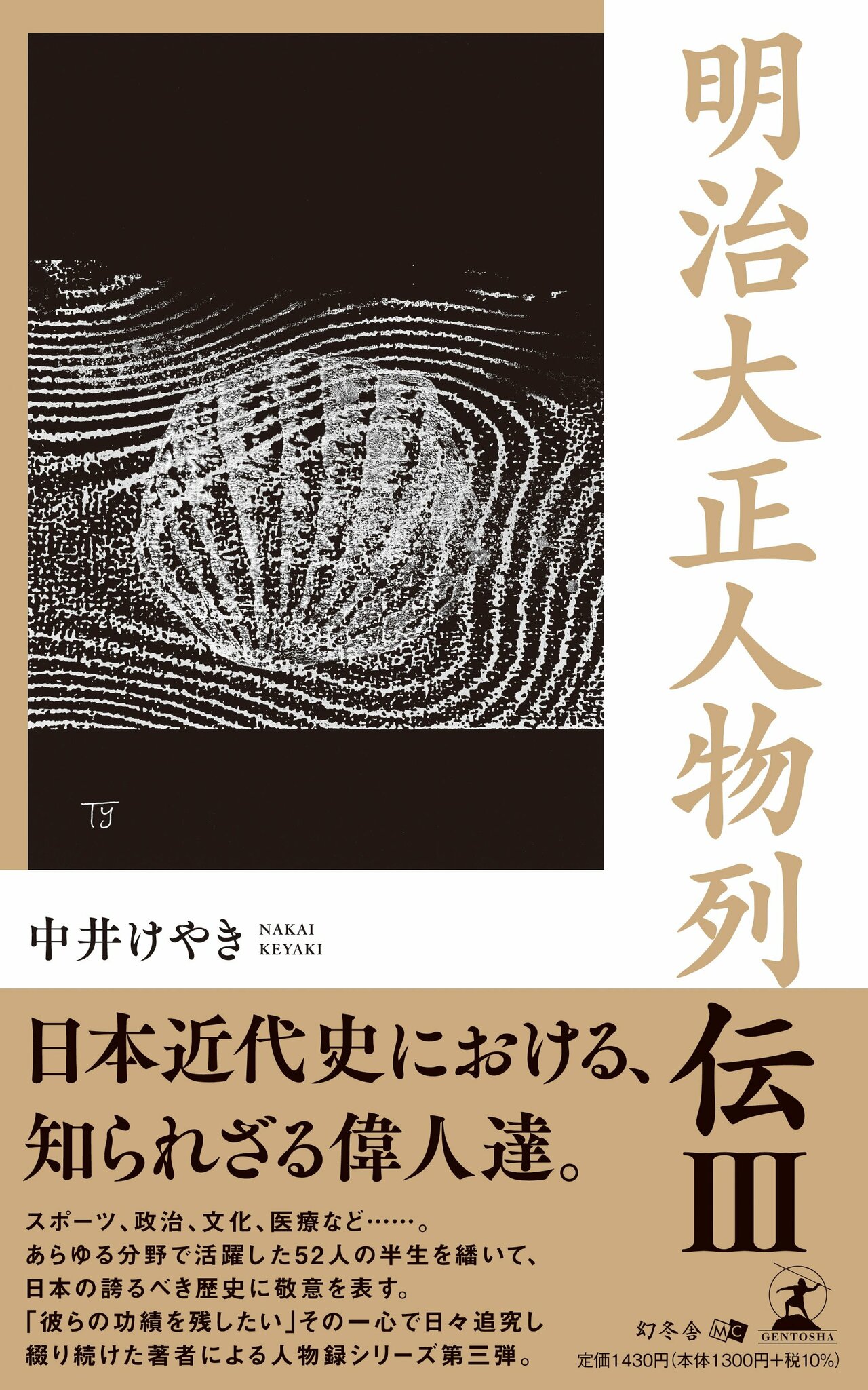【前回記事を読む】知られざる偉人たちの物語を紐解く。教科書には載っていない日本近代史の影の功労者たちを紹介!
春の記
2021 1.2
1912年、明治の終わり・大正の始まり
1912(大正元)年
しろがねの雪ふる山に人かよふ 細ほそとして路(みち)みゆるかな
(斎藤茂吉自選歌集『朝の蛍』、改造社1925)
8月1日 ※1鈴木文治ら友愛会結成。
5日 御停止明け。
そのあとも自粛ムードが続き、装飾屋・楽隊・日本囃子・蓄音機商など営業不振に。喪章の着用が流行。
岩野泡鳴「発展」の発禁に抗議し、総理大臣らに「文芸の発売禁止に関する建白書」を提出。
15日 手動式塵芥吸収機「バキュームクリーナー」発売、一台60円。
21日 第二十九議会、第二次西園寺内閣・御大葬費議決の臨時議会招集。
木更津線、蘇我‐木更津全通。
24日 瀬戸内海の播磨灘で暴風雨、漁船多数沈没。
27日 越後鉄道、新潟‐吉田間が開通。
30日 所沢飛行場で陸軍がドイツから輸入したバーセバル式飛行船20分間飛行。
――「飛行船来たる」一たび伝えられるや満都の子女は、路上に奔出しその壮絶を眺め、あるいは屋根に上がり、望遠鏡を持ち出してその跡を追えるもあり(10月23日 東京朝日)。
31日 関東地方で暴風雨。
――厄日として気遣われたる二百十日の天候は、31日朝より険悪を示し…… 東京荏原郡鈴ヶ森八幡海岸付近は二丈余の高浪起こりて六郷川増水し、浅草公園のひょうたん池は溢水して六区付近に深水し(9月2日 東京朝日)
9月1日 東京浅草で大火。300戸焼失。
9日 名古屋・大須観音で初めて大正琴発売。
ヨーロッパ演奏旅行から帰国した森田吾郎(琴や笛の演奏家)が創案した簡易な楽器。日本で流行していた二弦琴とヨーロッパで見たタイプライターの仕組みを合体させて考案した。発売当時は、町のおもちゃ屋の店先で売られた。現在は弦の数が2本から5~6本にふえ音域も広がっている。
13日 天皇大葬の日、乃木典希(まれすけ)夫妻殉死。
22日 台風が日本全土を襲う。
夜半に四国地方東部に上陸、関西地方から若狭湾をへて日本海を北上、北海道に再上陸してオホーツク海へ去った。死者は愛知・岐阜・徳島・鳥取・奈良など13府県に及んだ。
25日 松竹女優養成所が開設され、東京・大阪・名古屋などから158人が応募し、20人が舞台女優第一期生となる。
28日 作家・永井荷風が結婚。