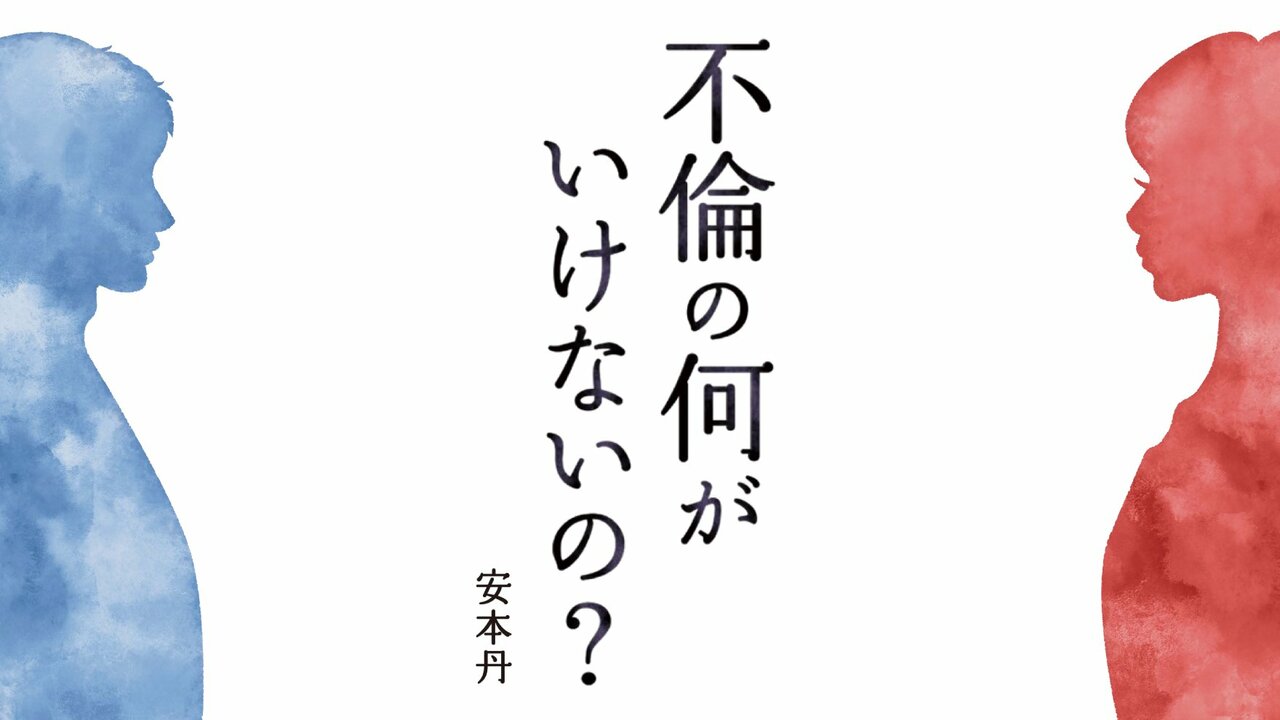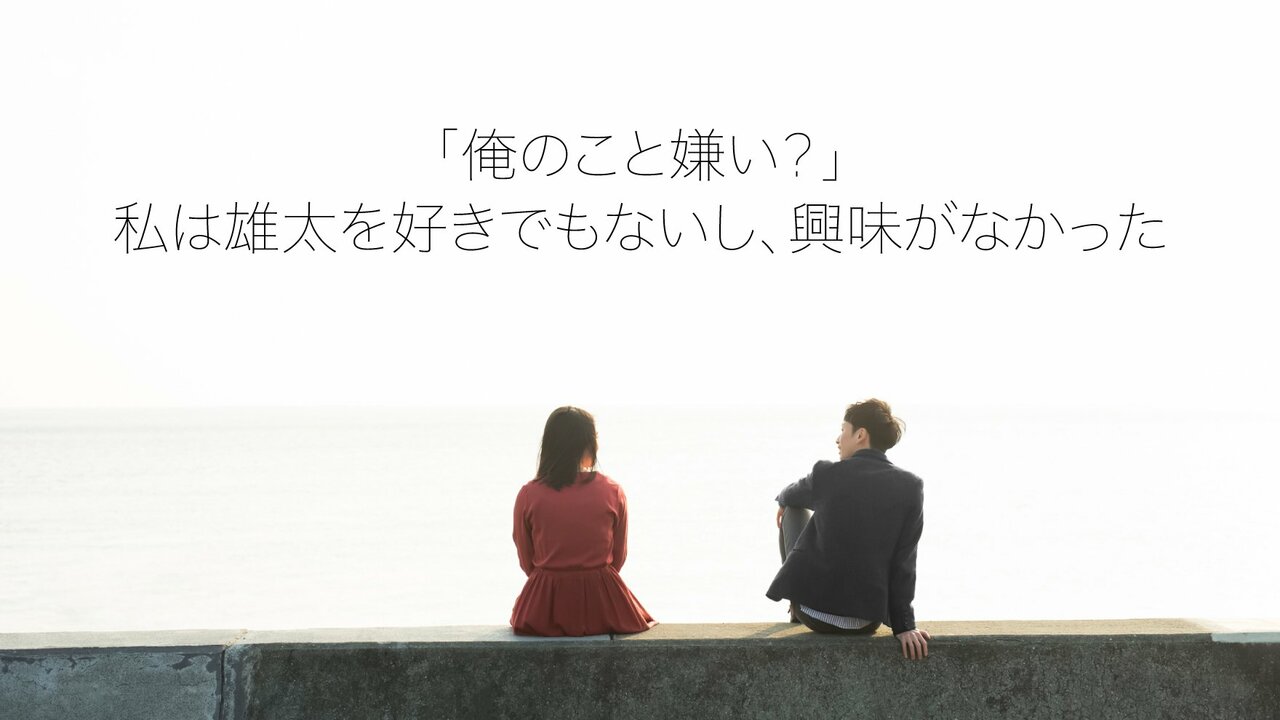第二章 雄太
誰もいないのか、と聞くと彼は複雑な、しかしありがちな家庭事情を話し始めた。
「妹がいるよ。まだ小さい。父親はいない。母親は夜働いてて、だからまだ帰ってこない」
帰ってきても部屋には来ないから安心して、と雄太は微笑んだ。長い歯茎がまたニョキッと飛び出す。
ふーん、と私は興味無さげな反応をした。内心父親はどうしたのかや、幼い妹は一人で大丈夫なのかが気になったが、あまり他人の家庭事情に干渉するのも気が引けて何も聞かなかった。父親や母親がいないことだって、私にとっては考えられないことではなかった。
「いつ寝てもいいからな?」
雄太はそう言ってテレビを点け、代わりに電気を消した。暗くて狭い部屋に、テレビの明るさが眩しい。雄太の顔も歯茎も鮮明に見ることができた。
たわいもない会話をしながら流れで私達はベッドに横になった。雄太はテレビのバラエティ番組を見ながら歯茎を見せて笑っている。
私は緊張でテレビの内容も入って来ず、一人壁の方を向いて寝たふりをした。しばらくしてテレビの音が消えた。そして、雄太が私の身体を弄(まさぐ)り始めた。私がそれを嫌がって見せると、彼は耳元で囁いた。
「俺のこと嫌い?」
嫌いな男の家に、泊まりに行く女がいるのだろうか。しかし、私は雄太のことを好きでもない。まだ彼のことはよく知らない。
しかしいまいち彼に興味が持てなかった。ある意味嫌いよりも、悪いのかもしれない。
私は何も言わずに振り返り彼の背中に自分から手を回した。びっしょりと汗をかいた背中にTシャツが張り付いている。私が抱きついたので安堵したのか、雄太は私の下着の中に手を入れた。
誰に教わったわけでもないのに自然と声が漏れる。快感で声が我慢できないというわけではなく、ただ声を出せば男性は喜ぶというのを、私はなぜか知っていた。一通り弄(もてあそ)ぶと、雄太は私の太ももで指を拭った。
気がつくと私は眠りに落ちていたようだ。カーテンから漏れる朝の光を浴びた部屋は、物は多いがきちんと片付いており昨日とは違って見えた。目を覚ますと雄太はベッドに座って壁にもたれてこちらを見ていた。
「お前まだ、ヒロキのこと好きだよな」
その口調はすごく優しかったのに、私は責められているように感じて罪悪感でいっぱいになった。叶わなかったヒロキへの想いが宙ぶらりんになったまま、好奇心を満たし寂しさを埋めるために興味もない男を利用している。
私は一筋の涙がゆっくりと頬を伝うのを感じた。頬を触るとアイラインが滲んだ黒くて汚い涙が手についた。
その後も私は雄太を好きにはなれなかったが、失恋の穴を埋めるのには丁度いい存在だった。雄太も、私のことは好きではなかったと思う。
それでも私は心の穴を埋めようとして、雄太と付き合いセックスをした。ヒロキの時とは違い痛みは全くなかったが、たいして気持ちの良いものでもなかった。
雄太と付き合ってからの私の生活はとにかく多忙だった。雄太は毎日でも会いたがった。毎日でもセックスしたがった。