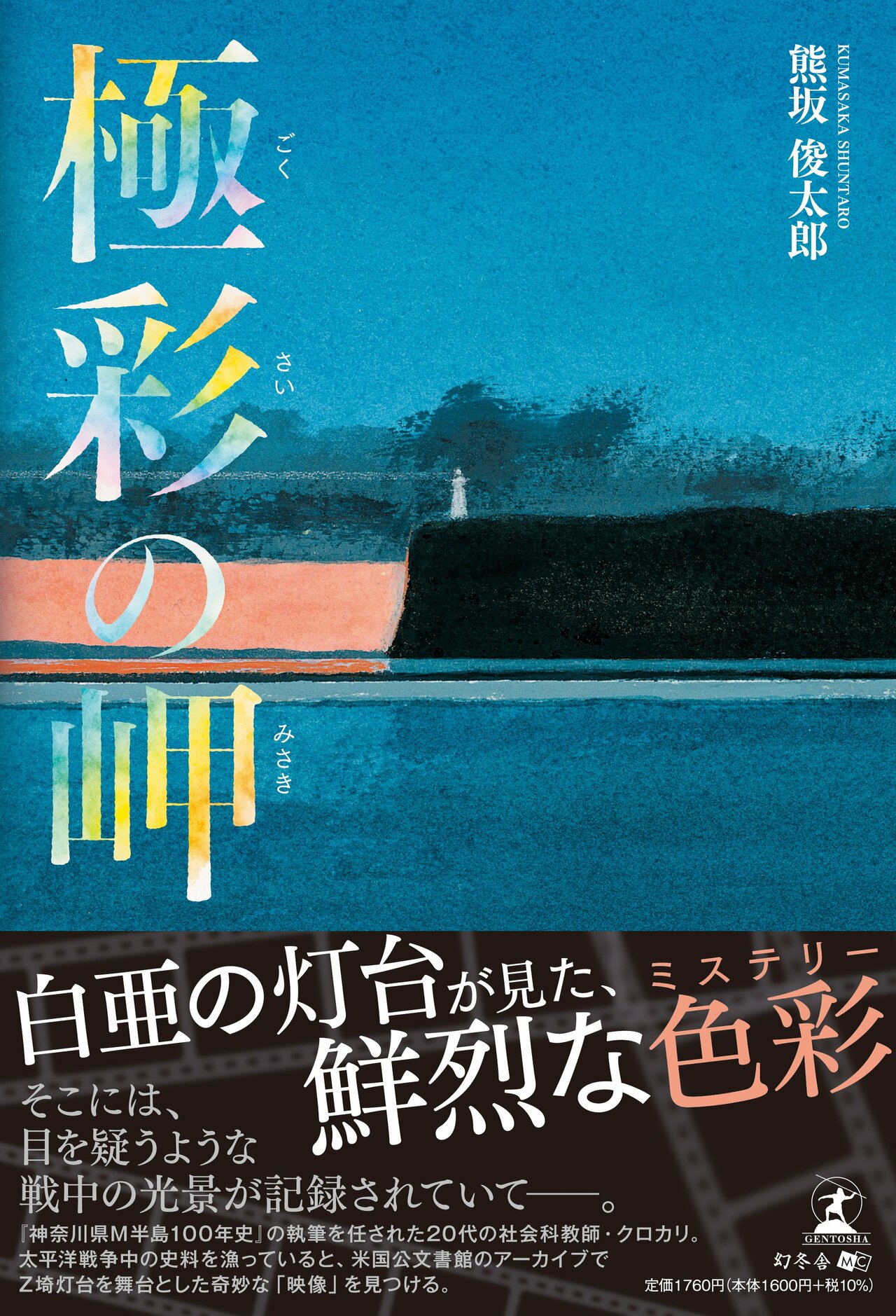この岬に灯台の祖型ともいえる燈篭矢倉(とうろうやぐら)が初めて組まれ、いわゆる“灯火堂”に松明(たいまつ)が焚かれたのは、江戸時代後期だった。
一六五八年(萬治二年)に創業した、灘のK酒蔵の資料館に残る『東国樽廻船海運記帳』には「その灯火、江戸へ“下る”最後の標(しるべ)として夙(つと)に知られ、船場門閥、豪商、二代目淡島屋左衛門が普請、修繕の一端を賄った」と記されている。
幕末期、すでに日本の近海には少なからず欧米列強の船舶が出没していたが、その静寂を破ったのが、言わずと知れた一八五三年(嘉永六年)、米海軍東インド艦隊、ペリー代将率いる“黒船来航”だった。
狂歌「泰平の眠りを覚ます上喜撰(じょうきせん)たった四盃(はい)で夜も眠れず」で知られるように、品川沖、わずか海岸線から三海里(約六キロ)まで接近した“黒い怪物”が江戸城に向けて放った威嚇の空砲は、文字通り、幕府を震え上がらせた。
果たして、開国を迫るアメリカに対して江戸幕府は、黒船来航の翌年の一八五四年(嘉永七年)に「日米和親条約」を締結。一八五八年には「日米修好通商条約」を交わし、以後、堰を切ったように欧米列強の船舶は全国各地の港に押し寄せることとなる。
だが、それにつけ、日本の港湾設備に対する列強諸国の酷評(クレーム)は日ごとに増していった。彼らは日本の海を「THE DARK SEA(暗闇の海)」と揶揄し、「直ちに欧米並みの近代灯台を建造せよ」と強く幕府に迫った。
十五代将軍、徳川慶喜はこの圧力に対して「改税約書」(江戸条約)で、取り急ぎ、東京湾、駿河湾、瀬戸内海などの重要航路の出入口、難所など全国八か所に近代灯台を建設することを確約。何とかこの窮地を切り抜けた。
幕府が、日々高まる欧米からの脅威に対峙するべく、築地、鉄砲洲、越中島などに西洋式の武術、砲術、軍艦操練のための「諸武所」「講部所(場)」を設置し始めたのもこのころである。