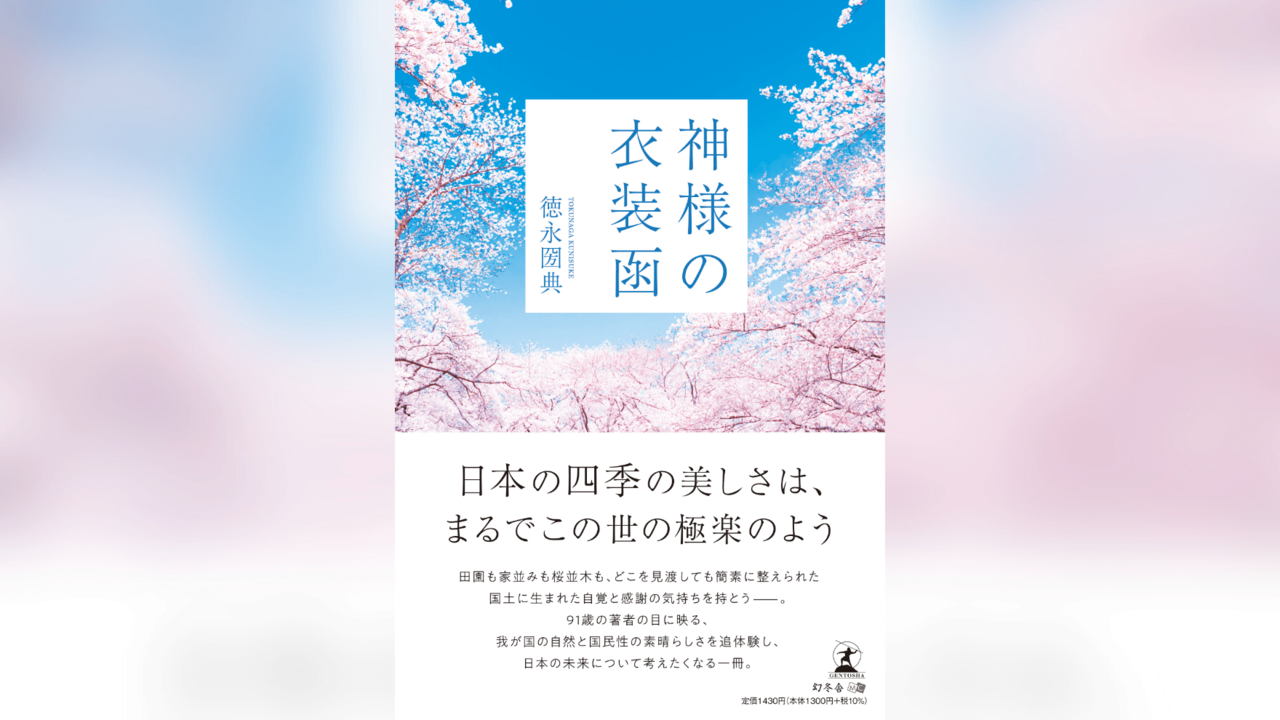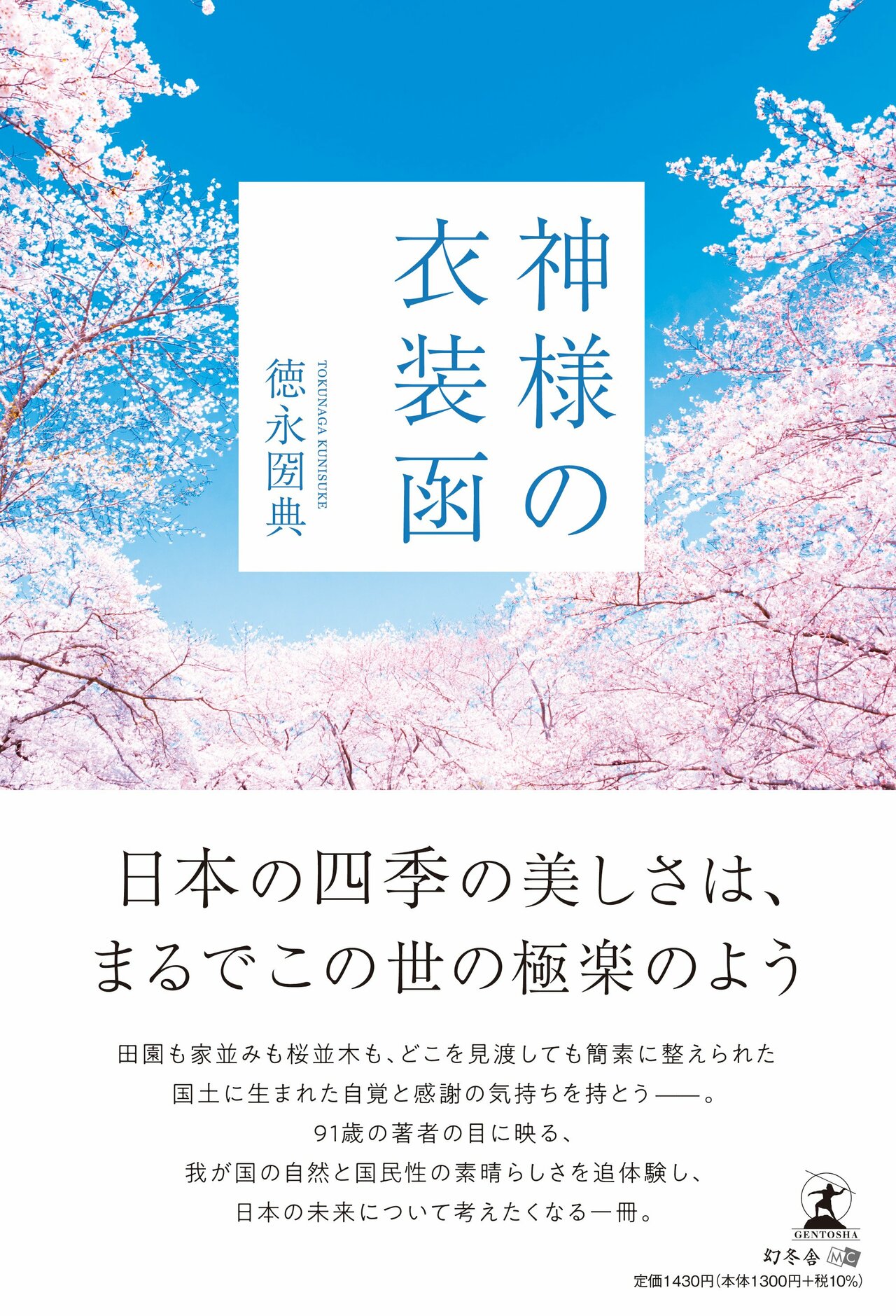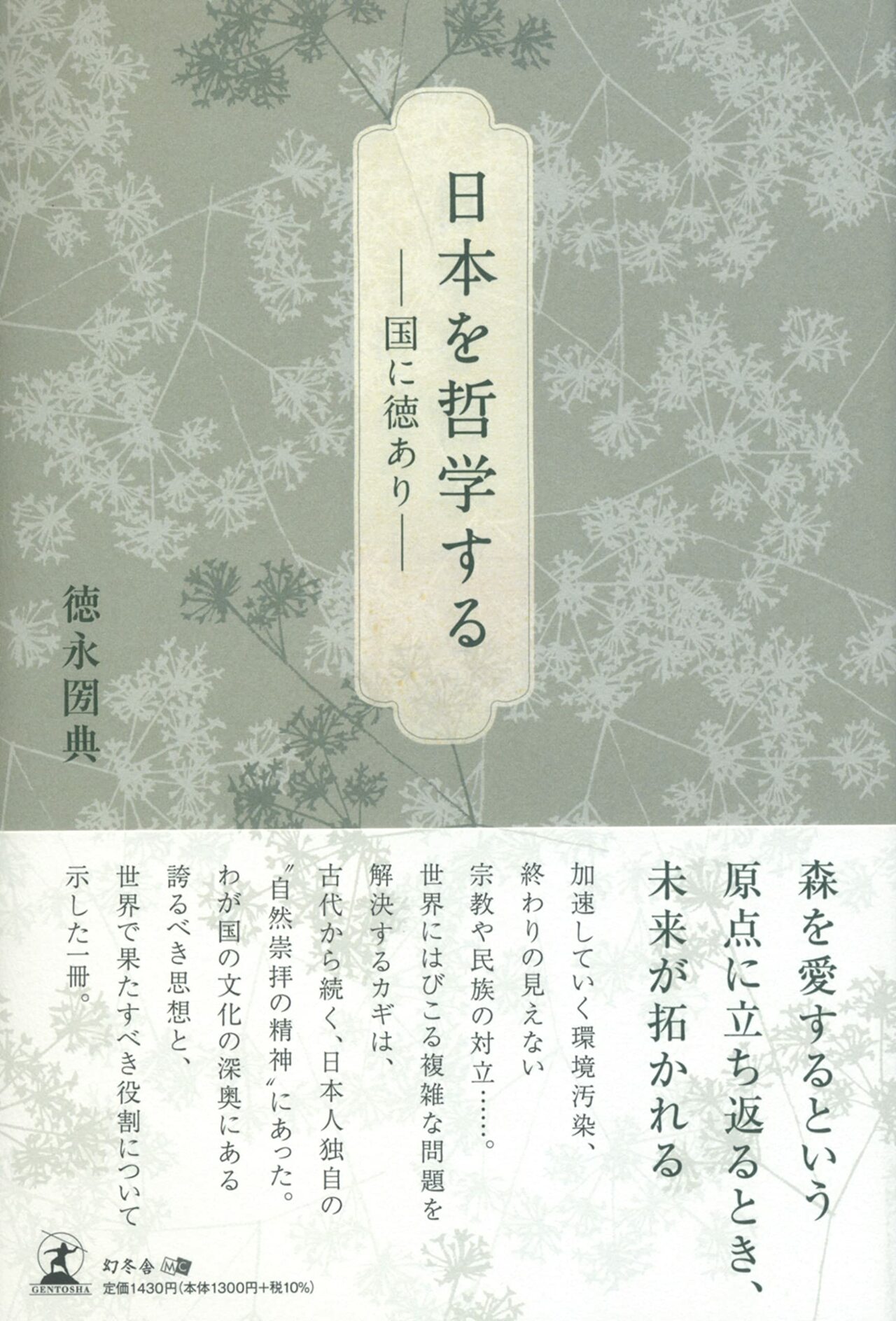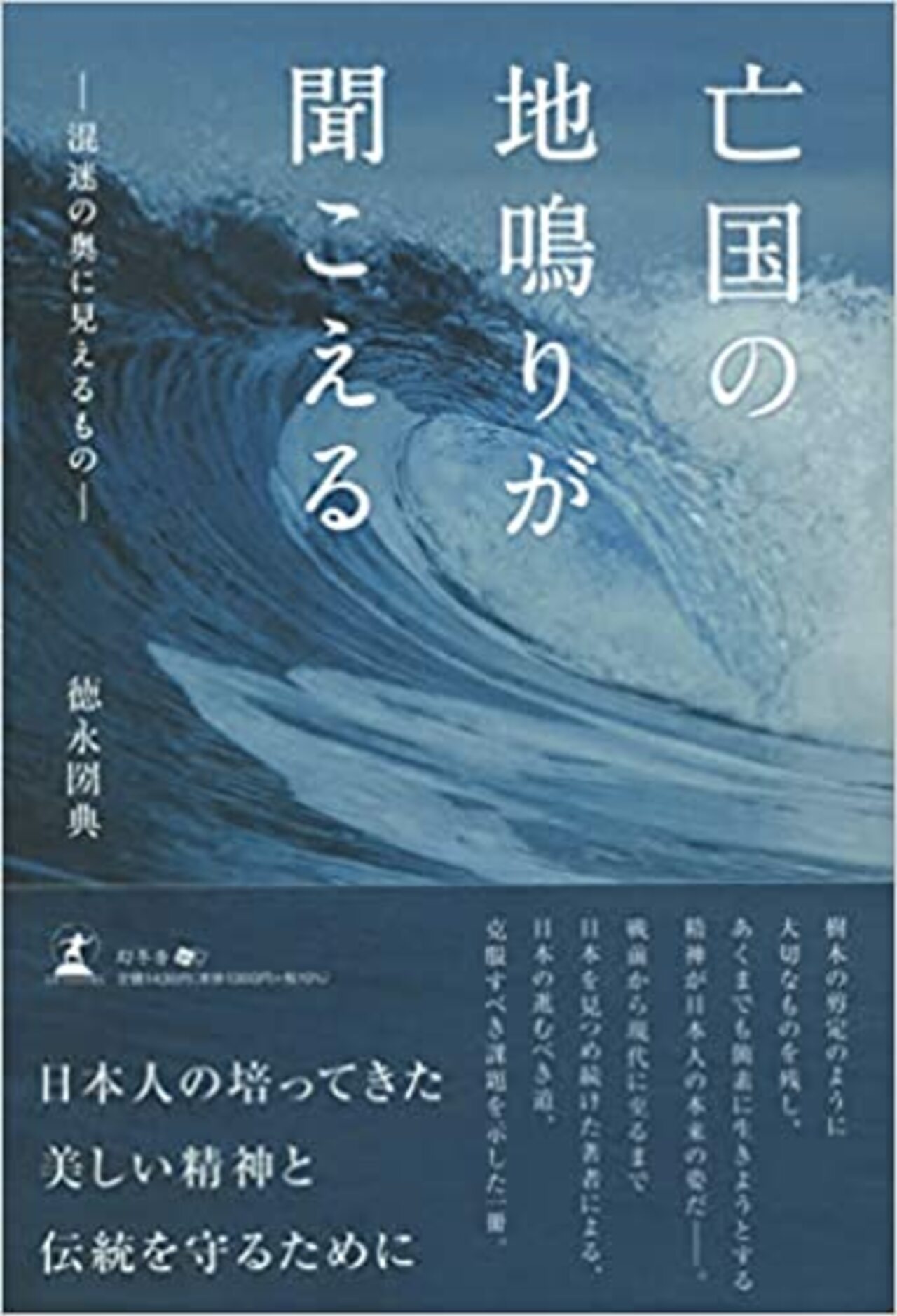【前回記事を読む】美しい日本の自然は、神様の衣装函のように思えてならない――時節ごとに色を変える山々。登山家の著者には神々の衣と映るのだ
一、美しい日本の山々
一 神様の衣装函
平成14年5月23日 日本海新聞 潮流
春はどこでも
長い冬を忍んで待ちに待った早春の3月、新緑を待ち兼ねて、山々に出かけるのももどかしいような木々、散々に歩き回るも新緑はまだまだと疲れて帰宅する。一風呂浴びて庭の樹木をよくよく見れば、新芽や蕾は満を持して膨らんでいるではないか。
春は枝頭にあって既に充分、これが早春の風景だ。それからつかの間だ。遠くに眺める森の梢に先ず、ぼやけたような薄茶色が霞む。それが次第に萌黄色となり、薄緑となり新芽がふいてくる。この頃の期待感は命の蘇りを待つ思いで私の最も好きな季節である。
その前に桜前線が日本国中をあっと言う間に北上する。染井吉野桜もいいが、私は楚々とした風情に見える山桜が針葉樹林の中に控えめに咲いている姿を好む。群生しないのもいい。
印象的には京都の保津峡であろうか、両岸のそそり立つ山々の斜面に垣間見える。桜といえば伊豆の河津桜は2月に咲いて温泉情緒を高めてくれる。箱根桜の花の小ぶりもいじらしい。
岐阜と富山県境に近い御母衣ダムの樹齢400年の荘川桜の物語は感動的である。岐阜の淡墨桜はなんとも言えない不思議な桜樹だ。
東北は角館の土手桜、弘前城の爛漫たる桜花には圧倒される。お城や武家屋敷の歴史美が格調を高めている。
京都は円山公園の枝垂桜は夜が豪華で華やかだ。その昔、用瀬の我が家の大裏にあった老枝垂桜は、離れの新建(しんだち)で祖父や両親が楽しんだが間違いなく庶民の衣装だ。倉吉は打吹公園で妖艶な美人桜の花吹雪を浴びた。
たおやかに 袖ひるがえす しだれ桜
忘れていた、奥琵琶湖は海津大崎の桜は一見に如かず。湖の船上からは更にいい。