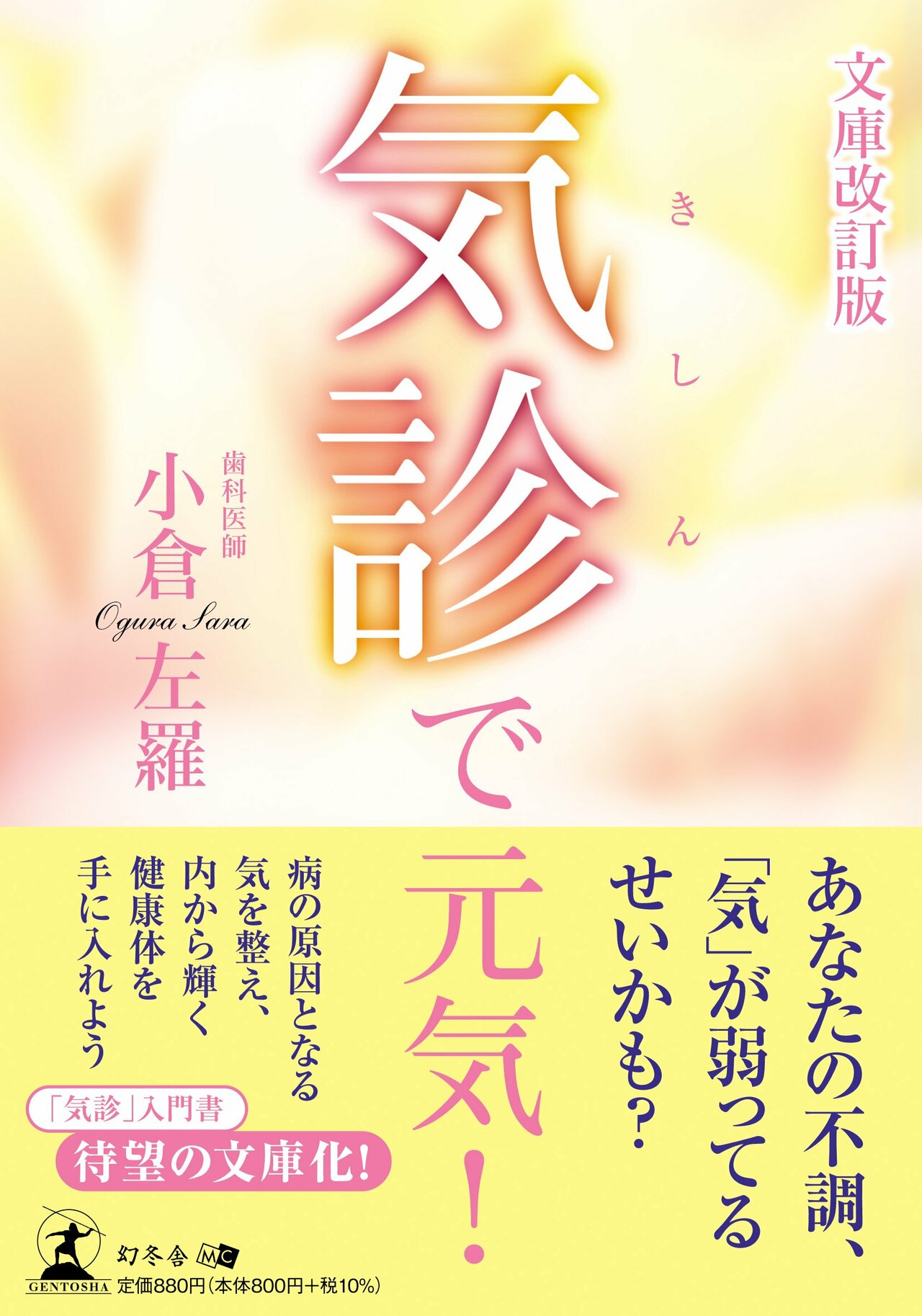さらに筋肉だけでなく、身体を取り巻く気にも変化が起こります。合わないものを持ちますと、周囲の気は、霞がかかったようになります。
周囲の気に手をかざして胸鎖乳突筋をつまむとカチカチに硬くなります。ですから身体に合わないものを知らずに食べ続けていると、気が乱れるだけでなく身体の調子をも崩してしまいます。
「気診」の修行を積みますと、その変化をとらえられるようになります。
次に身体の気の状態が悪いところを調べてみましょう。今度は「気の状態が悪いところに手をかざすと、胸鎖乳突筋は緊張する」と意識します。
そして身体の調子の悪い周辺に手をかざしますと、胸鎖乳突筋が緊張します。気の状態が悪いところとは、気の流れが悪いところです。
例えば、痛みのある箇所、冷えている箇所、筋肉が緊張しているところ、五臓六腑の気がダウンしているところなどです。
「気診」では自分の悪いところがわかりますし、他の人の悪いところもわかります。
例えば腰のあたりに手をかざして胸鎖乳突筋が緊張してきたら腰が悪い、膝に手をかざして胸鎖乳突筋が緊張すれば膝が悪いと判断します。
何でもないところに手をかざしても、胸鎖乳突筋は変化しません。
三、気診の修行
「気診」は、すぐにできる方もまれにいらっしゃいますが、たいていの方は最初、ほとんどわかりません。
特に胸鎖乳突筋が常に緊張している方は、なかなか緊張・弛緩の変化をとらえることができないようです。