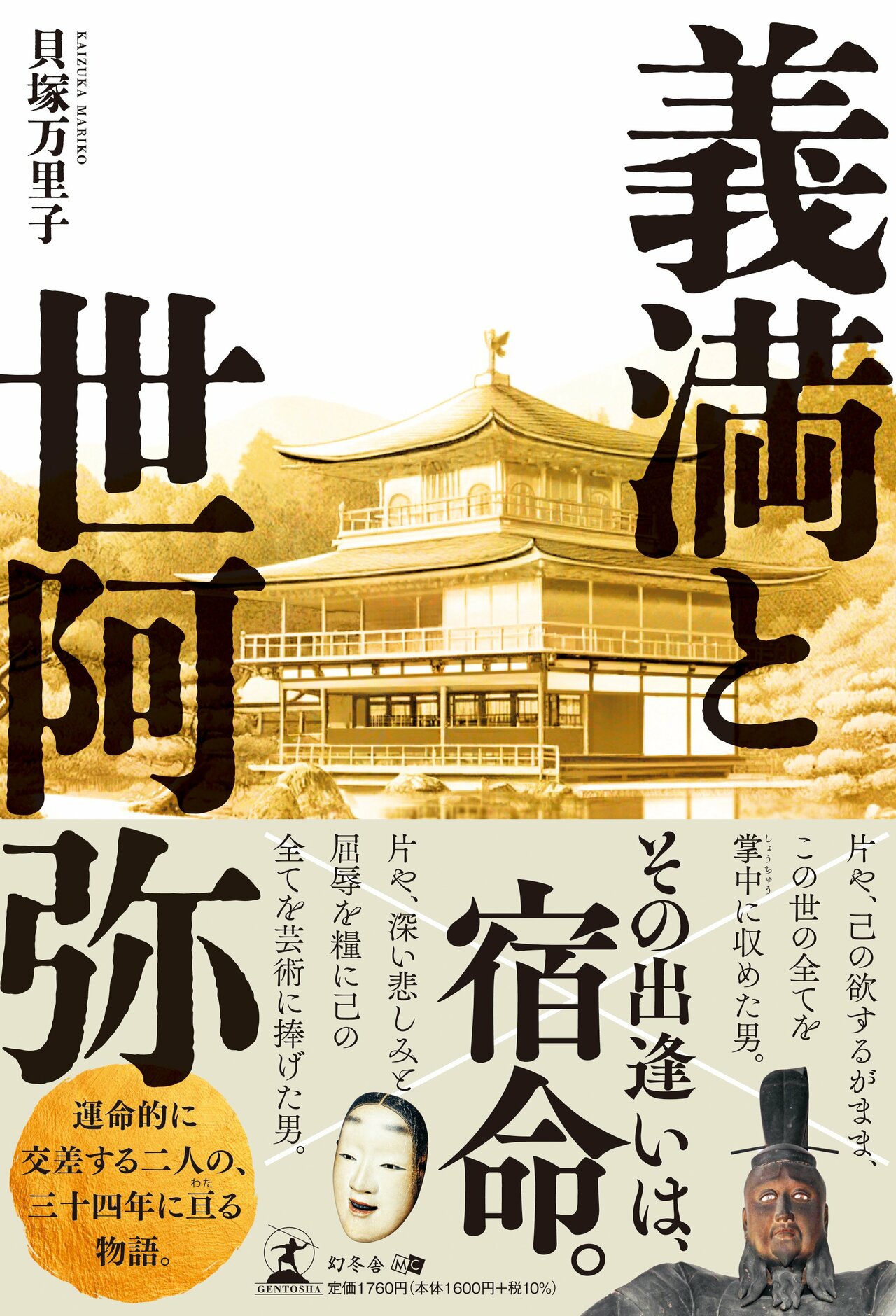連歌とは、平安時代末期に始まった、複数の詠み手が和歌を一つずつ詠み、繋げて行く遊びである。前の句と意味が繋がらない様に態(わざ)と変化を持たせ、和歌の意味を思いも寄らぬ方向にずらして行く、言葉遊びの様なものである。
それが貴族ばかりでなく広く庶民達の間でも流行し、鎌倉、室町時代には桜の木の下で凡ゆる階層の男女が集い、挙こぞって連歌を巻くという社会現象に迄発展していった。
貴族中の貴族である二条良基も、自宅の連歌会(れんがえ)に高僧や公家ばかりでなく、身分の低い連歌師を招待していた。この様に、平安時代には考えられ無かった身分階層を超えた交流が時代の風潮であり、この波に乗れない公家は衰微し、変化に聡さとい二条良基の様な者だけが生き残っていった。
一三七八年四月二十日、二条良基邸で催された連歌会に、京都を代表する知識人である公家、高僧に交じって、世阿弥が招待された。只一人元服前で髪が長かったので、垂髪(たれがみ)というあだ名で呼ばれた。連歌の最初の一句は招待客の中の長老が作る。その後順次句が付けられて行き、二条良基の番になった。
「いさをすつるはー すてぬのちの世ー」
自分の功績に慢心し過ぎると、次に生まれて来た時は功績の無い人となる、という、洒脱な二条良基らしからぬ、重い句である。本人は、敢えて偶にはこの様なもっともらしい句も面白いかと思ったのだが、次の番が世阿弥だったのに気が付いて、後悔した。もっと子供向けに易しい句を配慮すべきであった。
「なかなか含蓄深い句で御座いますな。しかし垂髪がこの後をどう繋げるか。いやはや、私の番で無くて本当に良かった」