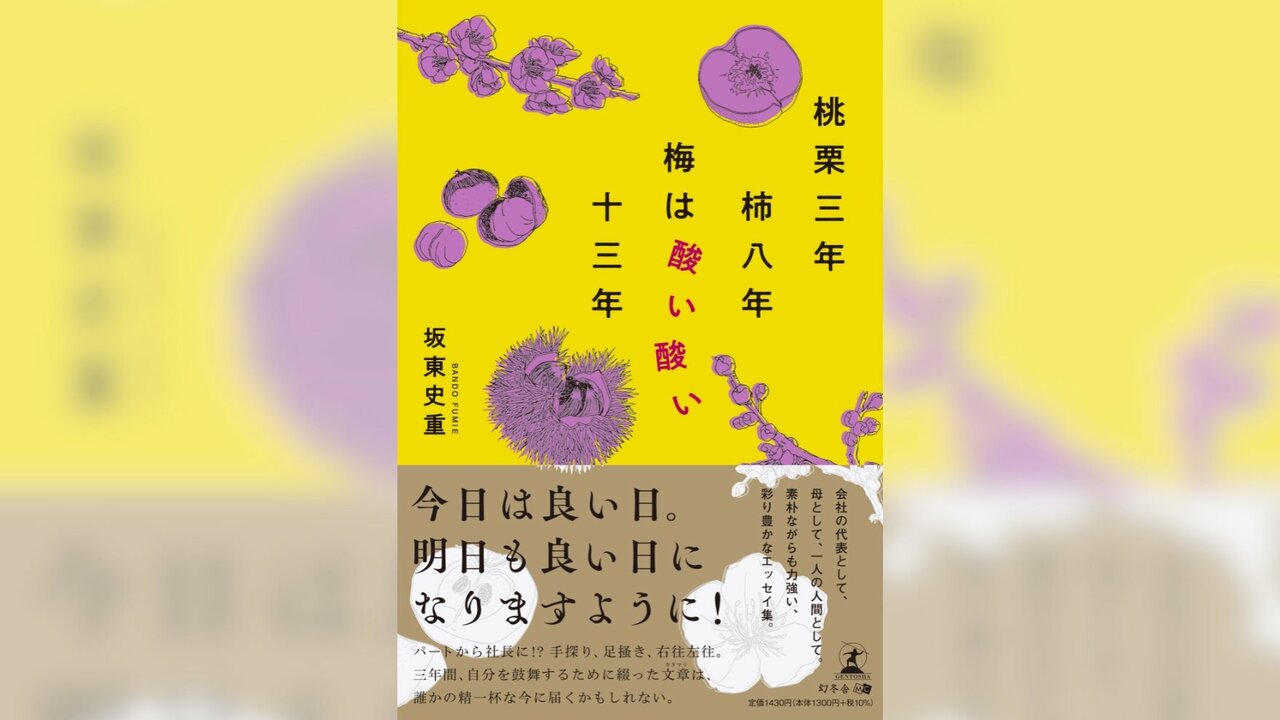【前回記事を読む】人々は自分の宇宙に潜り、質問への答えを見つけようとする。そこにある光を信じてほしい。その光を「自信」というのだ――
番外編1 1998年9月
水星人になりたい。なんなら木星人でもいい、みんなの記憶から消えてしまいたい。仕事は嫌いではない。家族も大切だ。でも、証明しろと言われたら証明できない。会社に行きたくない、家にも帰りたくない。昨日も、今日も、明日もきっと明後日も、私はだめ人間のままだ。いつもいつも自分が価値のないカタマリでしかない気がしている。
カタマリは主張するわけじゃないけれど、重石みたいにどっしりと沈んで、いつも存在を意識することを求めてくる。……こんなことを誰かに打ち明けても、きっと笑われるだけだ。
同情の目で見られて、いっときの気休めをもらうだけだ。そうしたら、なんてお礼を言えばいいんだろう。あれやこれやを抱え込んで、今日も私は重しのままだ。
「変わってるよね」と、顔のない誰かの声がする。悪気がないのは知っている。でもだからこそ飲み残しの乾いた澱みたいな汚い色が心に溜まる。いつまで続くんだろう。そろそろ限界みたいだ。
なんでもない顔の仮面を被っているのも、ここにまっすぐ立っているのも、なんだったらこのまま地球人でいることも。ここじゃないところに行きたい。全部放り出して逃げ出してしまいたい。
仕事は早いほうだと思う。なのに帰れない。保育園と学童のお迎えの時間が迫っている。でも、パートだからって中途半端には帰れない。
昼休みの談笑は気が重い。卑屈な気持ちで満杯になる。子育てがひと段落している先輩たちの生活は別世界。手間暇かけた夕食に、エステもどきの贅沢な入浴時間。就寝前には優雅で豊かな自分時間。私とは大違い。
散らかり放題で、毎日がやっとやっとの我が家のことなど、とても人様には語れない。人生そのものに×の烙印を押されているような気がしてくる。
「もう少し早くお迎えに来れませんか」。学童と、保育園の残り番の先生の顔が浮かぶ。今日はどちらを優先して先に向かおうか。先生方の残業は私のせいだ。
最近の子どもたちはいつもラストメンバー。「ほんとにごめん……」と言えば、「別に平気」と返してくれる。都合がいいけれど、救われた気分になる。「明日は早く迎えに来るから」と言えなくて、喉元ぎりぎりで押し止める。
守れない約束はしちゃいけない。穴埋めするみたいに、まるで機嫌を取るみたいに、絵本を読む約束をする。また夜が遅くなる。
「良い母親でいたい」と思う資格なんてない。かと言って「仕事に打ち込む母親」とも言い切れない。知っている。いつだって私は中途半端だ。
「約束は守れ、おまえはいつも口先だけだ、家も子どもも疎かにしてなにが仕事だ」。今日も夫の苦言シャワーが待っている。いい加減耳にタコだ。毎日続く苦言シャワーで、耳には小ぶりなタコがたくさんぶら下がる。