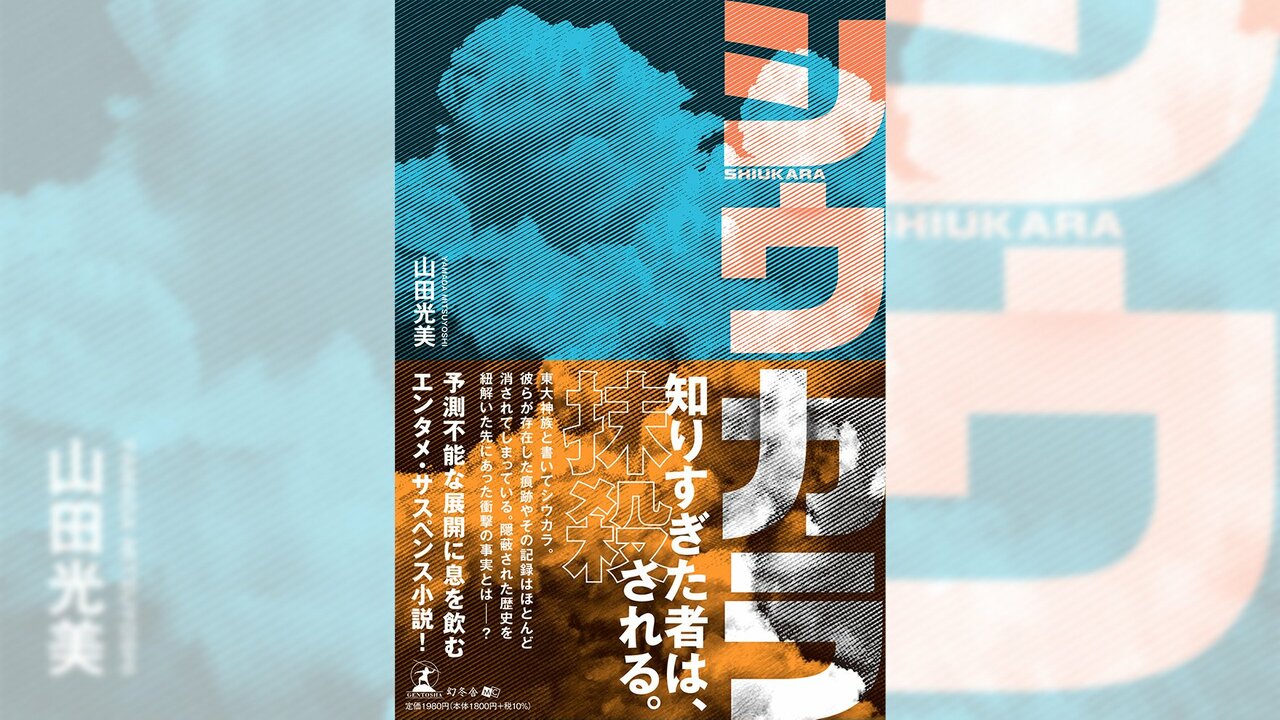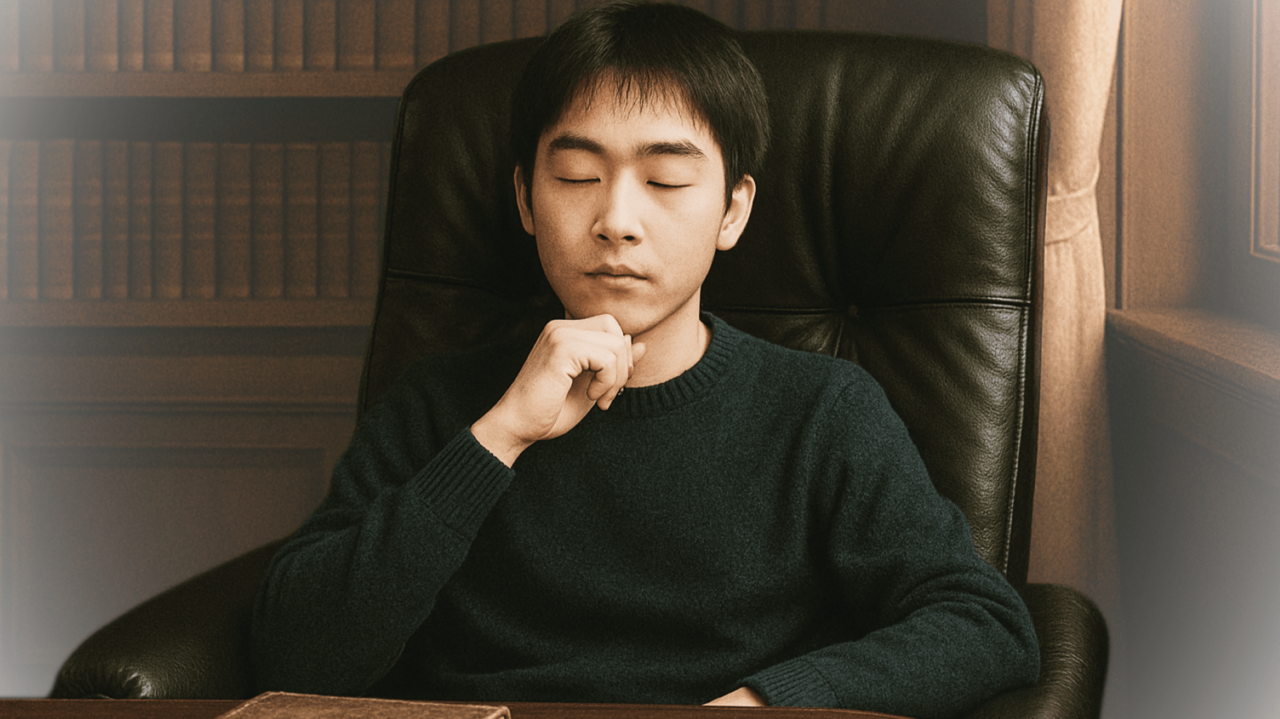【前回の記事を読む】死んだ父を見つけたのは見つけたのは家政婦だった。「自殺」と聞いたが現場はあまりにも不自然で......
第一章
光一はもう一度書斎を見渡した。いったい何冊あるんだろう。1万か、2万か……。いやそんな数ではない。そう思いながら眺めていると、書棚の一角がふしぎと気になり、吸い寄せられるように近づいていった。ちょうど目の高さのあたり、きっと頻繁に取り出せるように収められたのだろう。その中から題名に見覚えのある一冊の本を取り出した。
『契丹古伝』。光一も数年前に読破していて、なじみのあるタイトルだった。厚さが7、8センチはあるだろうか。簡素な装丁の復刻版で、光一の自宅の書棚にも同じものが収められている。
ページをパラパラと繰ってみると、おびただしい数の付箋がつけられていた。きっと何度も読み返したのだろう。ページのヘリはすり減り、付箋にはそれぞれに短い書き込みが見受けられた。
大正15年に初版刊行のこの書籍は、正式には「日韓正宗遡源」(にっかんしょうしゅうそげん)といい、浜名寛祐(はまなひろすけ)という軍人が従軍先の奉天郊外のラマ教寺院の僧侶から奇妙な巻物を見せられたところから始まる。
現地でこれを書写した浜名寛祐はその後帰国し、十年の歳月をかけて研究。漢語解読の才に長けていた浜名は、日韓古語の研究からその解読に成功し、ついに『契丹古伝』(日韓正宗遡源)を発表した。
『契丹古伝』の原本は、10世紀に東丹国(契丹の分国)の耶律羽之(やりつうし)によって撰録された漢文体の歴史書だ。
この本にはじつに驚くべき事柄が記されている。明治から大正にかけての旧かなづかい、しかも漢文混じりの文章は、いかに読書家の光一といえどもかなり難解な文献だった。そこに書かれていた内容は、なんと我々日本人の祖先にあたるある民族の歴史だった。
光一は、本の世界からふたたび現実に戻った。もう一度書棚に目を移すと、一般に「古史古伝」として括られている文献がずらりと並んでいる。
「古史古伝」とは、日本の古代史の公式資料とされている『古事記』と『日本書紀』の内容とは著しく異なる歴史を伝える文献の総称だ。こうした「古史古伝」はいまのところ、アカデミズムの主流からは偽書とみなされている。
『竹内文書』(たけのうちもんじょ)『宮下文書 (みやしたもんじょ)』『九鬼文書 (くかみもんじょ)』『上記(うえつふみ)』『三笠記 (みかさふみ)』『秀真伝(ほつまつたえ)』『カタカムナ文献』『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』『桓壇古記(かんだんこき)』などの原書、さらにはこうした文献にかかわる関連書がずらりと並んでいた。
興味の対象が同じじゃないか、と光一は思った。ここにこもって読み漁りたいものだ、と思った。会って話してみたかったな、と書斎の主の死を悔やんだ。