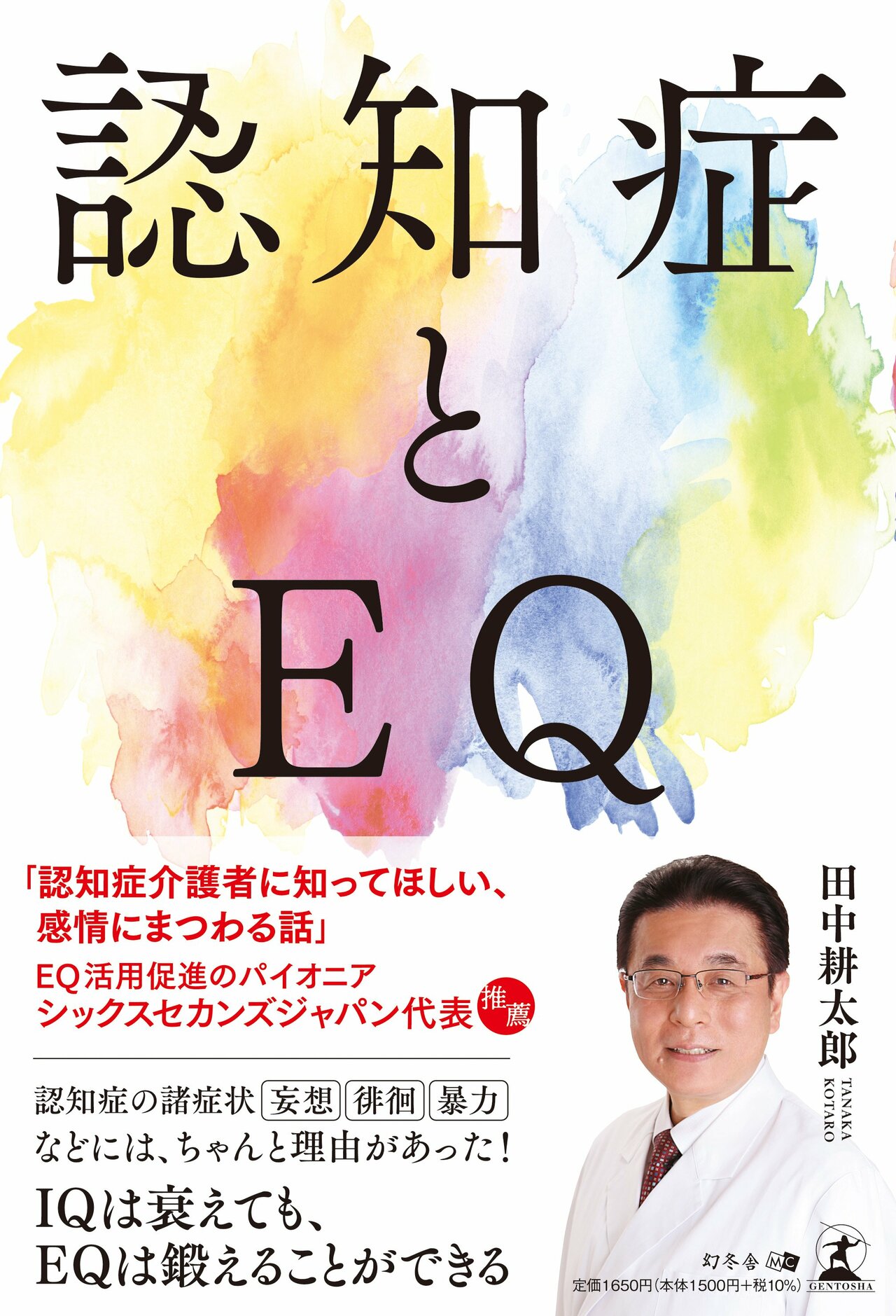そうなると話は食い違い、妻が私の話の腰を折ったり、言葉尻をとらえたりして、話がとんでもない方向に進んでいき、空中分解してしまいます。
そんなことを繰り返すうちに、実は妻に相談をされる場合は、すでに答えは決まっていて、話したいだけ話した後に「うん、そうだね」とか「本当にそうだ」とか、そんな言葉を聞きたかっただけなのではないかと気づいたのです。
聞き上手な方は、その同調欲求の存在をよく知っていて、無駄な争いが生じないように、相談主がすっきりするような態度で話を聞くのでしょう。相談主は、そんな方に愚痴を聞いてもらったり相談をしたりするといつもすっきりするのです。
つまり会話に同調できるというのは、高度な非認知能力だということです。会話で話されるのは相談事ばかりではありません。ほとんど、は言いすぎでしょうが、「愚痴」も多いのではないでしょうか?
「聞いて聞いて、〇〇さんにこんなこと言われたのよ」なんてセリフ、一度は言ってみたことがあるのでは? 体験したびっくり話やおもしろ話、芸能人の話題、おしゃべりの内容を思い返してみてください、実はこのような会話はただ単に情報を伝達しているだけではありません。
「嫉妬」「驚き」「喜び」「悲しみ」などの感情を伝えていることにお気づきになられると思います。つまり「情報」ではなく、自分が感じた「感情」に同調してほしい、共感してほしいと心のどこかで思っているということです。
気持ちよく話しているのに、話し相手が話の途中で割って入ってきて、(自分にとって)見当違いの解説や説教を始めたらどう感じますか? ものすごくもやもやしますよね。
逆にこちらの感情に「そうだ!」と相槌を打ってもらえれば、ものすごく気持ちがすっきりします。ですから感情の同調ができる能力、つまり「共感」する能力はほとんどの人の欲求を満たすことができる能力なのです。
このような共感できる能力というのは、いつから持っているものなのでしょうか? 小児期でしょうか? 幼児期でしょうか?
【イチオシ記事】お互いパートナーがいたけれど出会ってビビッと来ちゃった2人。そして妊娠発覚!