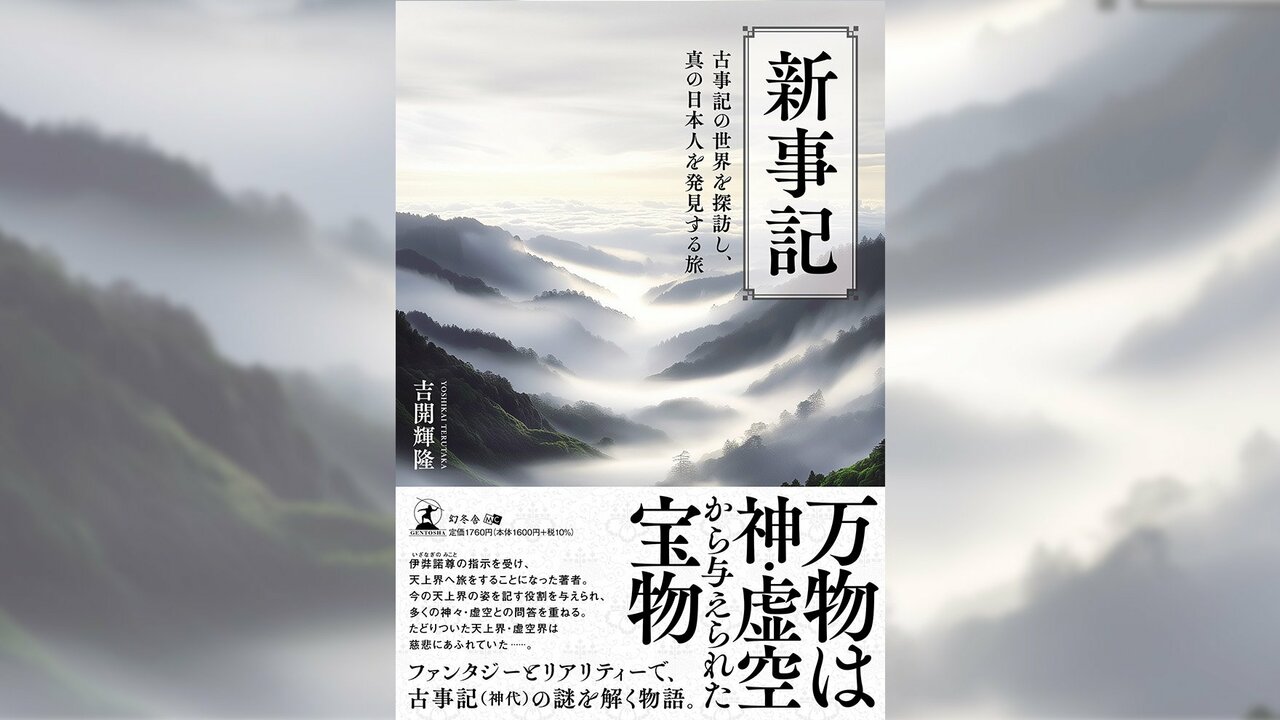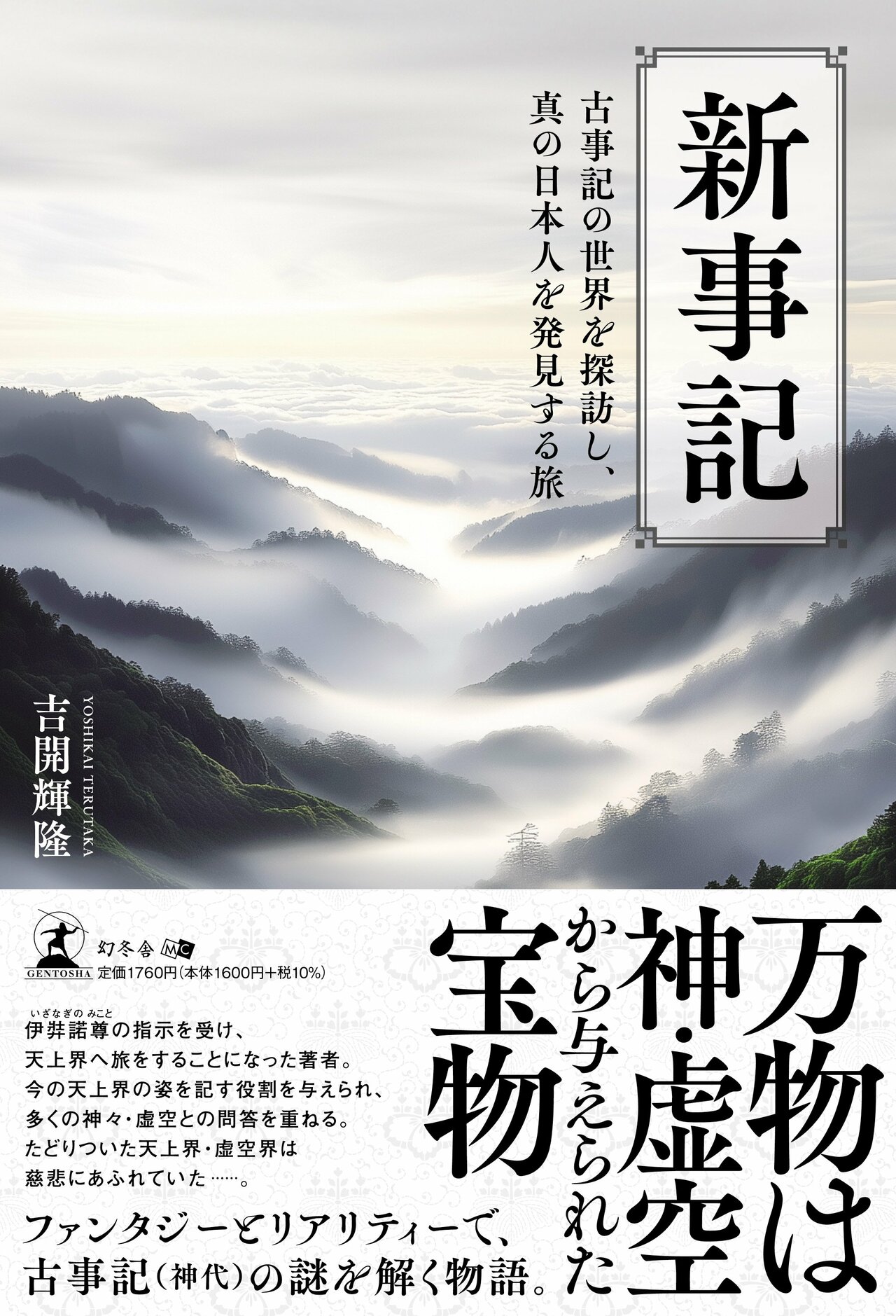まえがき
日本人に親しまれている年号は、現在では、ご承知のとおり、令和(れいわ)である。
この令和という年号は、シナ文化を出典とする、これまでの例から外れて、日本文化を出典としている。すなわち、万葉集巻五(まんようしゅうまきご)「梅花の歌三十二首、併せて序」にある一文からである。
その一文とは、漢文調では「時(とき)に、春の初(しょしゅん)令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風和 (かぜやわ)らぎ……」、
これを和文読みにすると、「時(とき)に、初春(しょしゅん)の令(よ)い月(つき)であり、空気(くうき)は美しく、風は和(なご)やかで……」である。
─作者は、大伴旅人(おおとものたびと)とも、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)ともいわれる。ところで、日本の文化は、自国の固有の文化(縄文)をもちながらも、他国に学び、
その他国を、古風ないい方であるが、自家薬籠中(じかやくろうちゅう)のもの(共存)にして、自国の固有の文化(日本の文化)を高めてきたように思われる。
─さきには、東洋(インド・シナ文化)に学び、いまでは、西洋文化(欧米)を学んでいる。
さて、ここで、令和の年号を取り上げたのは、昭和・平成の時代(雌伏)を終え、いよいよ、自国の固有の文化を高める時代(雄飛)の、到来する兆しが、この年号にみえるからである。
そのためには、まずは、自国の固有の文化を確かめておく必要がある。年号は、万葉集によっているが、自国の固有の文化は、古事記上巻(神代)によるべきではなかろうか。
ここでいう古事記(神代)とは、天地の始まりから国生み(日本国)、そして、天孫(天皇の祖先)降臨前後の時代までをさしている。
令和7年からは、自国の固有の文化を深め、そして、さらに高められた日本の文化が芽吹く時代を迎えるにちがいない。
─本書は、新しい波の、先導役になれば……、との思いで、しるしたものである。