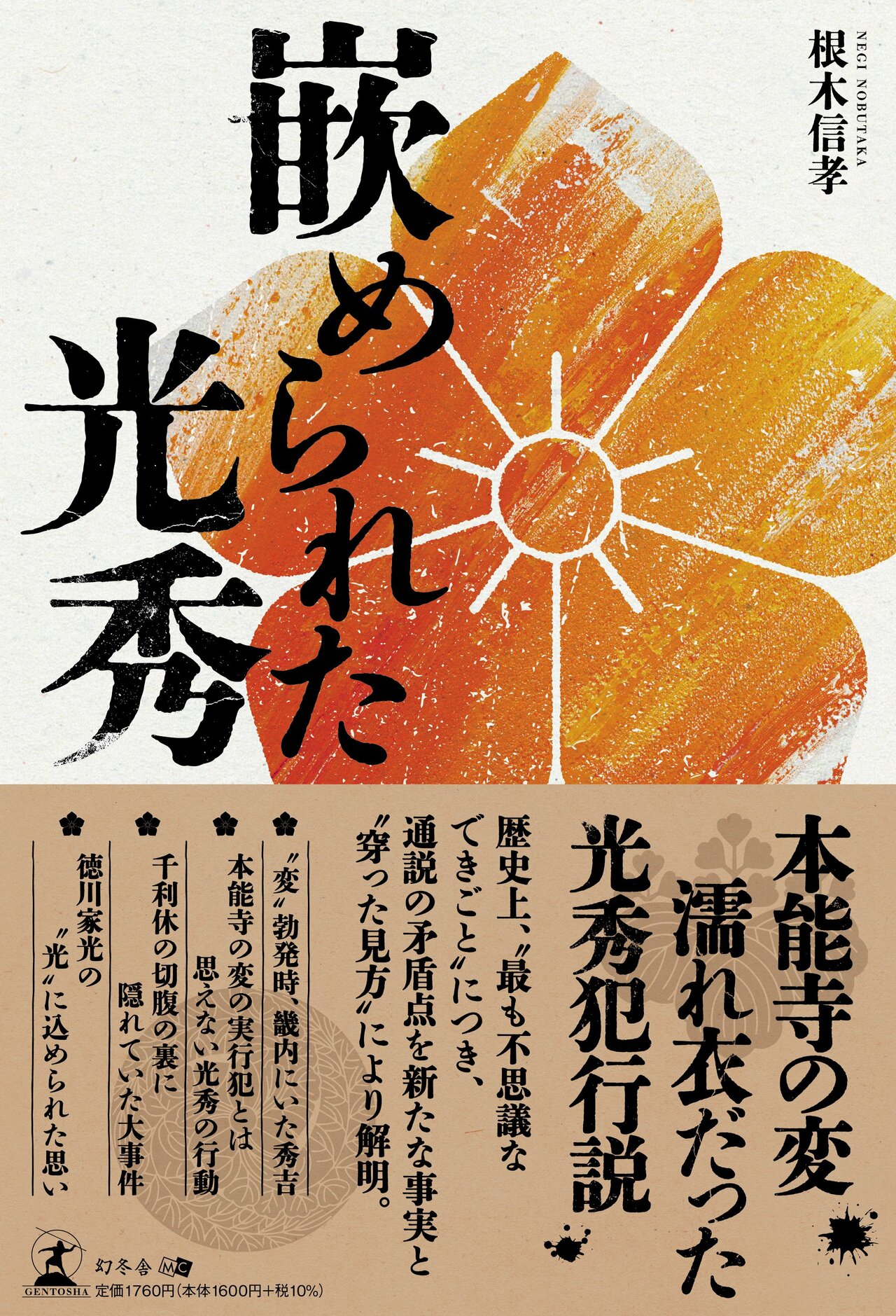元亀4年(1573年)4月、武田信玄は野田城包囲中に病※1が悪化し、甲斐に引き返したが、引き返す途上で死去した。
将軍義昭と信長の確執は解消されず、同年7月、義昭は再度挙兵したが、信長に敗れ、備後の鞆(とも)に逃亡。
天正3年(1575年)5月、武田勝頼は武田氏より離反し徳川家の家臣となった奥平貞昌を討つため、貞昌の居城である長篠城に攻め寄せた。織田・徳川連合軍は奥平氏の救援に駆けつけ、武田勢を破った(長篠の戦い)。
天正4年(1576年)石山本願寺が挙兵したため、これと対峙するが、この頃、上杉謙信が石山本願寺と和睦し、信長との対立を明らかにした。
この石山本願寺攻めは織田軍が本願寺の物資を断つ兵糧戦だったが、この最中に信長の重臣の荒木村重の家臣が本願寺側と内通して本願寺に物資を搬入する事件が勃発した。荒木村重は監督不行き届きで自身も罰せられると考え、謀反を選んだ。村重軍は粘った末に敗れ、村重は逃亡、家臣は打ち首となった。なお、村重は信長の死後、道薫(どうくん)と名乗り、茶人として生きた。
天正10年(1582年)、長篠の戦いで敗れた武田勝頼は上杉と和睦したが、織田軍がこれに侵攻を開始。3月に勝頼が自刃して終結した。
この頃、織田家重臣の明智光秀は丹波を攻略、柴田勝家は越中まで侵攻し、越後の上杉と対峙、羽柴秀吉は毛利側の諸城を攻略、四国は長宗我部元親が勢力を拡大しており、一旦は信長から「四国は切り取り次第」と言われていたが、13代将軍足利義輝を殺害したばかりか、勝手に14代将軍を擁立しようとし、信長に敗れて阿波に逃げていた三好が信長に降伏すると土佐国と阿波南半国のみと言われて対立した。
しかし、本能寺の変の直前に信長に従う意向を示したが、変の翌日には神戸信孝※2がまさに遠征するところだった。
※1 武田信玄は通説では病で死んだと伝えられているが、信玄が最後に攻めた野田城には信玄鉄砲 と呼ばれる、信玄を撃ったと伝えられる鉄砲が残っている。
※2 神戸信孝は織田信長の三男
【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...