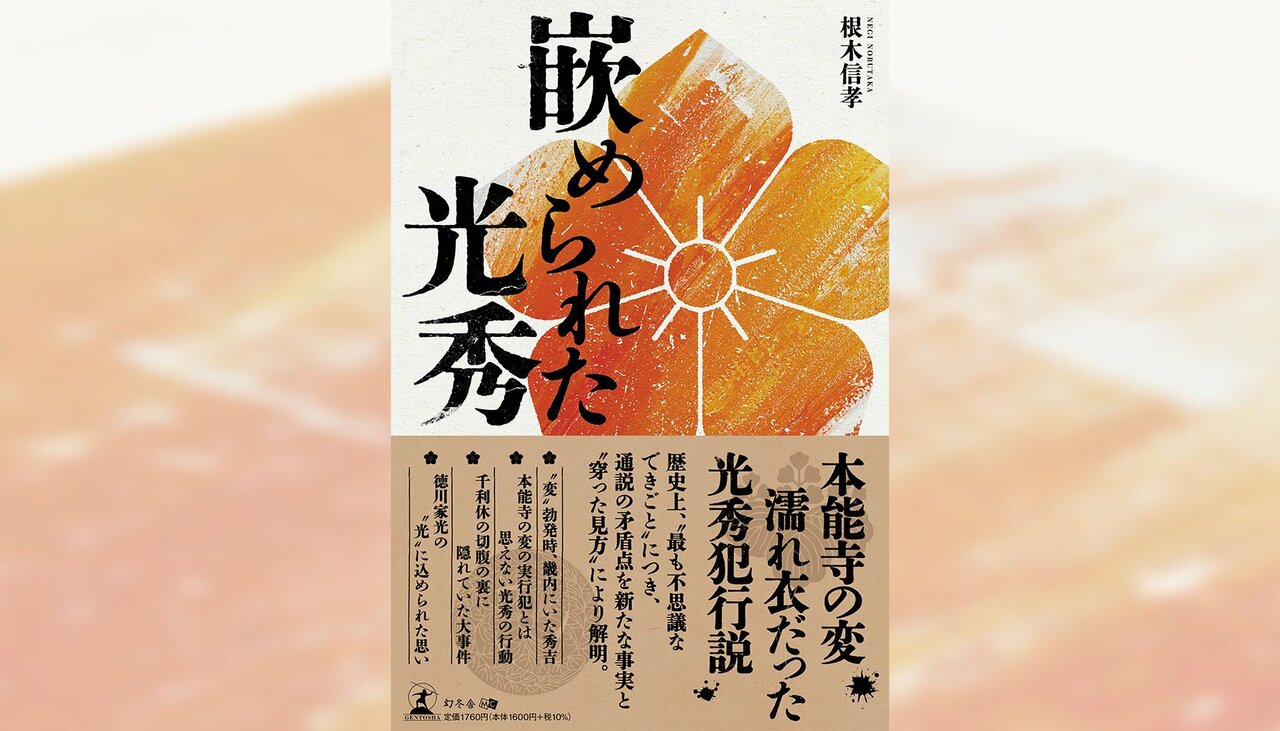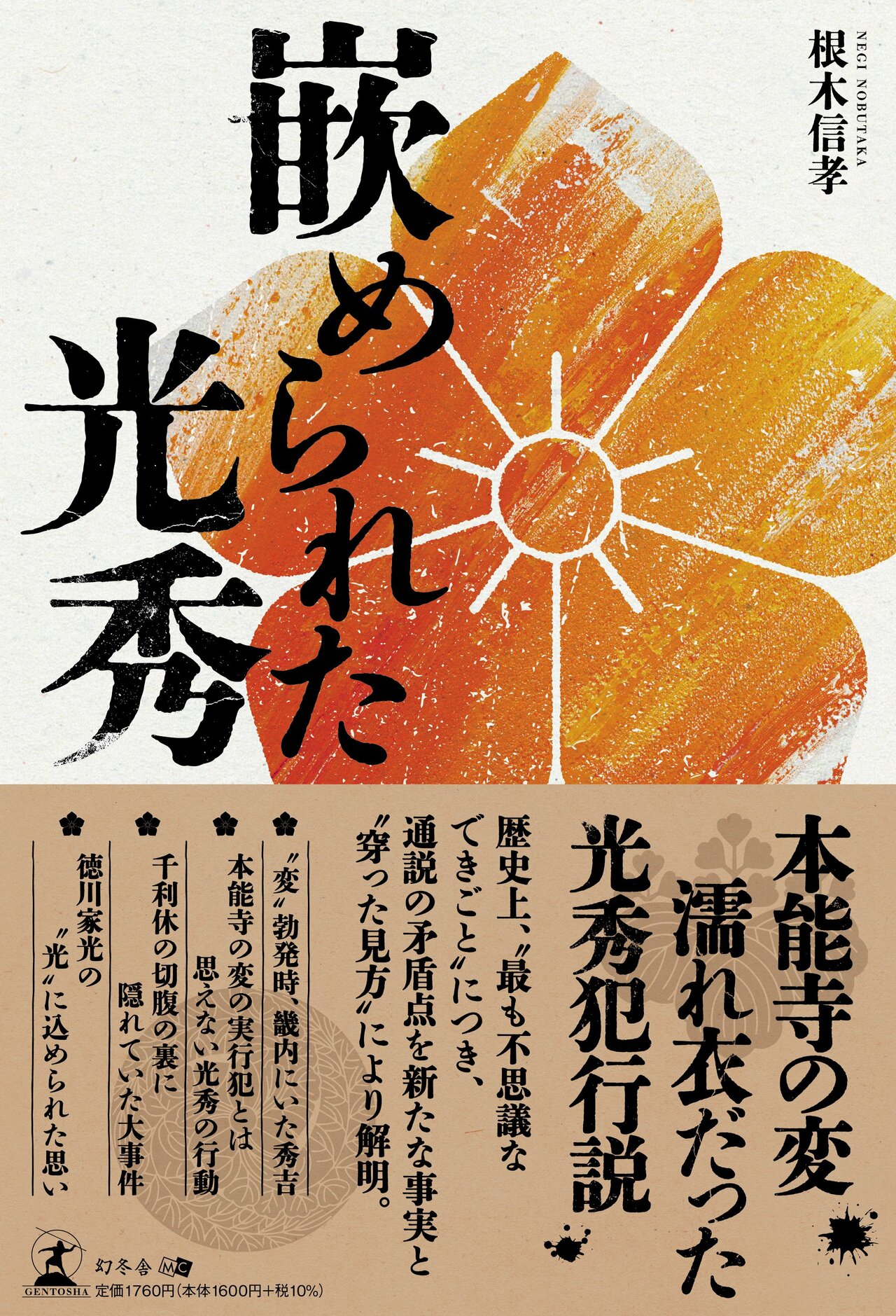【前回の記事を読む】休憩中の今川義元を急襲し撃破した桶狭間の戦い――今川2万5千に対し、織田は2千5百だったという説も
第一部
1 信長の足取り
1566年に木下藤吉郎が墨俣(すのまた)に一夜にして砦を建て、織田勢はこれを足がかりにして斎藤氏の稲葉山城を攻略した。なお、この時、秀吉は砦に使う材木を長良川に浮かべて運んだが、丸太のまま運んだのではなく、長良川の上流で接合部をできるだけ加工して一旦仮組みし、それを最小限解体して筏(いかだ)を組んで運んだという説がある。
その頃、京では永禄8年(1565年)に、「永禄の変」で第13代将軍の足利義輝が三好氏に殺害され、三好氏に推された第11代将軍の足利義澄の次男足利義維の長男として生まれた足利義栄が摂津国富田で第14代将軍になるが、織田勢から逃げる中、8か月後に病死した。
一方、一旦出家していた足利義輝の弟の義昭が還俗(げんぞく)して上京し、足利義栄と対立。義栄の死後、永禄11年(1568年)9月7日、信長に推されて第15代将軍に就任する。
義昭は京で将軍として執務するが、信長から「諸大名に勝手に書状を送ってはならない」など、諸々の制約を受け、次第に信長との間に溝ができ、反信長網の構築を画策する。
永禄11年(1568年)信長の妹のお市の方(かた)が近江の浅井長政に嫁ぎ、信長と浅井長政は義兄弟になる。信長は諸大名に上洛を命じるが、越前の朝倉義景が無視したため、元亀元年(1570年)4月、信長は朝倉氏の越前へ遠征を行う。
しかし、義兄弟である近江の浅井長政は朝倉家との繋がりが長く、朝倉方につき、信長を背後から挟み撃ちにしようと出陣した。信長は秀吉に殿(しんがり)を命じ、命からがら京に逃げ帰った。なお、この時、秀吉とともに徳川家康も殿を務めた。
同年6月、織田・徳川連合軍対浅井・朝倉連合軍は姉川で戦い、織田・徳川連合軍が勝利した。
元亀2年(1571年)9月、信長は比叡山延暦寺を焼き討ちにする。
元亀2年(1571年)末、武田信玄は後北条との同盟を回復させると、徳川領への侵攻を開始する。
元亀4年(1573年)に入ると、武田軍は遠江国から三河国に侵攻し、これを見た足利義昭は越前の朝倉義景の協力を見込んで信長との決別を決意したが、義景が上洛しないため、義昭は信長に攻められ、正親町(おおぎまち)天皇に調停を願い、和睦した。