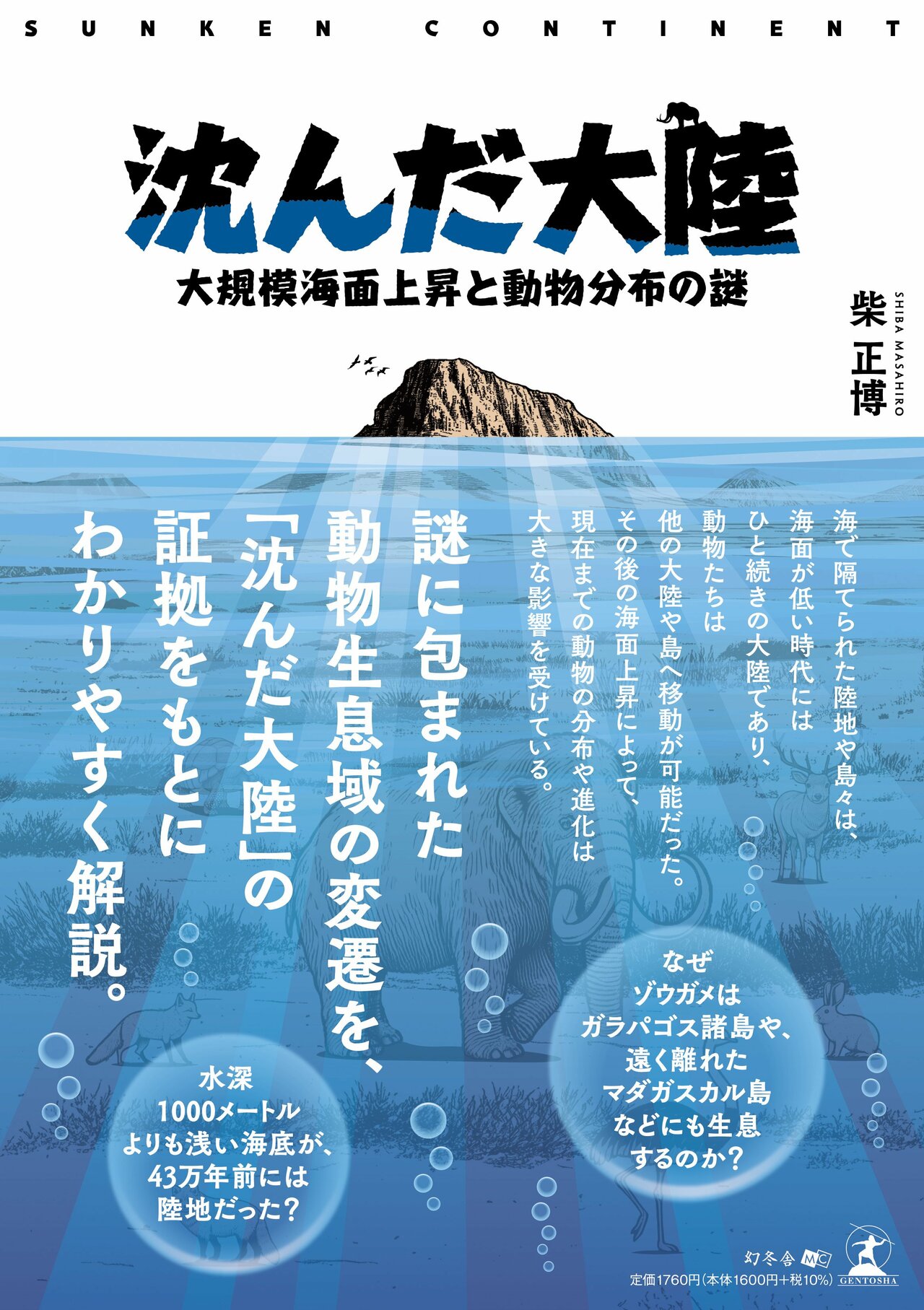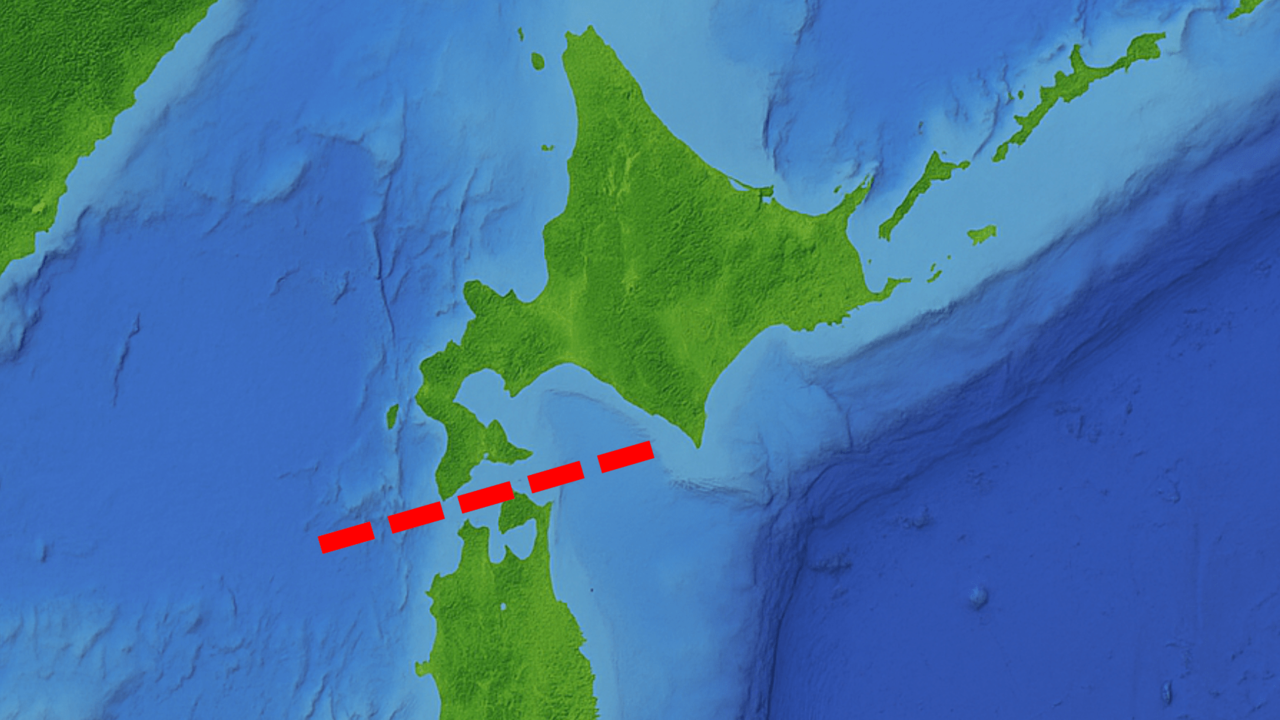生物地理学の進展については、二〇世紀初めまで、生物の分布、とくに陸生動物の分布は大陸と大陸、または島々をつなぐ陸橋によって説明されていました。
しかし、その後に海底の地形が明確になったことにより、海底が相当に深いことから陸橋説が否定され、プレート・テクトニクス説による「大陸移動」分断説と、「稀有な偶然による」海洋分散説が一般化し、現在では分断説で説明できないところを動物の遊泳や筏に乗った漂流などによる海洋分散説で説明する風潮になっています。
一方最近では、進化系統学の分野で、ある生物で共通している派生形質に注目して系統を考える分岐分類学が発展し、それにつづいてとくに二〇〇〇年代からは遺伝子解析による生物の系統分岐の順序と産出化石の年代から、各系統の分岐年代の推定が盛んに行われています。
それにより、生物地理学または生物進化学はこれまでの憶測をする科学から、ようやく推測する科学になってきました。しかし、生物地理学では、単にプレート・テクトニクス説による大陸移動や、海を漂流して渡ったという海洋分散説で、生物、とくに陸生動物の分布を安易に説明している傾向があります。
本書で私は、ジュラ紀末期以降に海面が一二キロメートル上昇したことを述べています。現在の深海底の大部分は水深五〇〇〇~六〇〇〇メートルなので、それにより現在の深海底の一部がかつては陸地だった可能性が出てきました。
この考えは、深海掘削(くっさく)により明らかになった浅海を示す岩石、または陸上で浸食された証拠の存在などと、二〇世紀の石油地質学者が明らかにした地層形成メカニズムにより、ジュラ紀末期以降の地層の形成には相対的沈降量が一二キロメートルにおよぶことからの、私の提案です。
地球の過去の歴史は地層の記録として残されています。この地層がどのように形成されてきたかということが、地球の歴史を解き明かすための根本問題であると、私は考えます。すなわち、私は地層を形成させた地殻の相対的沈降量を海面上昇量としてとらえて、それを白亜紀以降の生物地理学に適用した作業仮説をつくり、本書でそれをみなさんに提案いたします。
【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った
【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…
【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。