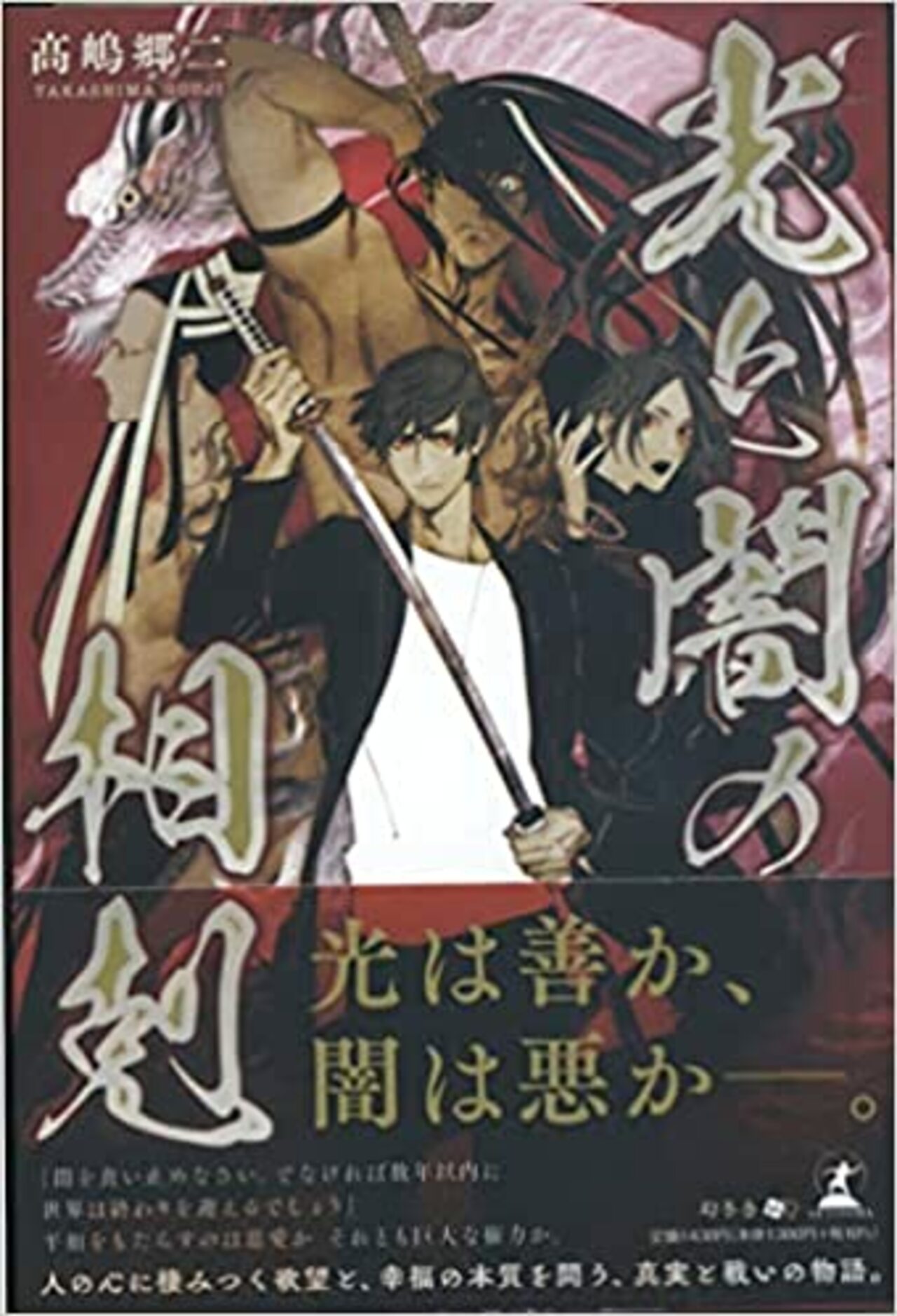エボシや毘沙門天の言葉を思い出し、かけるのことが気になった英良は自転車で病院まで見舞いに行った。院内は相変わらず消毒剤と薬品の交じり合った独特な臭いで充満している。時刻は午後二時を回っていた。待合室は閑散として窓口は一か所しか開いていない。何人かの看護師がバインダーを持って待合室を横切って行く。
受付まで行くと午後だったため閉まっていたので新患受付で用件を告げた。対応してくれた女性職員は二十代前半の若い職員で名前を渋澤さんといい、小柄で美人なほうで、茶髪を後ろで束ね化粧は薄くよく声の通る職員だった。その職員は事務所の奥の方へ行き、二、三分で戻ってきて英良に言った。
「入院病棟の五〇一号室の松本かけるさんでしたね?」
「そうです。会えますか?」
「松本さんはお亡くなりになりました」と渋澤さんが答えた。
「えっ?」英良は思わず絶句した。かけるは死んだ。分かりましたと一言いい、渋澤さんはそそくさと奥の方へ行ってしまった。
英良は病院を後にして帰るしかなかった。英良は暫く呆然自失として黙って振り返り後ろを見ていた。何も考えられず何も浮かばず思考が凍りついたように身体全体が固まったようだ。そのような状態が長く続いた。信号機から流れる青のシグナルに変わった音楽が流れ、気を取り直し自転車を押し歩を進めた。
すれ違う人達は赤の他人のことには興味を示すはずもない。人はそれぞれの運命の元時間を過ごしていく。英良に何が起きてもそれは巨大な現実の泡の中に吸い込まれ無数に起きた出来事の中のたった一つのものとして記憶されるか無意味なものとして忘れ去られるかだ。
英良は気持ちを落ち着けた。かけるの笑顔と今まで交わした言葉を一つ一つ思い出した。かけるとの出会いは俺の人生の中で一体何だったのだろう? 俺はかけるに何をしてあげられたのか? 俺の存在は何だったのか? 一縷の悔恨に自問自答して帰途についた。
【前回記事を読む】「お兄ちゃん。たすけて。毎日血が出るの。すごく頭も痛いよ。ぼくおかしいのかな?」あの子の夢、嫌な予感…もう亡くなるのか?
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。