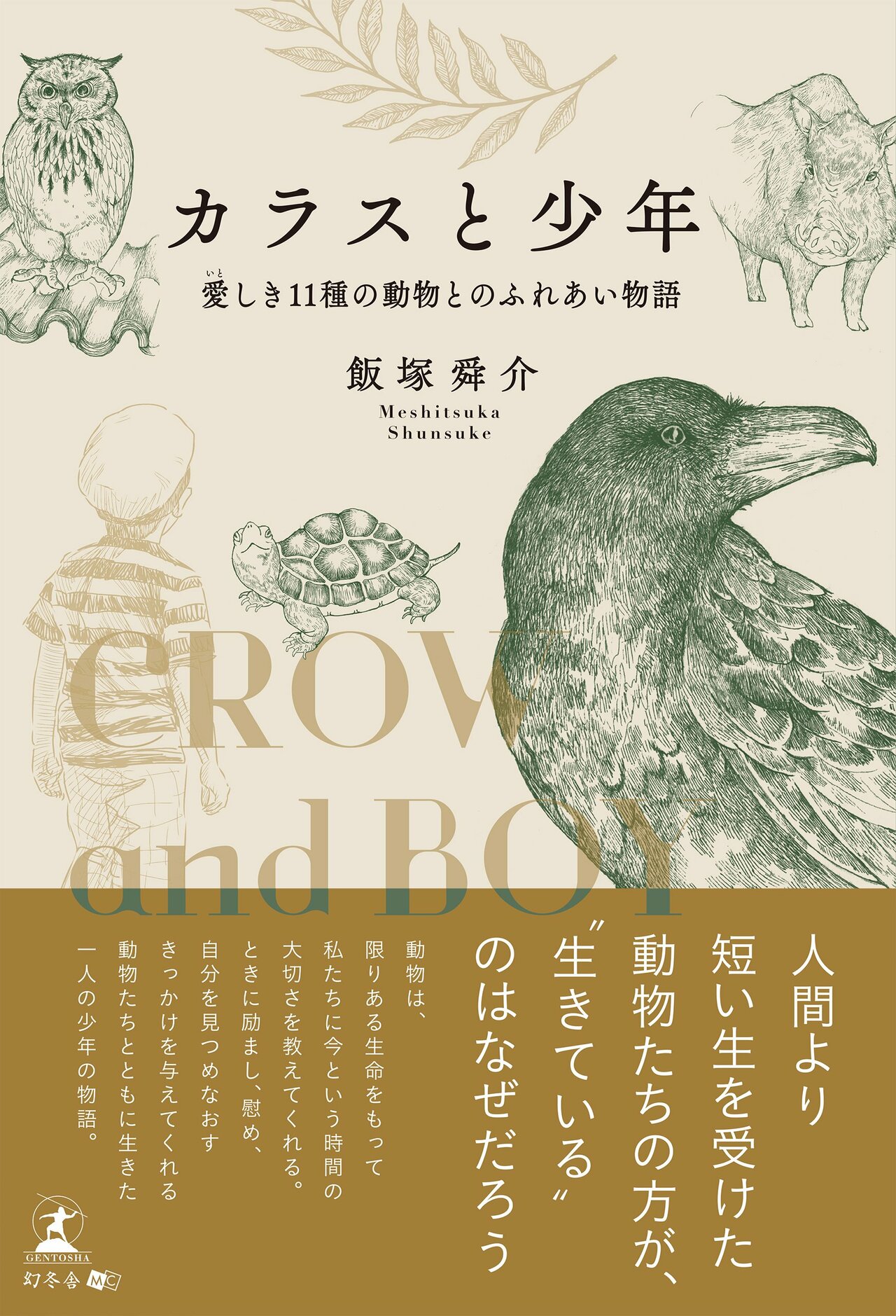外から見ると、屋根の破風(はふ)の下は、1辺が2メートルもある三角形の煙抜(けむりぬ)きの大きな穴(あな)が空いています。
おじいさんは、
「江戸時代までは日本は煙突(えんとつ)を作ることを知らなかったので、煙抜(けむりぬ)きが必要だったのだよ」
と説明しました。昔の台所では薪(まき)を燃料(ねんりょう)にしていたため、もうもうと上がる煙(けむり)を逃(のが)す仕組みが作られていたのです。
「明治時代になって、西洋から煙突(えんとつ)が入ってきたらしい。この家の台所の煙突(えんとつ)は後からつけたものでね」
と説明してくれました。かまどには煙突(えんとつ)がつけられましたが、煙(けむり)は焚(た)き口(ぐち)にも上がってくるので煙抜(けむりぬ)きは役立ちます。さらに夏には上昇気流(じょうしょうきりゅう)が生じて、天然のクーラーの役割もしました。
しかし、冬の吹雪(ふぶき)の日には雪が舞(ま)い降(お)りてきて、寒い台所でした。朝は流し台には決まって厚(あつ)い氷が張(は)っているのです。朝、かまどに火が焚(た)かれると、湯気が立ち、室温が上がって暖(あたた)かくなってきます。
【前回の記事を読む】牛を売買する業者のトラックが着到した。ハナは、家の門から出るのを嫌がっていたが、そのうち諦めたように、荷台に上って…
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。