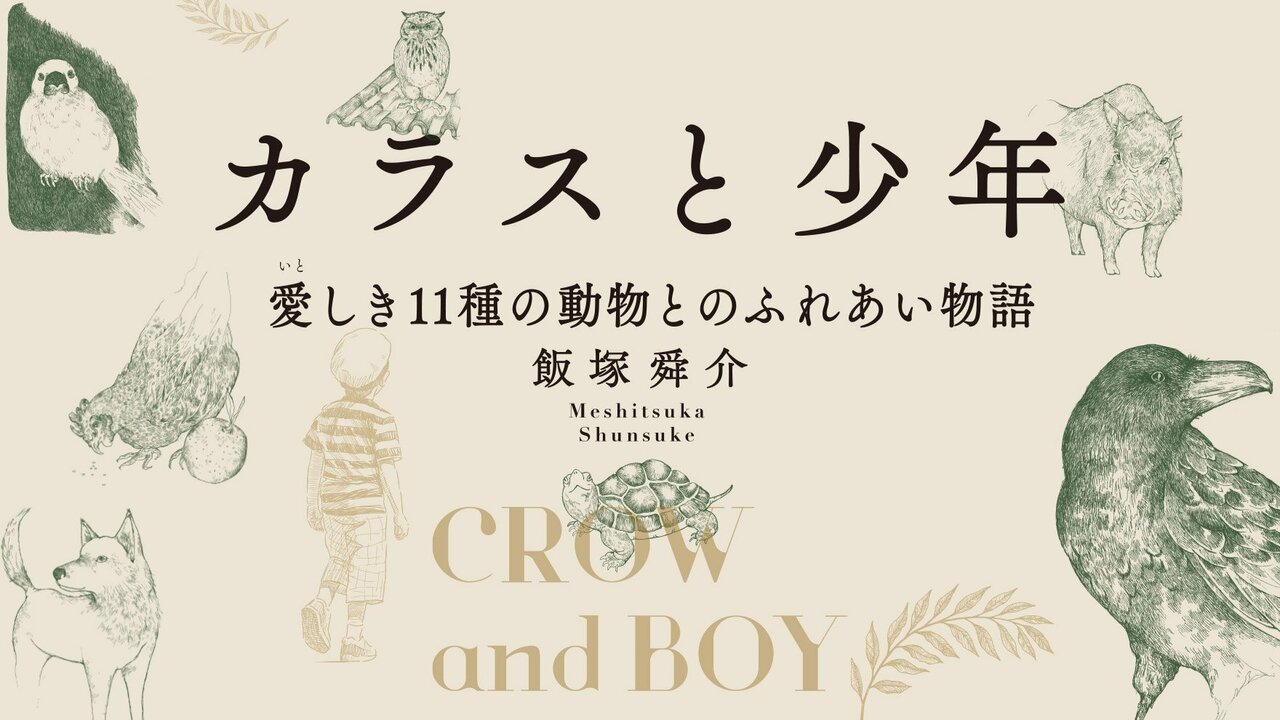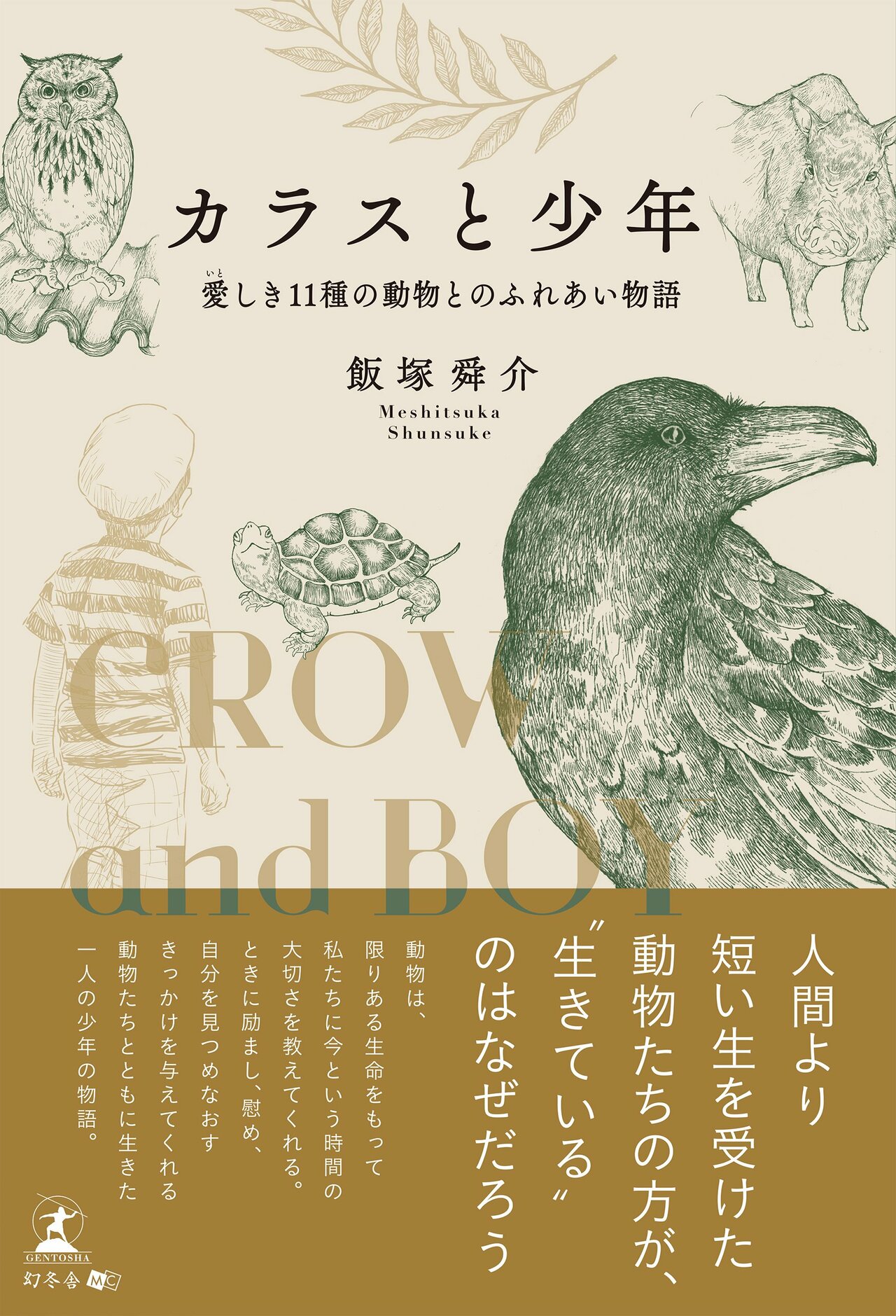家守のアオダイショウ
おじいさんの家
純二が暮(く)らしていたおじいさんの家は、築後(ちくご)200年ほど経(た)った日本家屋です。大きな家は典型(てんけい)的な田の字型構造(こうぞう)で、8畳(じょう)の間と10畳(じょう)の間が縦(たて)と横に3つ並(なら)んでいる建物(たてもの)です。壁(かべ)がないので、太い柱だけで建物(たてもの)を支(ささ)えています。
「ねえ、おじいさん、柱も鴨居(かもい)もどこも真っ黒に墨(すみ)で塗(ぬ)られているけど、何で墨(すみ)を塗(ぬ)るの?」と尋(たず)ねると、
「墨(すみ)を塗(ぬ)っておくと虫に食べられにくいのだそうだよ」
と教えてくれました。畳敷(たたみじき)の部屋の天井は高く、2階建ての住宅(じゅうたく)の吹(ふ)き抜(ぬ)け部分の高さほどもあります。それぞれの部屋の間は板戸か、ふすま、あるいは障子(しょうじ)です。家中の物音が全部聞こえますので、プライバシーはありません。
7月になると建具の立て替(か)えといって、障子(しょうじ)とふすまを細い葭(よし)でできた簾戸(すど)に取り換(か)えます。葭(よし)の間から隣(となり)の部屋が丸見えですのでプライバシーはさらになくなりますが、換気(かんき)は抜群(ばつぐん)ですので、熱がこもりません。
エアコンのない時代この地方の農家では、できるだけ暑い夏を過ごしやすいような北向きで風通しのいい家を建てていました。暑い間は朝から晩(ばん)まで田畑で働くので涼(すず)しい家で休んで疲(つか)れを取ることが大切だったのです。冬の間はこたつにあたって暖(あたた)かくなる春が来るのをじっと待つのです。