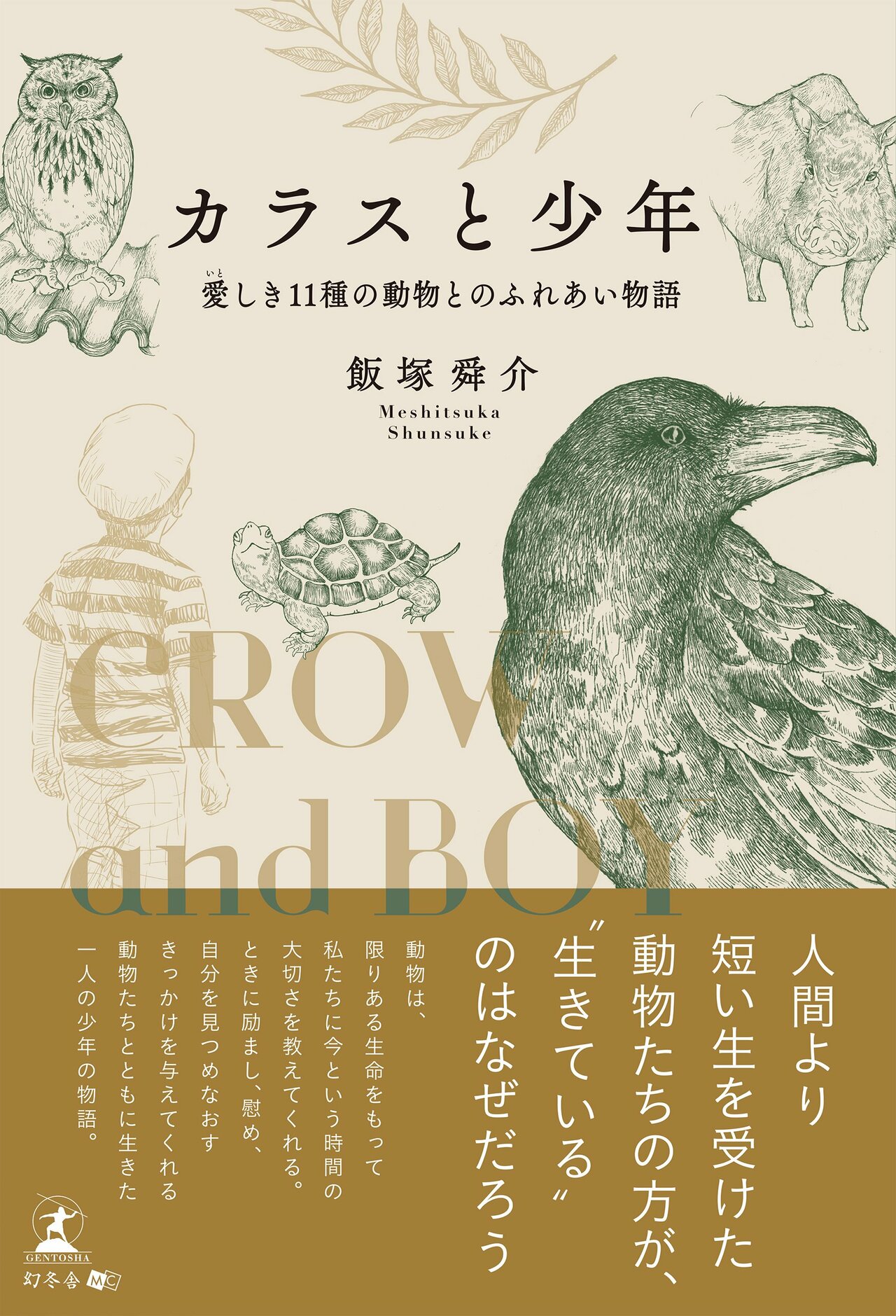大黒柱(だいこくばしら)
玄関(げんかん)を入ったところは広い土間で、縄(なわ)や草履(ぞうり)、むしろなどを作るわら仕事や、秋には玄米(げんまい)を俵(たわら)に詰(つ)める作業にも使われていました。
土間には天井が張(は)ってないので、見上げるとひと抱(かか)え以上もある梁(はり)が縦(たて)横に何段(なんだん)も組まれていて、頑丈(がんじょう)な建物(たてもの)であることが分かります。
中心にある大黒柱(だいこくばしら)が大きな梁(はり)を支(ささ)える構造(こうぞう)です。幅(はば)が30センチメートルもある大黒柱(だいこくばしら)はケヤキの木で作られていて、この柱だけつるつるに磨(みが)かれて光っています。
「おじいさん、たくさん柱があるのにこの柱だけを特別に、何で大黒柱(だいこくばしら)というの?」と尋(たず)ねますと、
「上の梁(はり)を見上げて、こちらの梁(はり)も、あの梁(はり)もどれも大黒柱(だいこくばしら)が支(ささ)えているよ。大黒柱(だいこくばしら)がダメになるとこの家は倒れてしまうのだよ。他の柱は取り替(か)えることができるが、大黒柱(だいこくばしら)は取り替(か)えられないよ」
と説明してくれました。
「他にたくさん柱があるのに、大黒柱(だいこくばしら)は1本だけ特別な役割の柱だね」と純二が言うと、
「そこから、一家の中心となる人を例えて、大黒柱(だいこくばしら)というのだよ」
と教えてくれました。大黒柱(だいこくばしら)の上を見上げると、梁(はり)の間から、屋根を支(ささ)えている太い垂木(たるき)も真っ黒く煤(すす)けて見えます。垂木(たるき)がよく見えるのは、煙抜(けむりぬ)きから外の光が差し込(こ)んでいるからです。