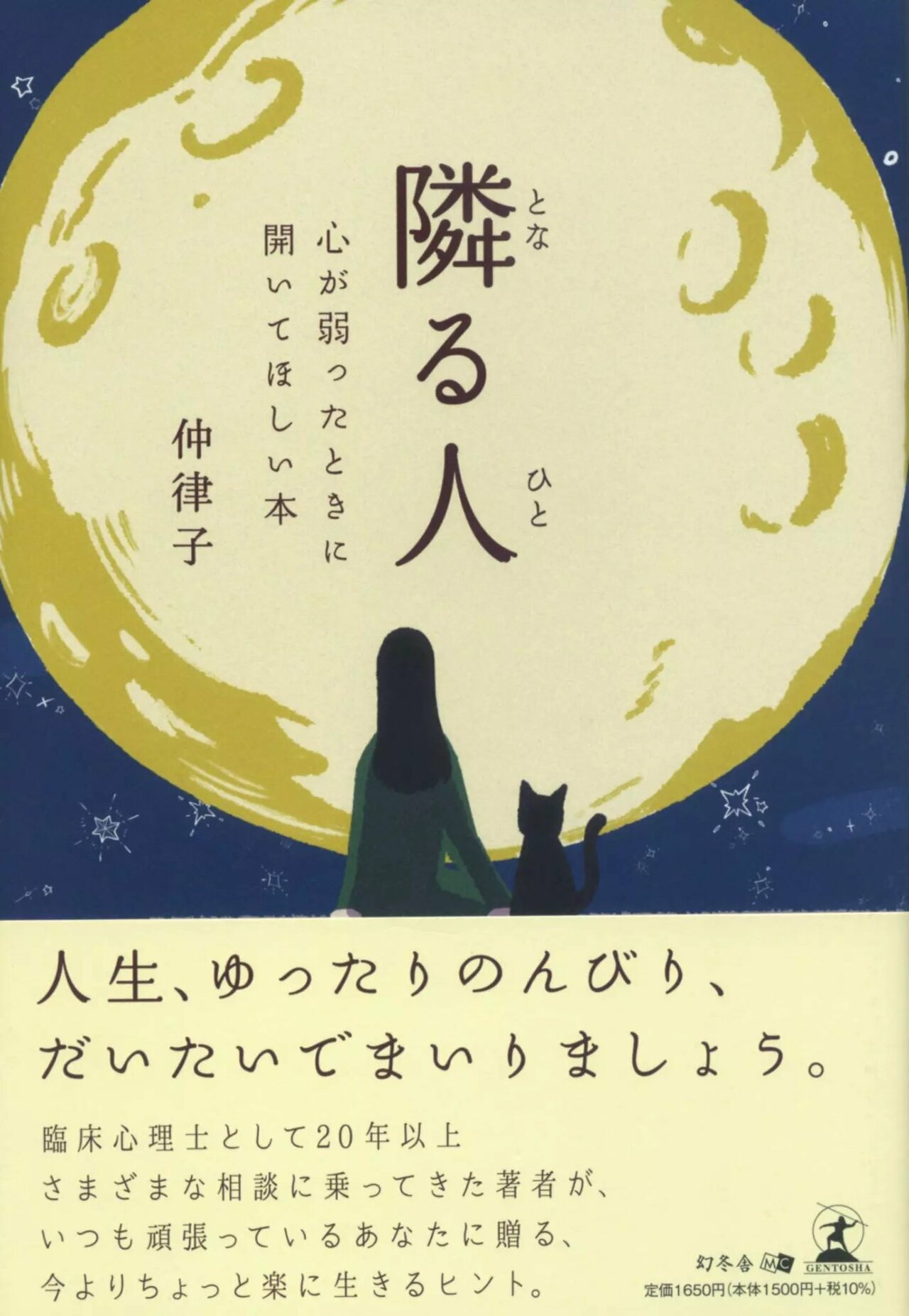良寛さんの恋
江戸時代の僧侶である良寛は、子どもとかくれんぼをしたり、手鞠で遊んだりと素朴で優しいイメージがありますが、生涯寺を構えず、禅を極め、物質的にも無一物に徹して、清貧の思想を貫いた人だと言われています。その良寛が晩年に熱烈な恋をしたことを、みなさんはご存知ですか?
それは良寛が七十歳の時のことです。三十歳の貞心(ていしん)尼(に)が良寛を訪ねていきます。良寛は留守だったので、貞心尼はおみやげの手鞠と歌を残して立ち去ります。良寛はこれを受け取り、すぐに返歌を送りました。それが恋の始まりです。そして歌を贈り合うことで、二人は愛を育てていきます。
いついつとまちにしひとはきたりけり いまはあひ見てなにかおもはぬ(良寛)
そして、この歌のように貞心尼は良寛にとって「いついつと待ちにし人」となっていくのです。ステキですね。お金や名誉を捨て清貧の思想を貫いた人が、人生の最後に恋に落ちるのです。
人間国宝の鎌倉芳太郎さんは、貞心尼と良寛の書について『良寛と貞心尼 新装版』(加藤僖一、考古堂書店、2017)にて以下のように述べています。
「貞心尼書のリズム、脳波の波長というようなものが、良寛と極めて近く、また酷似しており、この二人の間には、電波のように、テレパシィというか、それが目で見、耳できき、相通じあうであろうという可能性を知りました。(中略)良寛書は貞心尼に会って、それまでの技巧の書から、愛情(情感)に満ちた、そして波長の高い、美しい書となって、完成していると思われます」
おそらく良寛は、貞心尼と出逢うまでの七十年間で人間として完成形に近い精神性を確立していたに違いありません。江戸時代に七十年間を生きて、もうこれ以上上昇することはないと達観していた時に、貞心尼と出逢ったのです。
おそらくそれは良寛にとって感情を揺さぶられる出来事だったのではないでしょうか。貞心尼と愛し愛される喜びを知り、それが彼の芸術活動を完成に導いていったのではないかと思います。きっと二人にしかわからない至高の愛を育んでいったのではないでしょうか。
そして、貞心尼は良寛が亡くなった後、三十八歳の時に最初の良寛歌集『蓮の露』、七十歳の時に最初の良寛詩集『良寛道人遺稿』を完成させるのです。
現在の発達心理学の成人期以降のテーマは専ら家族の関係性ばかりです。でも、結婚をしない人たちが増え、高齢化が進む昨今、最後はみんなおひとりさまになる時代、中年期以降の恋愛や友人関係についてさらに研究する必要があるのではないかと、良寛と貞心尼に教えられたような気がします。
【前回の記事を読む】”家族”から自由になればラクに生きられるのになあ…家族という形態を重要視する日本。それにがんじがらめにされて…
【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...