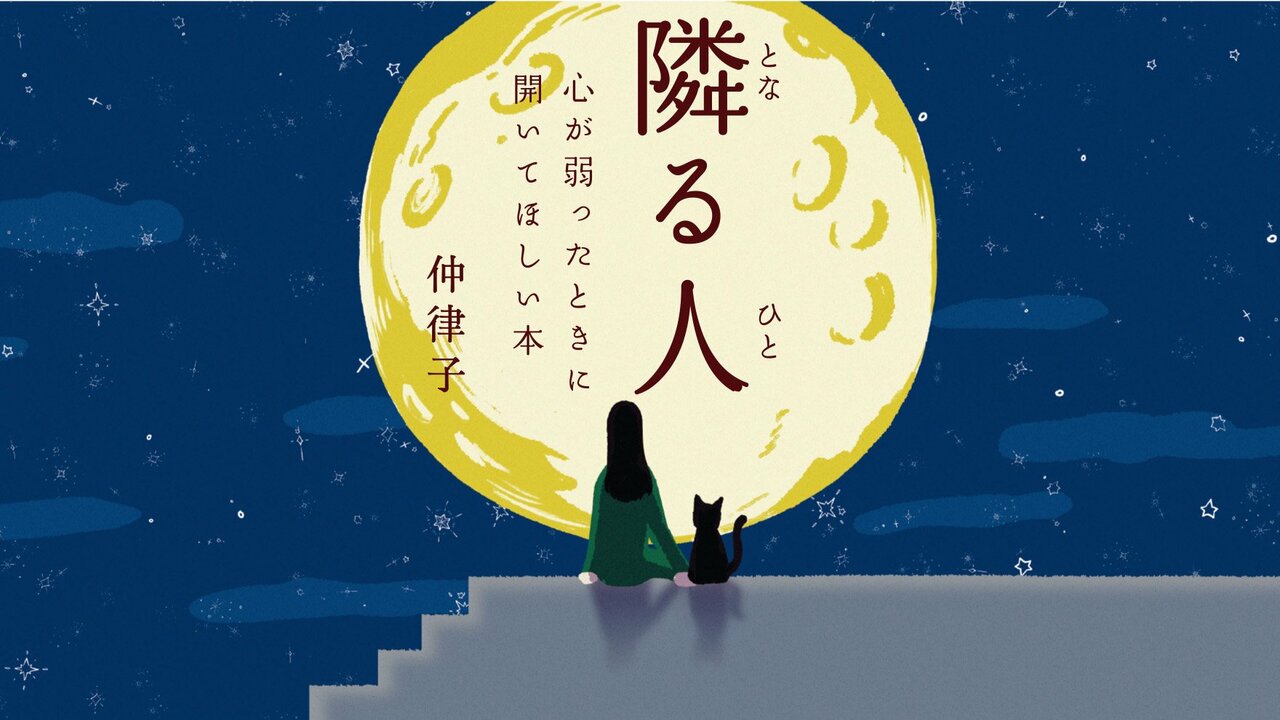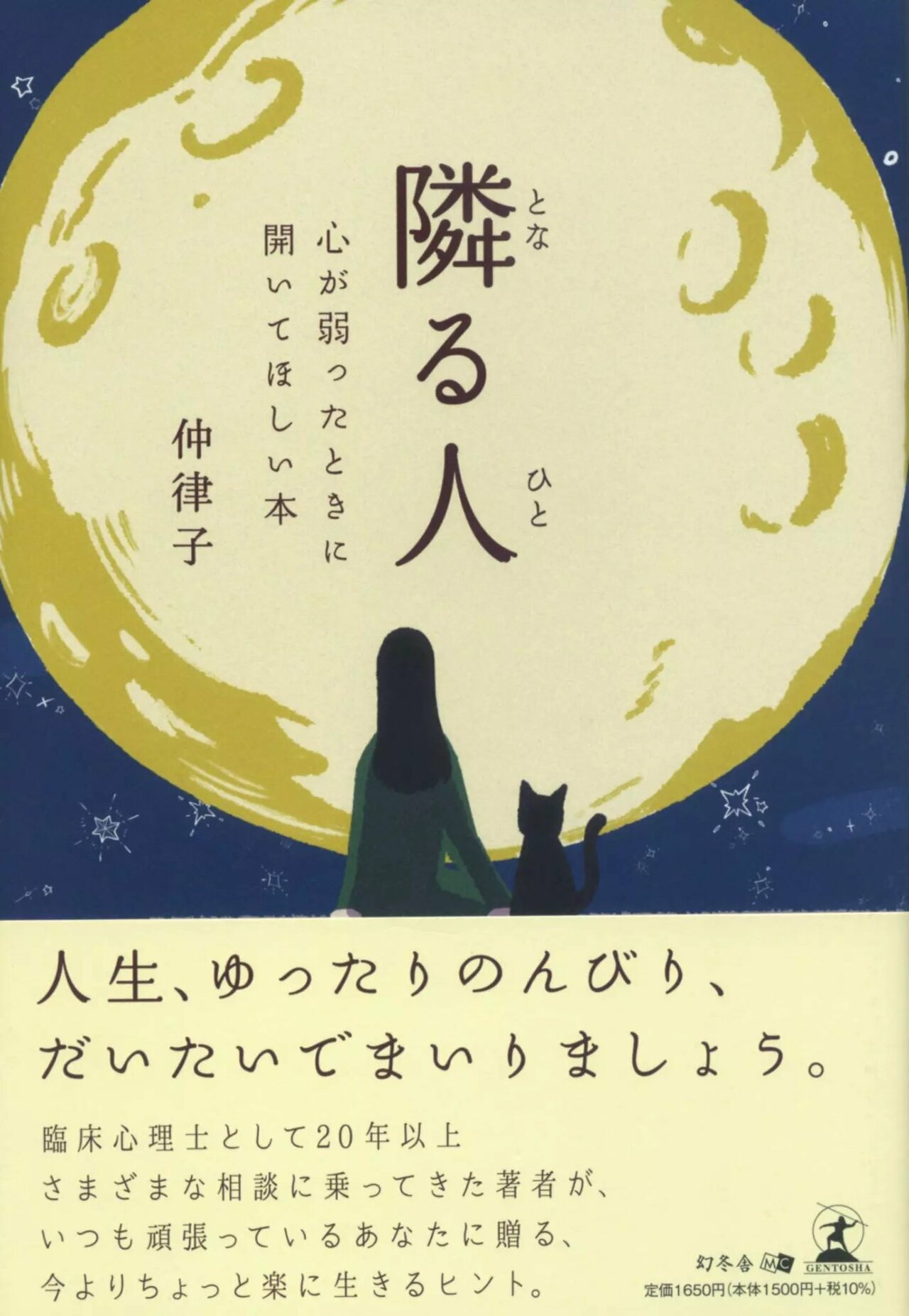第三章 隣る人
グレートマザーの光と影
先日、元養護教諭の先生が「七十歳になっても、母親に支配されて生きている人がいるのよ」と教えてくれました。いくつになっても母親という存在は大切で難儀なものです。そこで、今回は母親について書いてみたいと思います。
ユング心理学では、母という要素には二面性があり、一つには子どもを慈しんで育む力、もう一つは子どもを束縛し、のみこんで破滅させてしまう恐ろしい力があるとされています。
母のイメージは、あらゆる物を育てる偉大な母(グレートマザー)で、女性の成長の究極的な目標だとされていて、それは〝母性〞という言葉に集約されています。この母の偉大なイメージが難儀なのです。後者の子どもを束縛し、のみこんで破滅させてしまう恐ろしい力がクローズアップされていないのです。
思春期の課題に、自立や心理的離乳があるのですが、この時にグレートマザーと対決して、心の中で母親殺しをしなければならないと言われています。それはシンプルに母親の支配から逃れるためです。上下の関係性から、一対一の人間としての対等な関係性を再構築するスタート地点に立つというイメージでしょうか。いわゆる死と再生です。
そういえば、中二の息子がタイムラインで、ある投稿にいいねを押していたのを目にしました。
その内容は、「母親に死ねと言ってしまった。中三のある夏の暑い日、俺が楽しみにとっておいたアイスクリームを母親が弟に食べさせてしまった。その時、母親に〝死ね〞と言ってしまった。それから何時間か経って母さんが轢かれた。アイスクリームを買いに行っていたと知った。母さん……ごめんよ。俺が最後に死ねと言ってしまったことをずっと後悔している」というものでした。
被害者支援をしている立場からすれば、母親の交通死はとても痛ましい出来事であり、「死ね」と言ってしまった息子の自責感に苛まれる苦しみが想像できるのですが、発達心理学を専門としている私はこのタイムラインにいいねを押した我が息子に母親殺しという象徴を感じ、不謹慎にも嬉しく思いました。
この頃から、息子は一階のリビングから二階の自室で寝るようになりました。話しかけてもムス〜っとしていて、(お〜っ反抗期! 心理的離乳!)とその成長をたくましく思ったりして。
実は、この思春期の頃に心の中で行う母親殺し。これができないとグレートマザーにずっとのみこまれ、破壊されてしまう可能性があります。それが冒頭の七十歳になっても母親に支配されている現状を生み出す一つの要因でもあるのだろうと思います。母親と子どもとの関係性を健全に保つのは結構難しいことなのかもしれませんね。