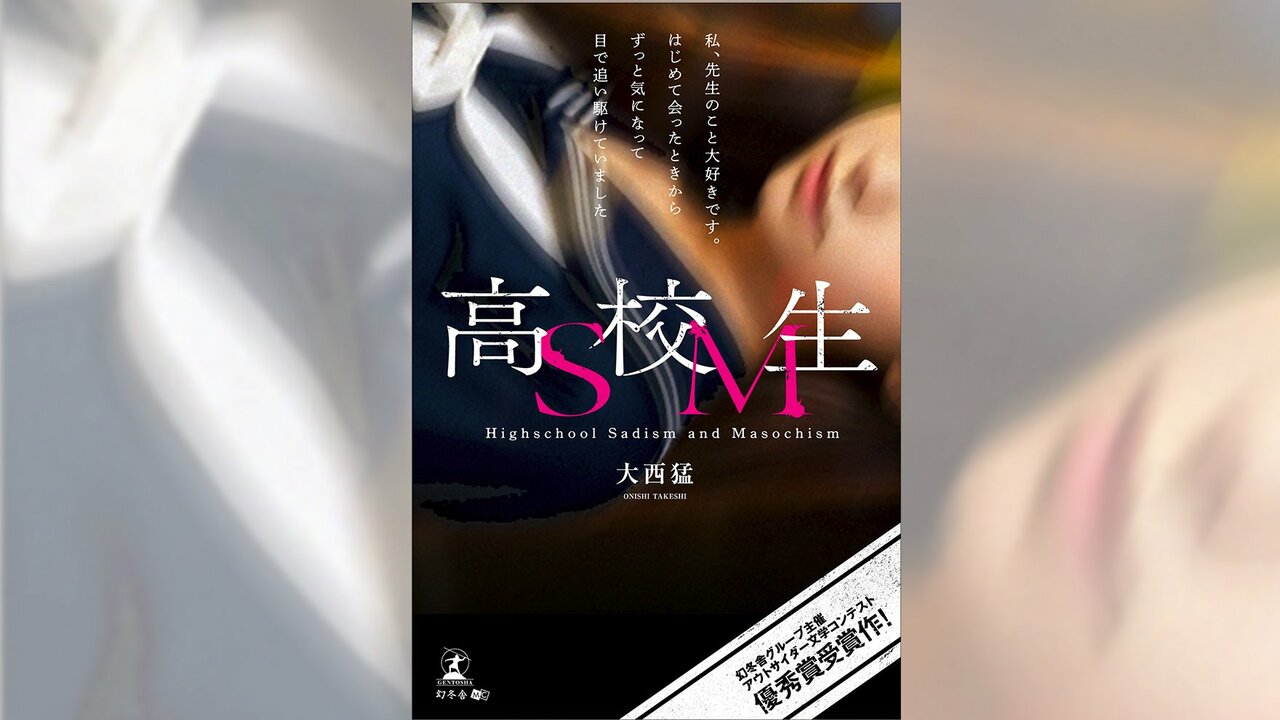3
そしてまたあの嫌いな休みが来た。私とあの人を断ち切る冬休みだった。夏に比べればその時間は半分にも満たなかったが、その間一切あの人と会えなくなるという点では変わらなかった。私はあの人に会えない寂しさと会えたとしても何も変わらないのだという寂しさを両方噛みしめながら寒くて陰鬱な冬の日々を過ごした。
冬休みが明け、三学期がはじまっても、私の寂しさの片方だけはやはり消えなかった。毎日教壇で見るあの人は、はじめて会った日と同じく他人行儀でよそよそしかった。そして授業終わりに廊下で立ち話するときのあの人も少しだけ笑顔を見せてくれる以外は、今までと大きな変化はなかった。
あの人はいつまでたっても先生のままだった。私の思いに気づこうとすらしなかった。私はもしこのままあと二年間を過ごすならいっそ別の先生に世界史を教わった方がましだった。そうすれば思いに胸を焦がす辛さを味あわなくてすんだ。何も変わらないあの人を見続けるぐらいならいっそ何も見ない方がよかった。
しかしもちろんそれは心からの願いではなかった。私が心から願うのはあの人にもっと近づくことだった。いつか夢見たような、二人で手を繋いで綺麗な景色の中を歩くことだった。
きっとそれが実現したら想像もできない幸せに包まれるだろう。今感じている苦しみがちっぽけだったと思えるほどに。私はやはり諦められなかった。諦めたら、今以上の苦しみがこの先に待っているだろう。
そんな未来は望んでいなかった。それならまだあの人へ思いのたけをぶつけて、拒絶されるほうがよかった。そしたら諦めもつくだろう。でも何もしないで諦めることだけはできなかった。私はあの人への気持ちにちゃんと決着をつけたかった。二月に入る前に私はバレンタインチョコをあの人にあげようと決めた。
実はチョコをあげるのは中学三年生のとき以来二度目だった。そのときあげたのは江畑先生という当時の担任だった。江畑先生は生徒から電柱というあだ名をつけられるような、痩せたさえない教師だった。
私はずっと片思いをしていたが、三年生のときにチョコを渡すまでは一度もその思いを伝えることができなかった。でももう同じ過ちは繰り返したくなかった。中学生のときのように何も相手に伝えられないまま無為に三年間を終わらせたくなかった。
あの人も私からチョコを貰えば嫌でもその思いに気づくだろう。それでどんな答えが返ってくるかはわからなかった。もしかしたら拒絶されるかもしれない。今まで以上に壁を作られるかもしれない。でも逆に思いを受け入れてくれる可能性もゼロではなかった。