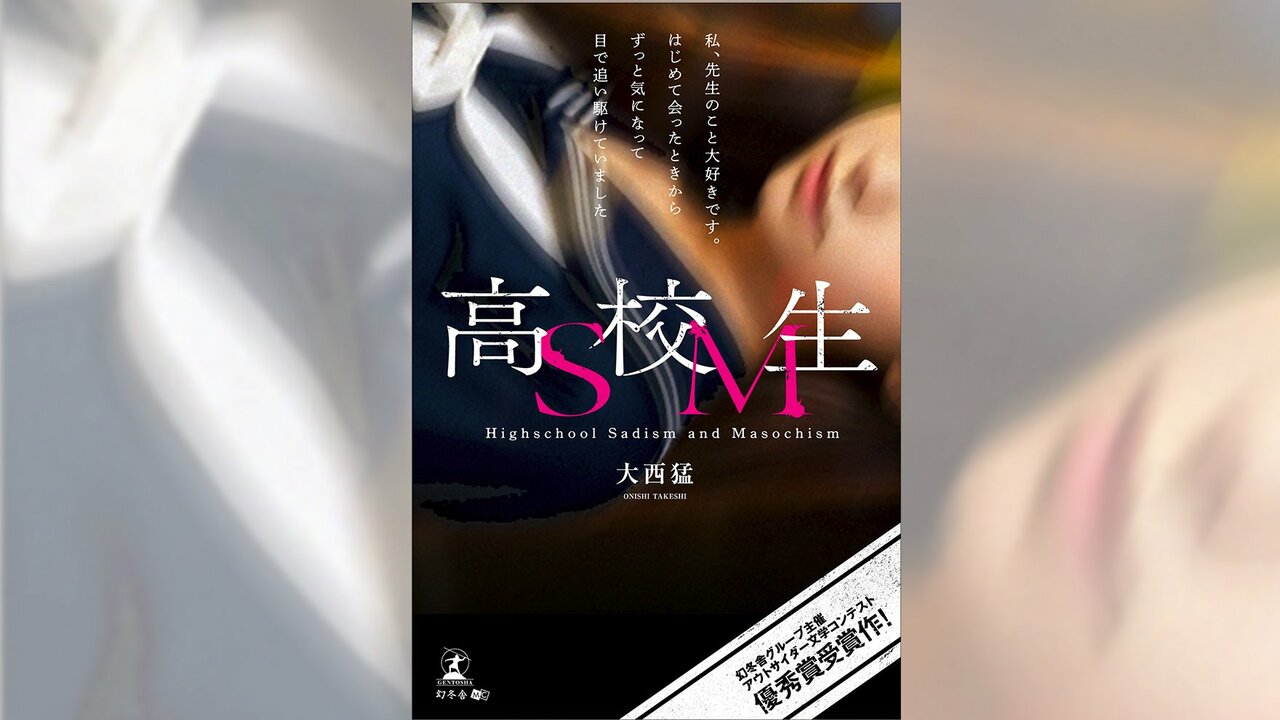3
授業が終わってあの人が教室を出て行くとき、私は後を追い駆けた。しかし、走り出した足は急に止まった。なぜかあの人の背中が遠くに感じられたのだ。
あの人は私の存在にはまるで気づかず、どんどん前に進んだ。そのとき私は思った。これがあの人の答えなのかしれないと。何も言わないことこそが感想なのかもしれないと。それは拒絶だった。私の思いは届かなかったのだ。私が作ったチョコはあの人の口に合わなかったのだ。
私は追い駆けるのを諦めた。そしてあの人の背中が見えなくなるのをじっと見送った。心は半分崩壊しかかっていた。私は泣くなと自分に言いきかせた。泣いたら心が完全に崩壊しそうだった。
その後に受けた授業の記憶はまったく残っていなかった。私はただ悲しみに張りつめた心の均衡を保つのに必死だった。あの人への大きすぎる思いは破れたとたん、大きすぎる苦しみに変わった。
泣くなと何度も自分に言いきかせたが、教科書に数滴涙がこぼれ落ちるのを止めることはできなかった。もう限界だった。私は早く一人になりたかった。
帰りのホームルームが終わると、すぐに教室を飛び出した。私は下駄箱まで走った。押し寄せてくる悲しみに足元をすくわれないように。そして、急いで靴に履き替え、一刻も早く学校から逃れようとした。あの人のいる学校から。
そのとき、誰かが私の名前を呼んだ。私は驚いて振り返った。あの人がそこに立っていた。私はすぐこれは幻覚だと思った。
「先生?」
あまりにもリアルなあの人の姿に私はついに狂ったのかもしれないと思った。
「ごめん、驚かせちゃって」
あの人は申し訳なさそうに謝った。それは本物のあの人だった。聞き取りづらい声も、丸めた背中も本物だった。私は混乱し、取り乱した。
「この前もらったチョコのお礼を言いたくて」
私は自分の耳に聞こえる声を信じられなかった。そして続いて言ったあの人の言葉はもっと信じられなかった。
「すごく美味しかったよ。ありがとう」
やはりこれは夢なのだと思った。自分は狂って幻覚を見ているのだと。辛い現実から逃れるために都合の良い現実を作りだしているのだと。私は信じなかった。信じてまた裏切られるのが怖かった。
「あれ、本当に手作り? 売ってるチョコより全然美味しかったよ。川北さんは勉強だけじゃなくて、料理も上手なんだね」
あの人は笑っていた。なんて素晴らしい夢だろうと思った。私は幸せだった。でもこれは夢だった。そうに決まっている。もしこれが夢じゃなかったら私は幸せすぎて泣いていただろう。