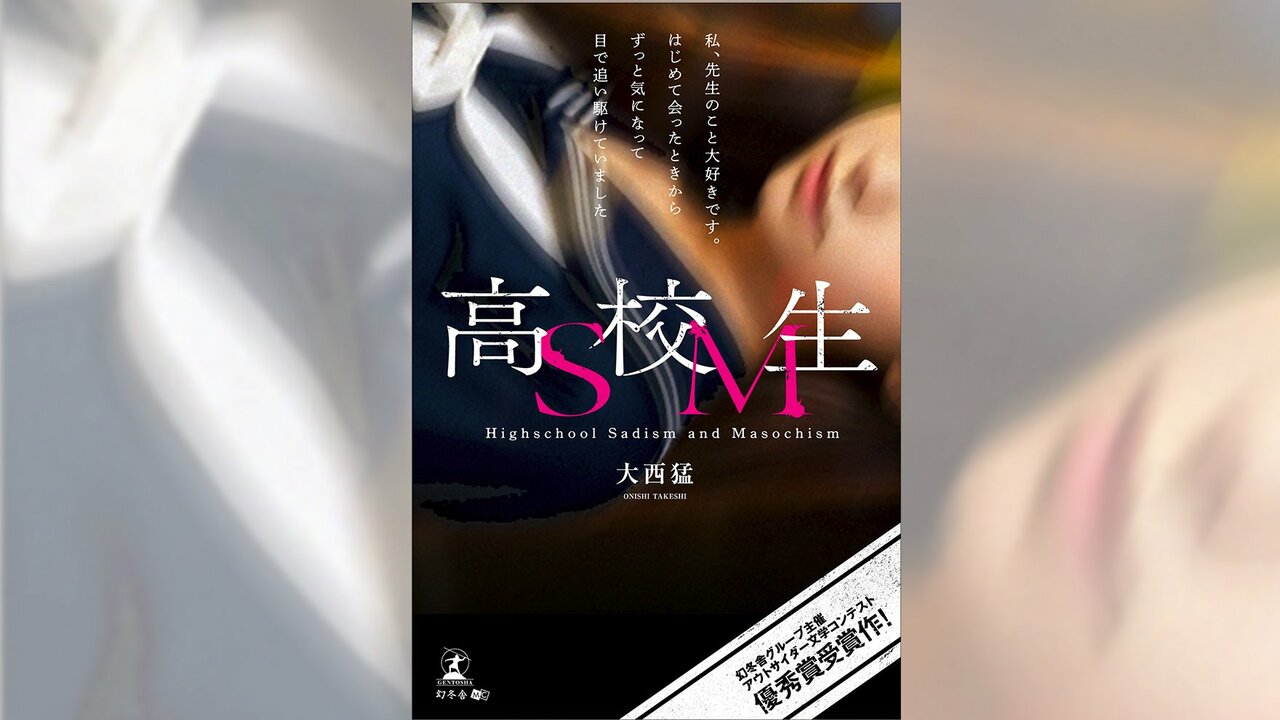3
授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。あの人は小さく頭を下げてから、教壇を下り、いつもと同じように足早に教室から出て行った。私は引き出しのチョコを手に取った。それは水色の包装紙で包まれていた。誰も私のことなど見ていなかった。私は急いで教室の出口に向かった。
あの人は数メートル先を背中を丸めて歩いていた。いつものように真ん中は生徒に譲って。私は駆け出そうとして、止めた。周りに人目が多すぎた。もしチョコをあの人にあげているのを見られたらすぐ噂になるだろう。私はあの人の後ろを同じスピードでついて歩いた。
階段を降りて一階に着くと、辺りは急に静かになった。私は渡すなら今だと思って駆け出そうとしたが、反対から国語の先生が歩いて来るのを見て慌てて止まった。先生はあの人とすれ違うと会釈し、それから数秒後に私とすれ違った。私は平静を装って頭を下げた。先生は私が背中に隠したものに気づかず通り過ぎていった。
廊下にはついに私とあの人だけになった。その先には職員室があった。私は床を蹴って駆け出した。
「先生」
あの人が職員室の前で立ち止まるのを見て、私は声を出した。あの人はドアに伸ばしていた手を下した。
振り向いてそこに私がいるのを見たあの人は「どうした?」と、やはり今日がバレンタインデーだということは一ミリも考えたことがない呑気な顔で聞いてきた。私はたった十メートルほど走っただけなのに、呼吸が苦しくなっていた。呼吸を整えるために、大きく息をした。あの人は何も言わず私のことを見ていた。
「あの、これ。もしよかったら受け取ってください」
私は最後に大きく息を吐き出すと背中に隠していたチョコをあの人に差し出した。
「これは何?」
まだここにきてもあの人は気づいていなかった。私は呆れると同時にそんなあの人が愛おしく思えた。
「チョコです。バレンタインの」
あの人は「ああ」と明らかに今日がバレンタインだと知った顔で頷いた。が、すぐその顔は驚きにとって変わった。
「僕に?」
私は頷いた。あの人の顔にはさらに驚きが広がった。それは私が想像したのとまったく同じ顔だった。私は笑いが込み上がってくるのを必死に抑えた。
「もしチョコ嫌いじゃなかったら食べてください。手作りなので味は保証できませんが」