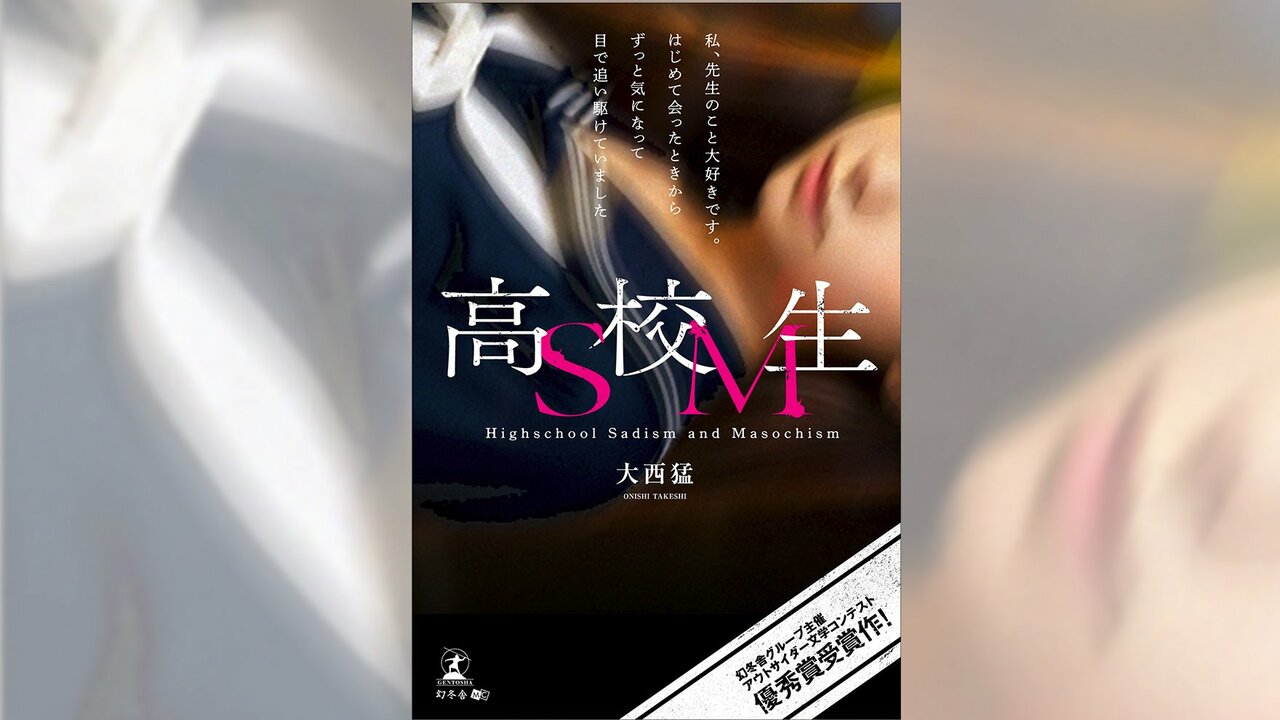3
「じゃあ、僕は戻るよ」
「帰るんですか?」
「いや、やらなくちゃいけない仕事があって」
いつの間にかあの人は他人行儀ないつもの顔に戻っていた。やはり私の思いは届いていなかった。しかし落ち込んだのは一瞬だった。背を向けて立ち去ろうとする姿を見て、私は思わず「職員室まで一緒に行っていいですか?」と言った。
「別に構わないよ」
あの人は驚いた顔でそう答えた。
私はあの人と二人で図書室を出た。並んで歩くのははじめてだった。私は自分の足が地面から浮いているようなふわふわした感覚に陥った。すぐ隣にあの人が自分と同じ歩幅で歩いているのが信じられなかった。
手は伸ばせば触れられる距離にあった。私は頭の中であの人の手を握る自分を想像した。あの人の手は温かくて、大きかった。私の手は自然と熱を帯びた。あの人の血が私の手の血管を伝って、体中を巡っているようだった。
私はあの人の横顔を盗み見た。するとあの人が気づいて目が合った。
「どうしたの?」
あの人は不思議そうに聞いた。
「いえ、なんでもないです」
私は慌てて首を振った。
あの人は何も知らなかった。なぜ私が一緒に職員室まで行きたがるのか。なぜ目が合っただけで心が騒めくのか。あの人は何も知らなかった。その心は近くにいながら遠くにあった。手と手は数センチしか離れていないのに実際に触れ合うことはできなかった。
私の目の前にいるあの人はさっき本棚の陰から見たあの人ではなかった。私に見られていることを知っていて、壁を作っていた。 私は拒まれていた。その心の中に入ることを許されなかった。
「先生、質問してもいいですか?」
「何?」
「先生は一人暮らしですか?」
「そうだよ」
「地元がこっちなんですか?」
「地元は山口」
「こっちにはいつ越してきたんですか?」
「東京に来たのは大学進学のときだから二十七年前になるかな」
あの人はどうしてそんなことを聞くのかという顔をしていた。でも私はあの人のことをもっと知りたいという欲望を抑えられなかった。
「それからずっとこっちですか?」
「そうだよ」
「じゃあ、こっちのほうが長いんですね」
「そうだね」
「結婚はされてるんですか?」
私は何気ないふりをして、でも実際は心臓が止まりそうになりながら聞いた。