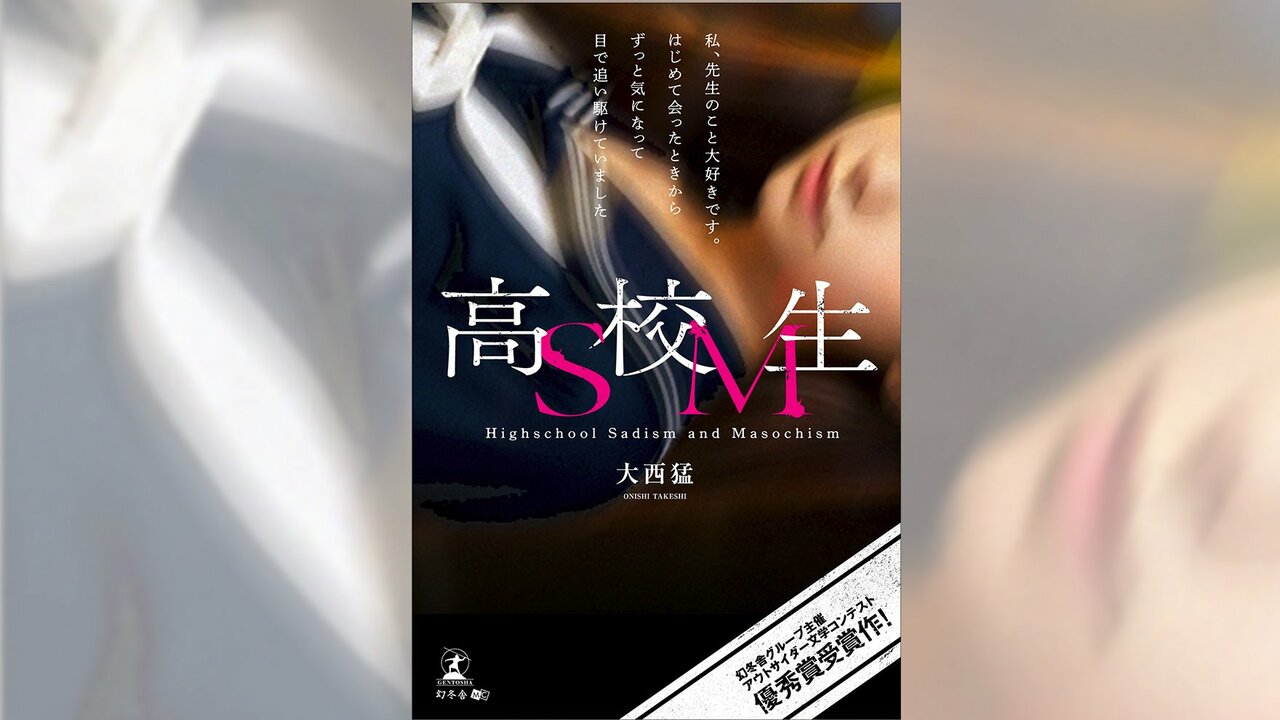3
壁などはじめから存在しなかった。壁があると思い込んでいるのは狭い常識のせいだった。私は自分が生徒だからという理由だけであの人を諦めたくなかった。
あの人にも私が生徒だからという理由だけで距離を置いてほしくなかった。常識の枠に収まることがいかに愚かで危険なことか、教えてくれたのはあの人だった。あの人への愛を諦めることはまさに愚かなことだった。私はあの人を愛していた。それはあらゆる常識や道徳から解放された真実だった。
苦しみが増す一方で、こんな苦しみに負けてたまるかという思いも強くなった。私は自分の気持ちに素直になろうと誓った。そして簡単にあの人を諦めないことも。
私はあの人に近づきたかった。その先に深い絶望が待っていたとしても。望むところだった。私は気づかないうちに、逆境を恐れない強い人間になっていた。それもあの人のことを好きになったからだった。私はあの人と会ってから確実に変わりはじめていた。
ある日の放課後、誰もいない学校の図書館で本を探していると、世界史のコーナーにあの人の姿を発見した。私は本棚の陰から気づかれないようにあの人を見つめた。
そこにいたのは誰の視線も意識していない無防備なあの人だった。猫背なところは教壇の上にいるときと同じだったが、自信なさげな表情はなく、代わりに食い入るように本に目を走らせていたその横顔は、どこかギリシアの哲学者のような厳かな雰囲気すら漂っていた。
一週間ほど伸ばしっぱなしの髭もかえって威厳を与えていた。あの人は完全に自分の世界に入っていた。そのとき間違いなく周りに壁はなかった。
私はあの人を見つめながら、不思議な感情が芽生えるのを感じた。それはあの人に触れたいという感情だった。あの人の体に、あの人の頬に、髪に、唇に触れたいと思った。それは肉体的な欲望だった。
あの人の無防備な姿が私の心を誘惑した。あの人の体に触れたら、心にまで触れられる気がした。緊張感のない、弛緩しきった肉体は、無警戒な心そのものだった。
私は後ろから近づいていって、あの人に触れたい衝動に駆られた。肩を叩くだけでもいい。服の上からわずかな肉体の温かみを感じるだけでも。しかし、私はすぐそれが愚かな考えだと気づいた。そんなことをしたら、あの人はたちまち心に壁を作るだろう。
振り返ったとき、もうその目は警戒心に満ちたものになるだろう。それならありのままのあの人を本棚の陰からこっそり見ているほうがよかった。触れられなくても、近くにあの人を感じているほうがよかった。
私は目をこらしてあの人を見た。ページをめくる乾いた紙の音だけが耳に聞こえた。
やがて、あの人は本を棚に戻した。そして別の本を手に取り、しばらく眺めてからそれを脇に挟み、体の向きを変えた。